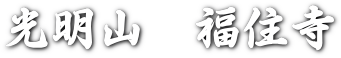住職のつぶやき
| << 次号 |
|---|
お盆の提案
お盆を仏教徒の先祖を敬う日に
8月といったら夏休み。海や山に遊ぶ計画が一番に優先しますが、忘れてはならないのはお盆の月であることです。ところによっては7月に勤めるところがありますが、札幌は8月です。
しかし、暦では、休日扱いではありません。国は盆ということで国民の休日には指定していません。
親を想う日、亡くなった人を想う日、先祖を想う日...
国がいのちの尊厳を思う日に定めてはどうでしょうか?
余談1 母の日
キリスト教から起こった母の日
5月の第二日曜日は母の日で親しんでいますが、聞くところによりますと、フィラデルフィアのウェブスターに住むアンナ.ジャービスという少女が、日曜学校の先生を長い間務めて死亡した母の追悼会に、一束のカーネーションを墓前に捧げたのがはじまり。やがて、この少女の麗しい母思いの話があちこちに伝わり、5月の第二日曜日にカーネーションを胸につけて母に感謝する習慣がはじまりました。それを、1914年5月9日 ウィルソン大統領は、合衆国議会で正式に5月の第二日曜日を「母の日」と定め官公庁では国旗を揚げるそうです。
教会や学校ではこの日母親を招待して記念式典をおこなうが、特に学校では日を早めその前の金曜日に行い、母を讃える歌をうたったり、母についての作文をづったりするそうです。
日本では、大正の初めころ全国の教会などで「母の日」がきめられ、本格的になったのは、昭和24年だそうです。このように、一少女の母に対する純粋な感謝と賞賛の気持ちを一束のカーネーンションを墓参に供える(アイディア)形がいつのまにか世界中にどんどんひろがって現在のようになったことを思うと、宗教、宗派を超えていのちの尊厳性を考える国民の日としてお盆は十分にその役割をはたせるのではないでしょうか...?
余談2 父と子の会話
お盆とは?
| 子供 | 「お盆ってなあに?」 |
|---|---|
| 父 | 「そりゃ 墓参りの日だよ」 |
| 子供 | 「墓参りなら、お盆でなくてもいいね」 |
| 父 | 「昔からお盆には墓に参るもの。それ以上はお寺さんにきいてみな」 |
| 子供 | 「住職さんお盆は本当はどんな意味があるのですか?」 |
| 住職 | 「何気なし行っていることも改めて聞かれると色々考えてしまいますね。日本のいろいろな行事のルーツを策って見ましょう」 お盆とはインドの言葉「ウラバンナ」と云う言葉から始まりました。それを中国では「倒懸」(人間が木から逆さまにつるされている状態.苦しんでいる事)と訳しています。ですから苦しみを表す言葉と受け止めていいでしょう。 お盆の行事は、起こりは遠く2500年前、お釈迦様の時代です。インドは4月の中旬から7月の中旬にかけてはひどい長雨で、虫が繁殖する 時季なので、お釈迦さまのお弟子方は心ならずも虫を踏んで殺害しないように外出をやめて、室内で研修をしました。その最終日が7月15日でこの日 を「自恣の日」と言って反省と懺悔をおこないます。 お盆は反省と懺悔の日です。 「ウラバンナ経」には、お釈迦様のお弟子の目蓮尊者は神通力で我が両親をながめると、父は仏の世界に母は餓鬼道の世界におられることを嘆きそのことをお釈迦さまに相談してご指示を仰ぎますと、お釈迦さまは7月15日の「自恣の日」に多くお坊さん達に供養を勧められその孝養によって母が餓鬼道から救われるという内容です。 この経をいただくと我が子がかわいいという母の自己中心の行いを指摘し人間の自己愛を考え直します。 その故事から、母を、親を、先祖を想い今の自分を見つめる為にお寺や墓にお参りします。 |
| 住職 | 「簡単に一言で言うと自分を生んでくれた母への感謝と母(人間の代表)が持っている自己愛の深さを振り返る日かな。お参りによって自分を振り返り反省する日」 |
| 父 | 「ご先祖様ありがとうございます。とお参りはしてきたけれど..そのような意味でしたかなァ」 「でもありがとうでいいんですね」 |
| 住職 | 「先だった人ありがとう。生かされてありがとう」 |
| 子供 | 「ありがとうの日だね」 |
 |
|---|