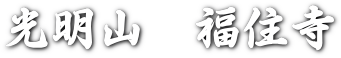| << 次号 | 前号 >> |
|---|
「なむ」は平成2年から毎月発行している福住寺の寺報です。
月報「なむ」
2021年11月
「幸せ」と「仕合わせ」
「しあわせ」と聞くと皆さんは何を連想されるでしょうか。お金持ちになること、試験に受かること、仕事が成功すること、あるいは健康であること、恋愛が成就することでしょうか。
しあわせは一般的には「幸」と書きます。この漢字の成り立ちをご存じでしょうか。「幸」は象形文字です。上部の「土」と下部の「干」が二本の線で繋がっているこの字は、もともと枷(かせ)手錠を表わしていました。人を繋ぎ止めて自由を奪う「枷」=「幸」がしあわせの意味を持つようになった経緯は、実はあまりはっきりしていません。一説では、枷をはめられていた罪人が、それを外された時に感じる感情が「幸」になったともいわれます。しかし、私はむしろ「幸」とは繋がれた状態そのものなんだと考えた方が自然だと思います。
お金があることが「幸」と考えている人は、お金に縛られます。愛情を得ることで「幸」と思っている人は、愛情に縛られます。それらを手放すことなど不安で到底できません。モノや人に繋がれた、客観的に見れば自由を奪われている状態が、「幸」。うなずかれる方も多いのではないでしょうか。
お手元の辞書で「しあわせ」を引いてみてください。ほとんどの辞書でまず「仕合わせ」とあって、次に「幸せ」とあるはずです。「しあわせ」は「仕合わせ」です。これはさらにさかのぼれば「為合わせ」と表記されていました。「為」= 為(な)されたことが合わさること、つまり「めぐりあわせ」「他者と出会うこと」をしあわせと呼んだのです。ですから元々は、良いことだけではなく自分が望んでいない悪い事態も「しあわせ」とすることがあったようです。
仏教は「しあわせへの道」であるというのは、まさにこの意味、「他者との出会い・他者の発見」においてです。ちなみに、浄土真宗で最も大切なお経である「浄土三部経」は膨大な文字量ですが、「幸」という文字はただ一カ所見られるだけで、しかも「しあわせ」という意味では使われていません。
誰もしあわせを求めない人はいません。しかしそれによって互いを傷つけあうことが少なくないのが私たちです。自分のみのしあわせを求める心性が、他者の切り捨てや無視を選択し、結果的に自らの基盤さえ失ってしまうという愚を私たちは繰り返してきました。他者との出会いは、すなわち自分との出会いです。枷をはめてきた自らを見つめ直し解放することで開かれる仕合わせは、もしかしたら私たちのまったく予想しない姿で立ち現れるかもしれません。
本願寺出版社『やわらか法話3』松本智量(東京都延立寺)より抜粋