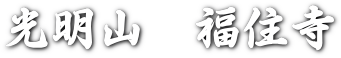月報「なむ」
2016年
百八ッの煩悩(除夜会)
2016年12月
年末になると、普段はどっしり構えている師匠も多忙に追われて慌ただしく走り回る。この「師走(しわす)」という言葉が表すように、日本人ほど年末の行事に忙しい国民は、そうそうないといえるのではないでしょうか。
新年の準備を開始する日を「事始め」といい、江戸時代には12月13日に「煤払(すすはら)い(大掃除)」を行う習慣があり、一家総出で行う煤払いは家の中の穢(けが)れを祓(はら)うという意味がありました。そして、大晦日の夜には、一年間の歩みをふり返りながら、新たな年へと仏恩報謝の生活を歩ませていただくための法要である「除夜会(じょやえ)」が全国の寺院で勤修され、人間の煩悩を消滅させるための梵鐘(ぼんしょう)が百八回突かれます。この百八という数は、
一、『貪欲(とんよく)』(貪(むさぼ)り)不必要なものまで欲張ること。
一、『瞋恚(しんに)』(怒り、腹立ち)自分の努力や思いやりを忘れ、他人のせいにしてしまうこと。
一、『愚痴(ぐち)』(愚かなる心)自分の見聞や経験でしか判断できないのが人間。自分自身は善であると思っていても、他人にとっては全く逆のこともあるということ。
一、『慢(まん)』(驕(おご)り高ぶりの心)自己中心的に生き、態度や言葉で人を傷つけ悲しませたりすること。
一、『疑(ぎ)』(疑い)疑い、勘繰(かんぐ)り、せっかくの親切を踏みにじり、疑心で人を傷つけること。
一、『見』(判断、見方)邪(よこしま)な眼鏡で、他人の真実をゆがめて見てしまったり、一方的な見解に囚(とら)われ、自分本位に結果を判断してしまうこと。
などの煩悩が人間にはあり、除夜の鐘とは、そんな私たちの言動や行い、考えを思い返し、煩悩まみれの自分に気づかせていただくためのものなのです。あらためて今年一年を振り返り、反省点を除夜の鐘の音に託しながら、真実の心で自らの煩悩の激しさを見つめ、救い難い私達をお救い下さる阿弥陀様のご恩に感謝させていただくお念仏生活を共々に過ごさせていただきましょう。
どうぞ皆さまお誘いあわせの上、福住寺の「除夜会」にご参拝下さい。お待ちしております。
《真宗法話辞典より》
声明クラブ・写経教室「スートラ」開講
2016年11月
9月24日、第8期「声明クラブ」が開講されました。
「声明」とは「梵(ぼん)唄(ばい)」、インドの唄という意味があり、仏教がインドから中国、日本へと伝わってきて下さったお釈迦さまの説かれたお経に、音の上がり下がりなどの節をつけて読む仏教音楽のひとつと言われております。
開講式では『讃仏偈』を唱和し、その後お勤め作法についての講義をいただきました。
「お勤め」という言葉の意味や、「お経」とは何なのか、何のため誰のために読経するのか、また、いのちのよりどころとなるお経本を開くときには、胸の前でお経本を両手で持ち、静かに額にいただいてから開く、閉じる時も同じ要領で大切に取り扱うことなどをわかりやすく学ばせていただきました。
お茶とお菓子をいただいた休憩後は、お焼香の作法などの講義でした。
首から下げる式章のかけ方、合掌する時のお念珠の持ち方、手の位置、礼拝する頭を下げる角度など、普段、何気なくしている合掌礼拝の作法は動作一つひとつが定められております。起立したまま焼香する場合、椅子に座った状態や正座での作法を学びました。
その後、受講者の方から「他の宗教での葬儀があった場合、その際の焼香の作法はどうしたらいいのですか?」という率直な質問がありました。
他の宗教、宗派の葬儀に会葬者として参詣することがあると思います。仏教では焼香をしますが、献花や玉串(たまぐし)奉奠(ほうてん)などをする宗教もあります。
他宗の葬儀では、「頑なにお念仏を称える」という思いより、喪主様が信仰している宗教を尊重し、その場その時に応じて失礼のないような作法、配慮が必要ではないでしょうか。
なぜ配慮が必要なのかと申しますと、他の宗教宗派の人であっても、「阿弥陀様の光に照らされた一人ひとりの尊いいのち」と言えるからなのです。
学びのいいご縁になります。楽しい「声明クラブ」お気軽にどうぞご参加下さい。
南無阿弥陀仏 たのみます 南無阿弥陀仏 ありがとう
2016年10月
お念仏を称える時、どんなお気持ちで称えていますか?
例えば、近々試験がありどうかその試験に合格しますように「南無阿弥陀仏」と称えたり、体の調子が悪くてどうか体の調子が良くなりますように「南無阿弥陀仏」と称えたり、宝くじを購入した後でどうかこの宝くじが当たりますように「南無阿弥陀仏」と称えたりしていませんか?私たちが称える「南無阿弥陀仏」は自己の欲望や願いを満たす為に称えるものなのでしょうか。
阿弥陀様は「われにまかせよ、わが名を称えよ、浄土に生まれさせて仏にならしめん」と苦しみ・悩みの多い私の人生につねに寄り添って下さっています。阿弥陀様の救いの力が私の称える「南無阿弥陀仏」となって、今この私にはたらき続けておられるのです。
私たちが称えているお念仏は、いつも私のことを心配し見守って下さっている阿弥陀様に対する報恩感謝の思いを念仏の声にあらわしているのです。だからお念仏(南無阿弥陀仏)は、自己の欲望や願いを満たすためのものではありません。
口に世事をまじえず ただ仏恩の深きことをのぶ、声に余言をあらわさず もっぱら称名たゆることなし(『御伝鈔』下巻第6段)
私たちも阿弥陀様への報恩感謝の思いからつねに「南無阿弥陀仏」とお念仏を申しながら、人生を歩んでいきたいものです。 (札幌組HP「今月の法話」より)
お彼岸をご縁に
2016年9月
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、北海道の短い夏が過ぎ去り、秋の訪れを感じさせる季節の到来です。「彼岸」とは、迷いの世界であるこの世「此岸」から、悟りの世界である「彼岸」(お浄土)へと到るということです。彼岸のお中日には太陽が真東から昇り、真西に沈みます。西方極楽浄土を憶い、すでに往生された故人やご先祖を偲ぶことで、他を顧みない自己中心的なあさましい私達を、西方のお浄土へと生まれさせ必ず仏にするぞとはたらいてくださるみ教えを味わう大切な仏教行事なのです。
よく人生は旅にたとえられます。「どこへ」「何のために」が明かでないと、その旅はあてのないものになってしまいます。どこへ行ってもそこには道があります。ではこの不安と混迷の現代社会を乗り越えるためには、一体どの道を歩んでいけばいいのでしょうか。
親鸞聖人はこんな私たちが救われる道はお念仏の道だとお勧めくださいました。それは『おかげさま』と生かされる道であり『ありがとう』と生き抜く道であるとお示し下さったのです。お念仏はお浄土(彼岸)に向かう道です。お浄土(彼岸)に生まれさせていただき、阿弥陀様の国で仏とならせていただくこと(成仏)が人間に生まれてきた大いなる旅の目的なのではないでしょうか。親鸞聖人は多くの道の中から、私達に最もふさわしい「お念仏の道」をお示し下さり、その道を私達のご先祖の方々も歩んでこられたのです。
『おかげさま』『ありがとう』を合い言葉に、皆様と共々にお念仏申させていただきながら、親鸞聖人がお示しくださったお浄土(彼岸)への道のりを、阿弥陀様の光に照らされながら、強く明るく生き抜いてまいりましょう。
親思う 心にまさる 親心 今日のおとずれ 何と聞くらん
2016年7月
大河ドラマ『花燃ゆ』でも一躍話題となりました。死刑に処されることを悟った吉田松陰(寅次郎)が家族に向けて遺した句です。「子が親を思う気持ち以上に、親が子を思う慈愛の気持ちはさらに大きく暖かなものだった。今日のこの報せを聞いた親は、なんと思うだろうか。」といった意の句でしょう。
勤勉な父・杉百合之助と、前向きで明るい母・滝のことを想ったとき、子が先に逝くことの申し訳なさを感じていたのかもしれません。しかし松陰は、改めて親の心の大きさ、暖かさに深い感謝の念を露わにされました。
人は親になってはじめて「親の気持ち」が分かるというものです。子どもながらにその親心に気づくことによって、人生が大きく変わることがあります。人生に迷い、苦しみ、そして悩んでいる時でも、そのありのままの自分を認めてくれて、暖かく包み込んでくれる、その存在こそが親の心、親心であります。
仏教では、仏さまはしばしば親に喩えて「親さま」と呼ばれます。それは仏さまが、どんな生き方であろうと、どんな老い方であろうとも、私たちを包み込み、見守ってくれる親のような存在であるからです。私たちがどんなに逃げても、背いても、暖かく見守ってくれるのです。
それに気づいた時に、どんなに辛い人生であったとしても、辛さのままに安心できる世界があります。「辛いものは辛いのまま」だけれども、「私を見捨てない、見守ってくれる存在がいる」ということに気づいたならば、その人生に「心の支え」となるでしょう。
やさしさに であったら
2016年6月
やさしさに であったら よろこびを 分けてあげよう
しあわせと おもったら ほほえみを かわしていこう
海をふく 風のように さわやかな おもいそえて
(作詞:久井ひろ子)
この歌詞のように、よろこびを分け合い、微笑を交わせてゆけたら、本当にしあわせなことではないでしょうか。やさしさや笑顔を、自分の方からの発信を心がけていたとしても、知らぬ間に、やさしさを戴くことのほうが多くなっています。自分の心に備わっている、やさしい笑顔の記憶の中には、今は亡き大切な方も多くおられるのではないでしょうか。有難いことに私達は、今でも忘れることのない有縁の方々の笑顔を思い出すことで、よろこびと安心をいただき、その笑顔に支えられながら人生を歩ませて戴けるのです。
《月々の法話「私の人生」より》
光いっぱいの世界
2016年5月
『光いっぱいの世界』(東井義雄)
病院の窓から見える 光いっぱいの世界
円山大橋を渡っていく たくましいトラック
力に充ちた そのエネルギー
堤防を中学校へ急ぐ 女生徒も
爽やかに光っている
その自転車まで光っている
堤防を歩いて急ぐ 男生徒も光っている
その後から 朝の散歩を楽しんでいる
おじさんも 光っている
私は七十五年
この光を見ずに生きていたのではないか
山の中にいると山が見えないように
光の世界の中では
この光が見えないということであろうか
わたしも やがて
この 光いっぱいの世界に帰らせていただく
光を見失わないように
生きさせていただこう
光を仰ぎながら 生きさせていただこう
病院の中で
気付かせていただいた
光を大切に
生きさせていただこう
この詩は、病気で療養中の東井義雄さんが、病院の窓から見える景色を眺め、よまれたものです。
生老病死の苦悩を解決する方法をこれっぽっちも持ち合わせてはいない現実を目の前にして、阿弥陀様の光に背いて生きてきた自分の愚かさに気付かされ、今まで見えることのなかった「全てのものが阿弥陀様の光に照らされている」という事実に目覚められたのです。その光のはたらきは「他の人の痛みや悲しみに寄り添う阿弥陀様のお心に学ばせていただこう、そのはたらきを仰ぐ生活をさせていただこう」さらに「苦悩を抱えたままだけど、自分のできることはできるだけさせていただこう、偏りすぎない欲張りすぎない生き方をさせていただこう」と、思わせて下さるのではないでしょうか。
うんともすんともいわず
2016年4月
『うんともすんともいわず』(東井義雄)
ゆうべの間にひげがのびている
しらん間に
うんともすんともいわずに
ひげが のびている
いのちの方は
うんともすんともいわずに
ちぢまっているというのに
ひげが のびている
いや うんともすんともいわずに
刻々ちぢんでいくいのちを
わたしにしらせるために
そっとひげが信号を
送ってくれているのかもしれない
うんともすんともいわずに
ちぢまっているいのちを
わたしにしらせるために
ひげがのびているということは
わたしが生きているということ
生きているということは
死ぬいのちを
かかえているということ
ひげをなでる
うれしいような
さびしいような
愛しくてならぬ
この なまあたたかい
生きているということの
肌ざわり
心あたたまる詩に出会いました。何も言わないけれど、いのちのあり方を警告してくれるヒゲを、愛おしく有り難く受け取られています。何気ない日常から私たちに「いのち」を考えさせてくれる詩です。
詩の作者は、明治25年に兵庫県のお寺に生まれ、生涯をかけて教育に尽力した東井義雄(とういよしお)さんです。今月は東井さんの生涯についてご紹介させていただきます。
東井さんの生い立ちは決して恵まれたものではありませんでした。小学1年生のとき母を亡くし、家も貧しかったので「一番安く学べる」という理由だけで師範学校に入学しました。師範学校時代、野球部・サッカー部など様々な部活動に入ってみたものの、どれも長続きはしなかったのです。根性と、持久力だけなら誰にも負けないつもりで、最後はマラソン部に入部しますが、それもいつもビリでした。しかし、東井さんは、心の中では悔しい思いをしたけれども、気づきがあったと言います。「ビリも役に立っている」「役に立たない者は一つもない」という気づきです。この想いから「生涯、努力しても結果がでない子ども達の立場に立つ教育者になろう」と誓われたそうです。
教育者になってからは、最愛の父との死別やわが子の大病など、逆境にもみまわれましたが、中学校長・小学校長を歴任し、教師としての実践を積み重ねていかれました。59歳で退職した後は、年300回を超える講演をなされたのです。貧しい村などで、子どもたちに教育を実践する一方で、「いのち」に関する教育のあり方を全国に伝えた人物でもありました。
「仏の声をきく」より
お彼岸とは、太陽の沈んでゆく方角、いのち終へ生まれ往く世界
2016年3月
一言でお浄土と言いましても、実は沢山あって、仏様はそれぞれに、ご自身のお浄土をお持ちです。その中で、お彼岸と呼ばれる極楽浄土のご主人様が阿弥陀様であり、その極楽浄土は西の彼方にあるということがお経に説かれてあります。お経は、悟りをひらかれ仏様となられたお釈迦様のお説教を文章として残されたもので、仏教では「仏語に虚妄(きょもう)なし」とし、仏様のお言葉には嘘はなく、仏教徒としての第一歩は、まず仏様の教えを信頼することだと言われています。ですから、極楽浄土が西の彼方にあるということを科学的知識のない昔の人の見方だと考えてしまうのでは、お釈迦様の言葉を信頼していないことになります。そうではなく、お浄土が西の彼方にあると説くことによって、お釈迦様は私達に何を明らかにされようとしたのかを考えることが重要です。
東西南北というのは、地球上での方角であり、飛行機で西の方角へ飛び続けても、元の場所へ戻ってくるだけで、お浄土に到着することはできません。また、地球上ではなく、西の空の彼方だと考えたとしても、日本から見ての西の空と、ブラジルから見ての西の空とは真反対です。しかも、地球は自転しているのですから、西という方角は刻々と変わり、十二時間で真反対の方角になります。こんなことをいくら考えても答えは出てきません。
東西は地球上での見方だとか、地球は丸いとか、地球はちょうど一日で一回転するとか、頭で知っている知識に基づくのではなく、私達がどのように想い感じているのかが大切なのです。太陽は朝になると東の空に昇り、夕方になると西の空に沈んでゆきます。これが私達の感じ方なのです。実は、地球が回ることによって太陽がだんだん見えるようになる時を朝といい、逆にだんだん見えなくなってゆく時を夕方と呼んでいるだけなのです。太陽が動いているのではなく、地球が動いているのです。私達の想いを地球の自転にあてはめますと、太陽は東から生まれてきて成長し、だんだん力強くなり、そして老化して弱ってゆき西の空に沈むという死を迎えます。ですから私達がこの世の命終へてゆく西の方角に、ふたたび生まれ往く阿弥陀様の世界があるというのが西方極楽浄土の教えだと言えましょう。
お彼岸のお参りを、西方極楽浄土の阿弥陀様に感謝をささげ、今日の自分をお育て下さったご先祖の方々に思いをはせる機縁としたいものです。
《本願寺新報・内藤和上の紙上ご示談より》
心なごむ なつかしい 歌声喫茶
2016年2月
【 歌声喫茶アミーダ 】
開催日 毎月 第3火曜日
時 間 午後2時〜3時半
場 所 福住寺喫茶室(庫裏会議室)
会 費 500円 (茶菓子付)
「楽しい時間をお寺で過ごしましょう」と始められ、福住寺で毎月、行われております心なごむ懐かしい「歌声喫茶アミーダ」は、平成22年4月より始めて7年目になりました。
カラオケの無かった時代に流行していた歌声喫茶を、お寺を会場として、1950年代〜70年代の歌を中心に昔懐かしい歌とお茶やお菓子でホッとひと息。
毎回、ジャズピアニストでご活躍されております、石黒眞知子先生のピアノ伴奏に合わせて楽しんでおります。大きな声を出してみんなで一緒に歌いますので、ストレス解消にもなり、とても健康的です。
「歌声喫茶アミーダ」の会員を中心としたコーラス隊は、昨年4月に京都西本願寺にて御堂(みどう)コンサートにて歌声を披露してまいりました。
今年度は、来る7月2日(土)サタデーナイトコンサートを福住寺で開催する前段で、歌の披露を予定しております。
味のある方ご一緒にいかがでしょうか。お寺に縁のない方にとっては、お寺さんとの交流の場にもなっております。歌詞カードはお寺で用意いたします。
どなたでもお気軽にご参加ください。
2016年1月
謹んで新春のお慶びと“お念仏”を申し上げます
今も昔もお正月を迎えるというのはおめでたいことです。しかし「めでたいめでたい」と浮かれるだけで、本当に大切なものを見失ってしまいがちなのが私たち人間の性なのではないでしょうか。
蓮如上人のお言葉を集めた『蓮如上人御一代記聞書』の最初には、「勧修寺村の道徳、明応二年正月一日に御前へまいりたるに、蓮如上人、おおさせられそうろう。道徳はいくつになるぞ。道徳、念仏もうさるべし。〜」というお言葉がのこされています。
これは弟子の道徳さんが、元日に蓮如上人へご挨拶に訪れたときの出来事です。道徳が新年のご挨拶をすると、蓮如上人はいきなり、「何歳になったのだ、お念仏を申しなさい」と、お正月早々厳しく戒められたのです。
昔は数え歳ですので、正月になると、ひとつ歳を重ねることになります。正月というのは少し浮かれ気味になってしまうのは人間の常であるともいえます。しかし、蓮如上人はそこで「おめでとう」と言わず、「念仏申さるべし」と言われました。これは新年を迎え、歳をひとつ重ねる、このときこそ本当に大事なものを確認しなければいけませんよということをさとされたのです。
また、蓮如上人と親交があり“一休さん”として知られる一休宗純も、同じような詠をのこされました。
「正月は、冥土の旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし」という詠です。
世間では正月に「めでたい」というけれども、また歳を一つとって、死に近づくじゃないか。この無常の世の中をしっかり心得るということが大事なことでないか。そのことを肝に銘じて、本当に大事なものを確認していかないと、あっという間に私の人生は終わってしまいますよということなのです。
新年を迎えたとき私たちは「おめでとうございます」と祝辞を述べますが、蓮如上人も一休宗純も、そんな時だからこそ「歳を重ねることはどういうことか」ということを改めて問われるのです。私たちに、いよいよ「いのち」について思慮すべしとさとされるのです。
残念ながら、私たちの「いのち」はいつ終わるかもしれない無常です。しかし、無常だから悲しいというだけでなく、無常がゆえに今日一日一日が尊い、今というこの時が尊いということをしっかり学んでいかなければならないと思います。私たちに対して、本当の幸せ、本当の満足を得るとはどういうことなのかを考えさせる。それがこのお二方のお言葉だと思います。
本年もどうぞご一緒に仏さまのみ教えを聞かせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|