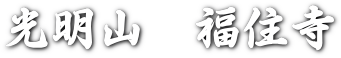月報「なむ」
2015年
「門徒の大晦日」「門徒の初詣」
2015年12月
12月になると世の中はクリスマスムード1色となり、それが終わると一気に正月の飾り物に追われます。しかし、その前に大切なのは掃除です。年末は、家の大掃除だけでなく、是非お仏壇の大掃除もおこなっていただきたいと思います。掃除をすることは1年を振り返り、感謝の気持ちを持つということです。そして大晦日には、1年間の報恩感謝をこめて、家族そろって、ご家庭のご仏壇にお参りし、お念仏を称えつつ、1年を振り返えらせていただきましょう。
大晦日からお正月の行事といえば、圧倒的に神社にお参りされる方が多いようですが、やはり、お念仏を喜ばせていただく私達がお参りする場所は、お寺ではないでしょうか。当寺でも、大晦日の夜11時半から「除夜会」、元旦の朝10時には「元旦会」のお勤めをしたあと、抽選会などを楽しんでいただき、年末年始のお参りをおこなっております。浄土真宗のご門徒の方は、1年の終わりと始まりを、阿弥陀様の前にてお参りさせていただくことが本来あるべき姿です。私たちは、そんな自分の姿をみることもなく、たった一度の限られた時間の中を生きています。しかし、ただ欲望を満たすためだけに生きているのでしょうか。そうではありません。阿弥陀様の前に座らせていただくことで、自らの汚れた心の姿が照らし出されます。このことが大切なのです。阿弥陀様は、私の生き方を攻めるのではなく、悪い事とは知りながらもそのようにしか生きられない私の姿を悲しまれ、そういう者を最も救いの目当てとして下さり、私たちのためにはたらきどおしで、いつも願われているのです。
嬉しいことも苦しいことも思い通りにはなれないのが人生です。その人生を一緒に歩んでくださるのが、阿弥陀様であり、その前で じっくりとわが身を振り返り、人生にとって何が大切か見つめなおし、確かなよりどころとなるお念仏を味わわせていただきましょう。それでこそ「門徒の大晦日」であり「門徒の初詣」ではないでしょうか。
今年の大晦日、来年の元旦は、是非とも家族そろってお寺にお参りさせていただき、共々にお念仏申させていただきましょう。
生老病死 みんな いのちだよ
2015年11月
7月に行われました福住寺仏教講演会では、滋賀医科大学名誉教授である早島理先生より「今日を生き、明日をはぐくむ 〜先端医療と生老病死〜」というテーマで講演をいただきました。
生老病死の現実から逃れる方法、解決する手段を持ちえない人間の死亡率は100パーセント。誰も逃れることはできません。そのような苦悩の中にあって、いのちのある限り、精一杯に生き抜いて「ああ、私の人生、良い人生でありました」と、安心して心おきなく人生の幕を下ろしていくには何が必要なのでしょうか。
先端医療の発達によって、難しい病気も治るようになった、長生きもできるようになった。「こんな時代に生まれてきてよかったな」と思って、ハッと気が付いたら、途方もない問題を我々は背負っているというのです。
それは「死にたくない」という願いをかなえてくれて「よかったな」と思っていたら、点滴を外すとか、延命治療をやめるとか、移植医療や遺伝子検査の問題など、大きな判断、厳しい選択をしないといけない。そんな時「誰がそれを決めるのか」という、もっと大きな苦悩を先端医療と一緒に背負い込んでしまったのです。
医療では、生きる方に価値があるとみるから、それをできるだけ伸ばそうとします。反対に、死の現実は「嫌だなあ、話をするのもやめよう、目をそむけよう」などと考えます。
しかし、お釈迦様は「生老病死、みんないのちだよ、成長するのも老いていくのも、時に病気になって死んで往くのも、みんないのちだよ。みんな意味があって大切なのですよ」と示されるのです。
腰が曲って体が痛くなって辛いこともあるけれど、その自らの体験は、人の喜び悲しみ辛さを分かち合えるようになった。「年をとらしてもらったな、生きていてよかったな」と、仏さまの光が届いているから、ますます念仏申す身となるのです。
念仏申す身になるということは、愚痴も言いたくなる。体も動かなくなる。でもその事実を受け止め、自分だけじゃない、みんな痛みや辛さを抱えていることに気付かせるのです。仏さまに抱かれて「今日生かされていることがそのまま意味があって、明日の私につながる」と聞かせていただきました。
いつも仏さまが見てくれている
2015年10月
昨今は嫌な事件が頻発しております。お盆過ぎに起きた大阪高槻の駐車場での殺人事件では、手がかりが見つからずに連日世間をにぎわせました。そんな中、ついに防犯カメラがきっかけで犯人逮捕に繋がりました。この事件に限らず、現代は防犯カメラによる事件解決が多くあるといいます。
思い返してみますと、昔は「誰が見ていなくても仏様が見ている」という考えがあったように思います。親から子に「悪いことは、するなよ!誰かが見て無くても、仏様は見ているからね」と言って育てられた方も多いのではないでしょうか。誰が見ていなくても良い行いをしなさい!という簡単な教えです。
しかし、これがなかなか難しい。誰も見ていなければ、大丈夫だろうと悪いことをしてしまうのが人間の本性かもしれません。仕舞には、証拠がないから無実だと主張し始める始末です。実に情けないことです。
親というのは、形ある財産だけでなく、しあわせになって欲しいという「願い」も私たちに残すのです。阿弥陀様は「心の親様」と言われます。阿弥陀様の願いも、形に表れないかもしれないが、私たち子に向けられた真実の確かな願いでありましょう。
仏教を聞くということは、誰も見ていなければ、ずるいことをしてしまうかもしれないこの私が、「仏様は知っておられる」「仏様に願われていた」と気づかされることの連続です。
現代は、様々なものが便利になって、目に見えるものだけが確かなものとしか考えられなくなったのではないでしょうか。そんな今だからこそ、目に見えなくても確かなものがあることに気づかせていただきたいものです。
報恩講とかぼちゃ様
2015年9月
『報恩講とかぼちゃ様』(東井義雄)
六日夜 かぼちゃの切り目が三片出た おいしかった
自然の恵みにみちた南瓜
仏さまの願いのあふれた薬であったのだ
光って見えた「かぼちゃさま」と拝んでいただいた。
全国二万ケ寺をこえる真宗寺院最大の行事が、報恩講です。報恩講は私たちにみ教えを伝えてくださった親鸞聖人のご苦労を偲(しの)び、そのご恩に感謝させていただく大切な法要です。
昔「報恩講さんは半年がかり」という話がありました。そのころは、ほとんどの家が野菜を自給自足していました。菜っ葉類の他、根菜などもつくっており、とりわけゴボウなどは、かなり高く土を盛って周囲を板で囲った畝(うね)をこしらえねばなりません。ある家で、それまでよりゴボウの畝が増えました。すると近所の人は「ああ、この家は今年おめでたか」とさとったといいます。おめでたがあると家族が増え、家族が増えると報恩講に参る人が増え、お斉(とき)に欠かせぬゴボウをまず多く植えておかねばいけないからです。このように報恩講は土の上に絵を描くような営みでもあったわけです。半年がかりで報恩講の支度をする人々の姿は、残念ながら今の私たちには実感がわかなくなってきました。大気汚染、森林資源の乱伐など、いま地球の荒廃が人類的問題となっています。しかし、これもまた日々の生活のなかでは実感できません。私たちの生活の中に、いつの間にか自然との関わりや一体感が失われてしまったからなのかもしれません。私の「いのち」は一粒のお米、一個の南瓜、一本の胡瓜(きゅうり)、その他のたくさんの「いのち」によって支えられているのだということの有り難さを、ともに確かめ合い、伝えていかなければならないのではないでしょうか。
報恩講をむかえるにあたり、さまざまな動物や植物の「いのち」をいただき、生かされていることへの感謝の心を、あらためて確かめるための「感謝の集い」として、皆さんと共々にお参りさせていただきましょう。
死して往く場所と目的
2015年8月
生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば
弥陀弘誓のふねのみぞ のせてかならずわたしける(親鸞聖人)
親鸞聖人は、高僧和讃に阿弥陀様のはたらきを船にたとえて讃えられております。
「果ての無い苦しみの深い迷いの海に沈んでいて、仏に成るため役立つものを何一つ持たない、自分の力では浮かび上がることのできない私。石ころのような私を、暗闇の海の底からすくい上げ、大きな船に乗せて下さり、必ず浄土へと渡し仏に成らせて下さるのです」と示されました。
私達は、何気ない生活の中で、場所と目的によって行動をしています。朝起きてトイレで用を足す。洗面所で顔を洗う。勤務先へ仕事に行く。学校で勉強する。お寺で仏法を聞く。寝室で寝る。など、場所と目的によって行動しているものであるといえます。
行き場所の決まっていない旅行を「ミステリーツアー」などと称して、ドキドキワクワク感を演出する旅行もあるようですが、場所が知らされていない不安もあります。また、用事を思い、隣の部屋に来てから「あら、私、いま何をしにこの部屋に来たのかしら?」と目的を忘れてしまうことがあるでしょう。そんな時「私だいじょうぶかな」などと戻って考え、心配になるのです。
仏法に出遇わなければ、この世のいのちを終えるまさにその時「どうしよう、どうなるのだろう」と、往き先不明、目的不明の大きな不安の中で終わっていかねばなりません。
今、一番、年齢の若いうちに仏法聴聞を重ね、浄土へ生まれ仏に成らせていただく、場所と目的が与えられるお念仏を称える。いのちの終え方はどのようであれ差し支えなし。「間に合ってよかった」と思わせる浄土への道を歩ませていただきましょう。
それでもいい
2015年7月
近頃の携帯電話は、みるみる進化しています。最新の携帯である、スマートフォン(いわゆるスマホ)は、もはや小型コンピューターである。スマホは、自分好みの機能をどんどん追加できる携帯であるが、その機能の1つに、「ネガポ辞典」というものがある。これは、ネガティブ(短所・消極的)な言葉を、ポジティブ(長所・積極的)な言葉に変換してくれる風変わりな辞典である。
この辞典で、いろんな言葉を調べてると、
「人見知り」 →「慎重に相手を見極められる」
「言い訳する」→「状況判断が早い」
「要領が悪い」→「丁寧でひたむき」
物は言いよう、確かに的を射た変換がされていた。
同じ状況に対し異なる見解が出るのは、見る側の感情が大きく関係してくるのは明らかだ。好ましくないと感じたものにプラスの感情を抱くのは難しく、反対もまた同じことが言えるのだが、誰もが同じものを見て同じ感情を抱くようなことはほとんどない。親鸞聖人がご和讃に、「煩悩にまなこさえられて(煩悩に目が遮られて)」と歌われたように、私たちは煩悩の色眼鏡を通して物事を見ている。それは自分の価値観に左右され、物事のありのままの有り様を見ることができない状態のことをいう。この状態は何も特別なときに起こるものではなく、それが私たちの悲しき常であるのだ。
自分に当てはまるネガティブな言葉を探し、「英語が苦手」という言葉を引いてみると、「それでもいい」と変換され、「大切なものは他にもたくさんある」という注釈に、思わず肩の力が抜け落ちた。
結局、ネガティブな言葉をポジティブに変換させる唯一の言葉があるのなら、それは「それでもいい」なんじゃないかなと思ったりした。
私たちは、つい自分のモノサシで物事を見てしまうが、短所と決めつけ溜め息をつくより、ありのままは見えなくても「それでもいい」と仏様が受け取ってくださる。ただただお任せするしかないのです。まさに浄土真宗のみ教えとはそういうことなのではないでしょうか。
http://merry-shaka.com/より
宗祖親鸞聖人降誕会
2015年6月
今から842年前、承安(じょうあん)3年(1173年)新暦の5月21日に宗祖親鸞聖人がご誕生になりました。このご誕生をお祝いする行事が降誕会であります。親鸞聖人は9歳で出家得度され、比叡山での20年間を堂僧として修行を経、下山後、法然聖人の専修念仏の教えと出遇い、その後の法難により越後へ流罪、関東でのご教化を経て、60歳の頃に京都へ帰り数多くの著述を残され、人々にお念仏のみ教えを伝えていかれました。今日の私達は、その親鸞聖人のおかげにより浄土真宗のみ教えをいただくことができるのです。親鸞聖人ご誕生のご縁がなかったら、お念仏をいただき、阿弥陀様に手を合わせることもなかったかも知れません。親鸞聖人ご自身も、吉水(よしみず)の草庵で法然聖人と出遇われたご縁を「本師源(げん)空(くう)いまさずは、このたびむなしくすぎなまし」《師匠である源空(法然)聖人がこの世においでにならなかったならば、私の人生は空しく過ぎてしまったでしょう》と、ご和讃の中でよろこばれました。そして「本願力にあひ(い)ぬれば、むなしくすぐるひとぞなき」《阿弥陀様のはたらきに出遇へたなら、空しい迷いの人生を送ることはありません》と、お念仏に出遇へたよろこびをうたわれました。親鸞聖人の時代から長い年月を経、多くのいのちの?がりの中で受け継がれてきたお念仏のみ教えに出遇へたなら、人生においてどんな困難や試練に遭遇したとしても、生きがいあるよろこび多き人生を歩みながら、やがては浄土に往生させていただけるのです。
お念仏と出遇うご縁を下さった親鸞聖人の降誕会にお参りし、「お陰様で感謝の毎日を送らせていただいています」と、心からよろこべる人生をお念仏と共に歩ませていただきましょう。
死んだら仏?
2015年5月
永代経法要のご法話にて、講師の先生から「人が亡くなったら自動的に仏さまに成れるのですか」という問いかけがありました。
テレビの刑事ドラマなどで、刑事さんが亡くなった人をさして「ホトケさん」と言うことがあります。「死んだらみんなホトケさま」と思われている方は多いのではないでしょうか。
ある葬儀の中で出棺の際、故人との別れの場面で棺の中にお花を納め入れます。そこで取り仕切っていた葬儀社の方が「どうぞ皆様お並び下さい。こちらから仏さま(故人)にお花をお飾り下さい」と言われました。それを聞いていた先生は、お寺参りやお念仏を大切にされていたとは言えない故人に対して「仏さま」と呼ぶことに違和感を覚えたそうです。
寺もいらなければ、僧侶もいらない、仏教そのものの教えもいらない。ということになるでしょう」とお話されました。
親鸞聖人は『本願を信じ念仏を申さば仏に成る』と示され「阿弥陀様の願いを疑いなく聞き受け入れ「なもあみだぶつ」とお念仏を称えることによって、仏さまに成らせていただく人生が開けてくるのですよ」と教えて下さいます。
阿弥陀様の願いは「あなたを必ず仏さまに成らせる。成仏の決定した人生を与えるから、私にまかせてほしい」と願われました。その願いは完成され私に届けられています。
いつ終えるかわからない不安定な私のいのちだからこそ、私が死ぬという問題の解決を今、済ませなくてはなりません。仏さまに成らせていただくことを定めるはたらきにおまかせし、お念仏を称え「今がしあわせ」と言えるような輝きある人生を歩ませていただきましょう。
4月8日はお釈迦様の誕生日です
2015年4月
お釈迦様は今から約2500年もの昔、インドのカピラ国の王子様として無憂樹の花が咲きほこるルンビニーの花園でお生まれになりました。お釈迦様は、お生まれになられると東西南北の四方に七歩足を運び、右手で天を指し、左手で地を指して「天上(てんじょう)天下(てんげ)唯我独尊(ゆいがどくそん)」と叫ばれたと伝えられています。
天上天下唯我独尊は「この世界中で私か最も尊い者である」と直訳できます。
しかし、大変傲慢な言葉に聞こえますので、少し意味を汲んで翻訳しますと、「この世界中で、またいつの時代でも、あらゆる者から最も尊いと尊敬される生き方、それが知りたい者は、私を知りなさい」といわれたのです。
しかし、この句には続きの句があり、世界中が尊敬すべき生き方こそが、下の句の内容なのです。
伝記は数種伝わっていますが、その中の一つ『修行本起経』に記された下句は「三界皆苦吾当安之(さんがいかいくごとうあんし)」というものがあります。「三界は皆苦なり吾まさに之を安んずべし」と直訳できますが、尊敬すべき生き方ということを汲んで翻訳すると「この世界は、苦しみと悩み、不安と不幸に満ちている。私はその人々の不幸を担い、苦に代わって、わけへだてなく自身の幸せを恵み、安心を与えていく。これこそが世界中で最も尊い生き方である」といえます。
ですから「天上天下…」のこの言葉は、単にお釈迦さまの伝記というのみでなく、仏さまということが全くわからない私たちのために、仏さまとはどのようなお方かを明確に伝えてくださった言葉なのです。そして、ここに示された生き方を尊いと受け入れる人を仏教徒と呼びます。
人々の悲しみ、苦を担い、自らの幸せを他に与えて、人々が幸せであることを自らの幸せと感ぜられる仏さまを尊いと仰ぐことは、それが自分自身の人生の目標になるということです。
これが私の目指すべきゴールになるのです。お釈迦様が説かれた仏の教えは、私たちの悩み苦しむ人生に光を放つ生きる力となって下さっています。
私達が人生でしてはならないことは 人生を途中で投げ出すことです
2015年3月
紙には表と裏があるように、私たち人間も出来る事と出来ない事とが表裏一体となった人生を過ごしています。
この世で完璧な人生を過ごした人などそうは居ません。たとえ人生の現実が不満足、不本意なものに思えても「今」「ここ」に与えられた人生を大切にし、出来ないことはお互いに助け合い、出来る事を精一杯にして生きていくしかないのです。日常、私たちが持つ不足感は、何か満ち足りないという日々の繰り返しから出てくるのではないでしょうか。
大切なことは自分を見つめ直し、自分を卑下せず捨てないと言うことなのです。
仏教においての人生とは、何かを成し遂げてはじめて意味を持つものではありません。なすべきは課題の解決ではなく、その課題から目を背けずに問い続け、担い続けることです。
時として人間は我ままな生き物ですが、人生はなかなか思い通りにはいきません。確かなことは、一人では何も出来ない人の痛みに気付くことすら出来ないこの私が、あらゆるいのちとつながりあい、支えられて「今」「ここ」に生かされていると言うことなのです。
死なない方法を聞かせていただく
2015年2月
昨年の8月に亡くなった叔母は、入院中に「お助けください、助けてください」と言いました。「何を助けてもらいたいの」と聞くと「いのちを助けてもらいたい」と答えるのです。いのちの叫びをその場で聞いていた私は、何にも応えてあげることはできませんでした。
その後、叔母が亡くなり葬儀が行われました。葬儀のお勤めが終わり火葬場へ出棺する前、棺のふたを開けて遺体と対面し、お花などを棺の中に納めます。
その時、私の隣にいた農業をしている父が、姉の遺体を目の当たりにし、悲しみが大きくなって疑問がふと湧いてきたのでしょう。思いついたことをすぐ口にし、言葉遣いがあまりよくないのですが、突然大きな声で「死なねえ方法ねえのか」と問いかけてきたのです。
私は「えー」と思ったのですが、少し考えましたら「ああ、そうだよなあ。死なない方法を聞かせていただいているんだよなあ」と思いましたので「仏法を聞くこと、仏さまの教えを聞くことです」と応えました。
「いのちを助けてほしい」という叔母に対して、寄り添い続けることはできない。助けることはできない。見捨てているのと同じ、何にもできない自分に気付かされた。そして、叔母の死を通じて「死なねえ方法ねえのか」という父の質問に、仏様としてお浄土へ生まれさせていただく、何の力もない弱い私の助かる方法がすでに与えられている慶びを感じさせるものでありました。
叔母を亡くして悲しいけれど、悲しみのままでは終わらせない。阿弥陀様のはたらきは、弱い私に安心や慶びを与えて下さるのです。
「なもあみだぶつ」と称える私の口から現れて下さっている阿弥陀様のお前を必ず救うという心、死なない方法「如来より賜りたる往生成仏の道」を聞かせていただきましょう。
(岩淵)
2015年1月
大切な心
あわただしく一年が過ぎ去り、新たな年をむかえます。去る年も来る年も、様々の出来事に休む暇もなく日々は過ぎていきます。だからこそ仏様の前に座り、あらためて自分を見つめ直し、心新しく歩みはじめる新年でありたいものです。
「昨今の殺伐とした世の中は、日本の心が忘れられたからで、今こそ本来の日本の心をお年寄りから習うべきである」とういう発言を耳にすることがあります。日本が現在のような文明国になったのは人生の先輩方のご苦労のおかげです。けれど、一歩下がってみてみると、真実の道を求められたご先祖様方が、身をもって伝えられた大切なお心をおろそかにして、物質的文明だけが先走った感じがしないでもありません。そのために、お金と物には恵まれながらも、心の内側には不安と空しさの雲がかかって先が見通せていないのではないでしょうか。大事な心は、よろこびをもって生活する心、もったいないといただく心、仏恩報謝のお念仏をする心です。この心は、人生の中でどのようなことに出遇っても、生かされて生きる命に深い味をかみしめながらご縁を喜ばせていただき、強く生き抜く人間生活を過ごすためには大切なことです。新年を節目に、あらためて日々お念仏の伝統に耳を傾けながら、自己中心的な分別に固執することなく、開かれた人間として実りある人生を共々に歩ませていただきましょう。
《真宗法要法話より》
| << 次号 | 前号 >> |
|---|