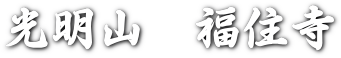月報「なむ」
2013年
また会いましょう また遇いましょう 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
2013年12月
2013年、今年も残すところもわずかとなりました。振り返りますと今年も多くの仏縁をここ福住寺でいただき、ご門徒様を始め多くの方にお会いさせていただきました。本堂に響き渡る皆さまのお念仏の声を大変ありがたく聞かさせていただきました。どうぞ来年もお念仏のみ教えに出遇わさせていただきながら、感謝の毎日を共々に過ごさせていただきましょう。
◆除夜会
12月31日(火) 午後11時30分より除夜の鐘(梵鐘)を撞いていただきます
◆真夜中の成人式
1月1日(水) 除夜の鐘に引き続き午前零時よりご家族に成人式を迎えられる方がおられましたら記念品を差し上げますのでお寺までご連絡ください!
◆元旦会 1月1日(水) 午前10時より
元旦会は新年を祝うと同時に今年もお念仏と共に日々を送らせていただく誓いを新たにするお正月のすがすがしい行事です。「一年の計は元旦にあり」といいますが、浄土真宗の門徒にとって元旦は、真実に生かされる身の幸せを喜び、この一年をお念仏のみ教えをよりどころに送る決意を新たにする日です。元旦の朝には家族揃って家の仏壇に灯りを 点じ、仏さまに年頭のお参りをして新年を迎えたいものです。
そっとつながる ホッがつたわる
2013年11月
携帯電話は、ほとんどの人が持ち歩き、いつでもどこでも連絡の取れる通信手段としてはとても便利なものです。ボタンを押すことによって会話が成り立つようなネット社会は、いつでもつながっていないと不安になる依存症を引き起こす原因になるそうです。相手の顔の表情が見えない人間関係は、もしかすると、信頼し合うことが難しいのかもしれません。
日頃、感謝の気持ちを忘れがちな忙しい生活を送っている私に、お参りするご縁は、改めて、いのちの尊さ大切さ、そして感謝の心を育んでくださいます。感謝の心をいただく積み重ねは、うまくいかない人と人との「つながり」信頼関係を、良い方向へと向かわせるはたらきがあるのではないでしょうか。
あらゆるつながりの中に生かされている私たちです。親鸞聖人は、「誰にでも、仏さまが一緒ですよ」と教えて下さいました。そのはたらきは、私自身を見つめ直し、感謝の心を育て、どのような時にでも余裕をもって楽しみ、苦しみ、大きな悲しみの中であっても、苦悩を長引かせない、輝きあるよろこびの人生を与えるのです。
そのような生き方をする人は、他の人の悲しみ苦しみに「そっと」やさしく寄り添い、どこか「ホッ」と安心感を与えます。それは「あの人のような生き方をしたいな」と周りの人を励まし、何か暖かいものを感じさせるほどに、広く深くつながっていくことでしょう。
感謝の心を大切に、『学仏大悲心(がくぶつだいひしん)』仏さまの心を学ばせて頂きましょう。
真宗法要法話大辞典より
恩知らず
2013年10月
「恩知らずは、ひとでなし」と言われたりすることがありますが、恩を知り、恩に報いる心情は、人として生まれてきた私達にとって最高のよろこびではないでしょうか。最近の世相を見ますと、御恩をよろこぶ心を有難いといただくことが少なくなり、御恩に報いる気持ちを忘れ各々の不平不満ばかりが先に立ってきたように思われます。
仏教で、「知恩」「報恩」に相当するインドの言葉を「カタンニュ」といい、「我のためにして下さったことを知る」という意味があります。これは、誰かが『私』のためにして下さった「行い」を感動をもって受け止め感謝するということで、その「行い」は三つに分類されます。
一つは「身業(しんごう)(身体でして下さったこと)」
二つは「口業(くごう)(言葉で教えて下さったこと)」
三つは「意業(いごう)(思慮分別の心を起こして下さったこと)」です。これを「三業(さんごう)」と言います。
この「三業」を味わい感謝してこそ人として生まれてきた本当のよろこびに出遇えるのではないでしょうか。
このよろこびに出遇えた感動を、孫達がお爺ちゃんの葬儀で読んだ弔辞があります。
「お爺ちゃんが死んでとても悲しい。みんなのために立派に仕事をして下さり、人間にとって大切な事をたくさん教えて下さいました。心の中で、僕たちがしあわせで立派に育つことを思い続けて下さったことでしょう。僕たちも頑張って、お爺ちゃんのような人になります。これからもお浄土から僕たちを守り、お育てください。お爺ちゃん有り難う」「なもあみだぶつ」「なもあみだぶつ」
有り難うの究極のかたちが「なもあみだぶつ」であり、いつでも、どこでも、私と離れず守り育てて下さる阿弥陀様の呼び声なのです。
真宗法要法話大辞典より
親鸞聖人のご生涯
2013年9月
平安時代も終わりに近い承安3年(1173)の春、親鸞聖人は京都の日野の里で誕生された。父は藤原氏の流れをくむ日野有範(ひのありのり)、母は吉光女と伝える。聖人は養和元年(1181)9歳の春、伯父の日野範綱(のりつな)に伴われて、慈円和尚(じえんかしょう)のもとで出家・得度をされ、範宴(はんねん)と名のられた。ついで比叡山にのぼられ、主に横川の首楞厳院(しゅりょうごんいん)で不断念仏を修する堂僧として、20年の間、ひたすら「生死いづべき道」を求めて厳しい学問と修行に励まれた。
しかし建仁元年(1201)聖人29歳のとき、叡山では悟りに至る道を見出すことができなかったことから、ついに山を下り、京都の六角堂に100日間の参籠をされた。尊敬する聖徳太子に今後の歩むべき道を仰ぐためであった。95日目の暁、聖人は太子の本地である救世観音(くせかんのん)から夢告を得られ、東山の吉水で本願念仏の教えを説かれていた法然聖人の草庵を訪ねられた。やはり100日の間、聖人のもとへ通いつづけ、ついに「法然聖人にだまされて地獄に堕ちても後悔しない」とまで思い定め、本願を信じ念仏する身となられた。
法然聖人の弟子となられてからさらに聞法と研学に励まれた聖人は、法然聖人の主著である『選択集』と真影を写すことを許され、綽空(しゃっくう)の名を善信(ぜんしん)と改められた。そのころ法然聖人の開かれた浄土教に対して、旧仏教教団から激しい非難が出され、ついに承元元年(1207)専修(せんじゅ)念仏が停止された。法然聖人や親鸞聖人などの師弟が罪科に処せられ、聖人は越後(新潟県)に流罪。これを機に愚禿親鸞(ぐとくしんらん)と名のられ非僧非俗の立場に立たれた。
このころ恵信尼(えしんに)さまと結婚、男女6人の子女をもうけられ念仏の生活を営まれた。建保2年(1214)42歳の時、妻子とともに越後から関東に赴かれ常陸(茨城県)で自ら信じる本願念仏の喜びを伝え、多くの念仏者を育てられた。元仁元年(1224)ごろ、浄土真宗の教えを体系的に述べられた畢生(ひっせい)の大著『教行信証』を著された。
嘉禎(かてい)元年(1235)63歳のころ、関東20年の教化を終えられて、妻子を伴って京都に帰られた。『教行信証』の完成のためともいわれ、主に五条西洞院(にしのとういん)に住まわれた。京都では晩年まで『教行信証』を添削されるとともに、「和讃」など数多くの書物を著され、関東から訪ねてくる門弟たちに本願のこころを伝えられたり、書簡で他力念仏の質問に答えられた。
弘長2年11月28日(新暦1263年1月16日)、聖人は三条富小路にある弟尋有の善法坊(ぜんぽうぼう)で往生の素懐を遂げられた。90歳であった。
本願寺HP「親鸞聖人の生涯」より
必ず死ぬ私が 必ず助かる法を聞く
2013年8月
6月初旬、道道江別恵庭線で交通事故があり、たまたまその現場を通りかかりました。前方には、不自然に止まっている大型ダンプカー。その真横をゆっくり通りかかると、ダンプカーに食い込み正面衝突している乗用車がありました。
ダンプカーの運転手さんは特にけがはないようでしたが、乗用車の運転席に挟まれている人がいました。呼びかけても反応はありませんでしたが、救急車が来るまで励まし続けました。
大きなサイレンを鳴らして、救急車と消防車が到着。現場の状況を把握したうえで、ダンプカーと乗用車を切り離し、レスキュー隊の特殊な機械を使って車内から運転手さんが救出され救急車で運ばれていきました。
翌日の朝刊にその記事があり、残念ながら年齢20代の運転手さんは亡くなられました。
人生、どのような死に方をするのかわかりません。病気の場合もあるでしょうし、この方の様に、事故などで突然の場合もあるでしょう。近づく自分の死を考える余裕があれば「死にたくない」と心を乱し、泣き叫ぶかもしれない、暴れだすかもしれません。
そうであっても、冷静に考えるわずかな時間はあると思うのです。そんな時、「ああ、そういえば、阿弥陀様がお浄土を用意して下さったなあ」などと思うことでしょう。すると、「死」という苦しみは少し和らぐのではないでしょうか。
どなたか知らない人の死によって、有るのが当り前ではない、いのちに目覚め、気付かせていただく時、その方の人生も私の人生も、むなしく終わらぬ意味のある人生となるのです。必ず助かる法を聞かせていただきましょう。
(岩淵)
くりかえしえない人生
2013年7月
「苦しみに つぶされる人あり 苦しみを のりこえる人あり」
「私だけが、なんでこんな苦労をしなければならないのか。自分は世界一の不幸者だ」などと落ち込んでしまうような時が誰しも一度ぐらいはあるのではないでしょうか。それとは逆に、「苦しみは、のりこえるためにこそある」という言葉を告げた人もあったと聞きます。
順風満帆に人生を過ごすことだけが人間を成長させるものではなく、時には逆境にぶち当たり、困難を経験することが人間力を身につけるためには大切なのかもしれません。
くりかえしえない諸行無常の人生であるからこそ、苦難が我が身に降り注いだ時に愚痴と言い訳に終わるのではなく、その苦難を受け入れ真剣に向き合うことこそが、深いよろこびと充実に満たされた人生を生き抜くということではないでしょうか。
《真宗法要法話大辞典より》
人生の苦悩を 土壌として まことのいのち 花ひらく
2013年6月
釈尊の教えは、仏に成ることをめざし、享楽の夢を求めてさまよう人間の闇を破り、人生の楽しみも苦しみも皆『苦』であることを明らかにされた。
生きる喜びも、死の恐怖もすべて「生死の苦海」である。その苦しみの原因も知らない身を凡夫(ぼんぶ)といわれる。しかし苦悩する意味が明らかになれば、苦悩こそ、わがいのちとして苦悩の中に生きる知恵を頂く。それは泥中に咲く蓮華のごとく、凡夫の身にいのちの花がひらく。
真宗法要法話365日大辞典より
東西本願寺の分立
2013年5月
本願寺は、第8代の門主に蓮如上人が就任してから、社会的勢力を拡大していきました。それは戦国大名に匹敵するもので、天下統一を目指す織田信長にとって、支配権を奪わなければならない存在となっていきました。
第11代顕如上人の時代に信長は、当時、大坂の石山にあった寺地の明け渡しを要求してきます。それを本願寺は拒絶し、信長はこれを機会に、巨大な勢力をつぶそうと考え、1570年、石山戦争が始まります。約10年間続いた石山戦争の敗北に際して、教団内部では、和解を受け入れた父、顕如派と、徹底抗戦を主張する長男、教如派に分かれ対立していました。
その後、本願寺は、現在の和歌山県や、大阪府などに移転しましたが、豊臣秀吉の都市計画の一環として京都移転を命じられ、1591年、七条堀川の現在地に寺基を移すことになりました。
翌年、阿弥陀堂と御影堂が完成しましたが、顕如は積年の疲労で倒れられ、50歳で往生されました。即座に、教如は第12世を継ぎますが、顕如は、三男准如を後継とする旨の譲状を残していたため、教如は退職し、弟准如が第12世の法灯を継承しました。
その後、裏方と呼ばれていた教如は、徳川家康に親近し、烏丸七条に寺地を与えられます。ここに御堂を建立し、これが東本願寺の起源となり、本願寺が西と東に分立したのです。
家康の寺地寄進は、再び戦国時代の混乱が生じないように社会の変動、混乱を避けようとしていましたので、石山戦争以降、内部で対立していた本願寺教団を二派に分ける措置は、社会的、政治的に必要なものであったのです。
「早く来て 手伝ってよ」の 弥陀の呼び声
2013年4月
すべての衆生を救いたいと、二百一十億もの仏の国を覩見(とけん)し、五劫という長い間思惟して、永劫の修行で完成されたのが阿弥陀如来の西方極楽浄土です。その極楽浄土へ、「南無阿弥陀仏」のお念仏一つで必ず往生させたいというのが阿弥陀如来の願いです。「こっち、こっち、こっちへおいで」と呼ぶ声が、「南無阿弥陀仏」のお念仏なのです。そのお念仏に呼ばれて、浄土への道のりを感謝のうちに歩ませて頂くのが、私達の人生ではないでしょうか。
阿弥陀如来は、「この世の迷える衆生を救う仕事を共に手伝っておくれ」と、浄土から呼びかけておられます。お念仏申す人々は、もう既に仏の仲間であり、自分のよろこびや楽しみのためだけに浄土へ生まれさせていただくのではありません。仏様のお手伝いをさせていただくためなのです。
この世でも「南無阿弥陀仏」、浄土でも「南無阿弥陀仏」と、阿弥陀如来の大いなる慈悲に抱かれながら、深い安心の中でお念仏申す人生を、皆様と共々に歩ませていただきましょう。
《真宗法要法話大辞典より》
和顔愛語
2013年3月
【いつも言葉や態度を和らげて、互いに憎しみ合わないようにする】
「和顔愛語」とは「大無量寿経」のなかにあるお言葉です。この言葉は文字通り、和らいだ顔つきをして、優しく言葉でいつも人と接するという意味をもちます。
私たちは自分の心に思っているままに、顔つきや、言葉に表われるものです。嫌な人に会えばそれが顔に表われて、嫌な顔つきになる。腹が立つことがあれば、ついつい言葉もきつくなってしまいます。そのことが直接関係ない相手にまで不快な思いや心配という気持ちを与えているのです。 顔つきを見る鏡はあっても、自分の言葉遣いを映す鏡はありません。しかし腹が立っている時に、自分の顔を鏡に映す心の余裕があれば、その腹立たしい気持ちもおさまるものです。
日々、生活を送っていれば腹の立つこともあるでしょう。ですがそんな時に「自分も悪くなかったか」と考え、振り返る心を持つだけで腹立ちや、憎しみも和らぐものです。
世の中には、人を思いやる優しさの中に幸せがたくさんあるのです。
慶びの人生
2013年2月
生死の苦海 ほとりなし ひさしくしづめる われらをば
弥陀弘誓の ふねのみぞ のせてかならず わたしける (高僧和讃)
親鸞聖人が示されたこの和讃は、阿弥陀様のはたらきを讃えられたものです。
生死という、迷いの人生を送り、ほとりない深い苦しみの海に沈んでいて、自分の力では浮かぶことのできない石ころのような私を、阿弥陀様の誓われた本願の一方的なはたらきは、大きな船となって、私を乗せて下さり、迷いの世界を超えて、お浄土へと必ず渡して下さいます。
人生には、思いがけないことが起こるものです。そのような時、「こんなはずではなかった、なぜ、私だけがこんな思いをしなくてはいけないの、何か悪いものが影響しているのではないか」などと、不安な日々を過ごすこともあるでしょう。
思い通りにいかない苦しみ悩みは、時として、病気を引き起こす原因になるのかもしれません。生きている以上、様々な苦しみからは逃れることはできないのです。
阿弥陀様の教えをいただくことができれば、身の上に起こる全ての苦しみは、阿弥陀様が、用意して下さった励ましであると受け止められ、歩んできた今までの人生のひとつひとつが大切に感じられるようになるのではないでしょうか。
自分の人生を振り返り、「苦しいことも、悲しいこともあった」しかし、「何一つ無駄なことではなかったのだ、全て意味のあるものだったのだ」と、うなずくことができるのです。
そして、「少し遠回りしてしまったのか、もっと早く出遇うことができればよかったのに」と悔やむことがあるかもしれません。しかし、それは、「大切なものに出遇わす最も近道であったのだ。そして、今、もう既に、阿弥陀様の救いの手の中にいた、弥陀弘誓の船に乗せていただいていたのだ」と気付き、苦しみ悲しみを縁として、慶びの人生へと転じられるのです。
今、ここを、この身このままで精一杯に生かすはたらきに身をまかせ、穏やかな心をいただき、充実した、感謝のお念仏生活を送らせていただきましょう。
自己を見る
2013年1月
新年は私たちがお互いに心を新たにして、生活に新しい決意を持ってのぞむための、生活の区切りのようなものです。人間は時々区切りをつけないと、いつの間にか慣れてしまって心がゆるんでしまいます。新年を迎えるという事は、その心を引き締めるのにあたり、丁度いい機会ではないでしょうか。
私たちは毎日忙しく目まぐるしい世の中で生活し、休む間もなく色々なことに気を配り「忙しい、忙しい」と言いながら日々をすごしています。そうした中でも、他人の欠点や悪い事は何でもすぐに目についてしまいます。ところが、自分の欠点や間違いは気付かずやりすごしてしまいがちです。間違いの上に、間違いを重ね、気付いた時には取り返すことが難しい状態になることさえあります。
「鏡を使うのは人間だけ」と言われます。鏡に自分を写して自分を見る。つまり、自己を反省し自己を見つめ直すことができるのは人間だけなのです。
新年を迎えるにあたり、日々の行いや考えを反省し、ご縁の中で生かされる毎日を「おかげさま」と感謝させていただきながら、皆さんと共々に新しい年の始まりを慶ばせていただきましょう。
《真宗法要法話大辞典より》
| << 次号 | 前号 >> |
|---|