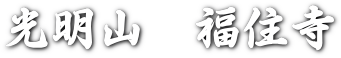月報「なむ」
2012年
家の中も心の中も大掃除
2012年12月
今年も早いもので一年を終えようとしています。皆さまも今年一年、色々な出来事があったかと思います。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、苦しいこともあったでしょう。色々な出来事の中で、良いことだけは過ぎないでいてほしい…。そんなに都合は良くいきません。
お寺で配布させていただきました法語カレンダーにも「人生の苦しみは仏様のはげましである」というお言葉がありました。悪いことがなければ良いことも『良い』と感じられないのではないでしょうか。良いことだけでは嬉しいことも楽しいことも当たり前になってしまい、ますます心が満たされなくなってしまいます。これも私達の煩悩の一つです。時には嬉しく、楽しいことも、時には悲しく、苦しいこともあります。出来事の一つ一つが仏様のはげましといただきながら、皆さまと共々に除夜の鐘をつき一年を振り返り、新たな年を迎えご縁、ご恩の毎日を歩まさせていただきましょう。
心の窓
2012年11月
み仏の み名を称える わが声は
わが声ながら 尊かりけり (甲斐和里子)
お仏壇は「心の窓」であるといわれます。窓と言えば、光を取り入れることと、空気を入れかえるという大切な役割があります。
部屋の中に光を取り入れると、暗い部屋が明るくなり、物につまずくことなく、ごみの1つでも目に付けば、掃除をする気も起きるでしょう。
それと同じように、私の心にも窓がなければなりません。お仏壇で阿弥陀様の光にあわせていただくのです。すると、今まで気づきもしなかった、心の中のごみや垢に気づき、怒りや腹立ちといった、愚かな心を抱えている自分の本当の姿に気付かせていただくのです。
窓のもう1つの役割は、空気を入れかえる換気の役目です。私達の心の中にも日々、もやもやとした濁った空気が立ち込めます。
愚痴がたまり、いらいらし、あの人が悪い、この人が悪いなど、押さえていると爆発しそうになってしまいます。
そのような時、お仏壇の前に座り、静にお念仏を称える、すると自然に心は落ち着き、穏やかにおさまることもあるでしょう。
人生には、恐ろしい事、いやなこと、悲しい事など様々な出来事がおこります。しかしどんな状況になろうとも、しっかりとこの私を支え、お導き下さるのが阿弥陀様です。
お仏壇は今を生きている私のために、阿弥陀様を心のよりどころとして、身近に仰ぎ、導かれて生活するために必要なのです。
そのお方が、私の家にまでお姿を現して下さっている、それがお仏壇です。
先立たれた方々を偲び、お参りを大切にするということは、それはそのまま、自分自身を大切にするということに、つながっているのではないでしょうか。
和顔愛語
2012年10月
「和顔愛語」とは大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)というお経の中に示された言葉です。この言葉は、「和らいだ顔つきをし、いつも優しく穏やかな言葉遣いで人と接する」という意味です。
私達は、自分の心に思っているまんまが、顔つきや言葉に表れがちです。嫌な人に会えばそれが顔にあらわれて、嫌な顔つきになったりしてしまいます。腹が立っているときは、ついつい、きつい言葉遣いになっていたりします。そのことが、直接関係のない第三者にまで不愉快な気持ちを与えてしまうものです。
自分の顔つきをうつす鏡はあっても、心や言葉遣いをうつしだす鏡はありません。しかし、腹が立ったときに「はたして自分は悪くはなかったのだろうか?」と、あらためて自分自身を省みる心を持つだけで、腹立ちや憎しみは和らぐのではないでしょうか。
他人のせいにしたり、世の中を嘆くだけではなく「和顔愛語」と人を思いやる優しさこそが、実りある人生を過ごすために必要なことではないでしょうか。
真宗法要法話大辞典より
一秒が尊く感じる人生を
2012年9月
後、二十年も生きていたらいいな、子供も一人前になるから・・・(四十代男)
何言うとるの、二十年くらいすぐ来るよ、人生あっという間やで・・・(六十代女)
そうそう、時間が長いと思うのは、待ってるときや。
他人を待たせてるときは、すぐ時間がたつけどな・・・(五十代女)
そういえば、物心ついた頃からある年齢までは、時間がたつのがずいぶんゆっくりだったような気がする。だが次第に早く感じるようになり三十歳も過ぎると毎年が本当に早く終わっていく。
ということは子供の頃は、何かを待っていたから長く感じていたのかもしれない。大人に成長して行く時間がやってくるのを待っていたのだろう。
ところが、いつの頃からか時間が早くなった…。
時間の早さが変わっているのではなく、自分の感じ方が変わっているのではないだろうか。
早く感じるようになったのは、そんなわたしへのご催促なのだろう。
「大事なことを忘れるな『万障繰り合わせて、死はやって来る』のだから」と。
なにを恐れますか、あるがままを受け入れられますか?
大事なことは一日一日を大切に、ありがとう、ありがとうと感謝のお念仏を申す人生を共々に歩んでいきましょう。
一分、一秒が尊く感じる人生を。
真宗法話大辞典より一部引用
再び会える世界がある
2012年8月
浄土にて かならず かならず まち まゐらせ候ふべし(親鸞聖人御消息)
私達一人ひとりには、受け継がれてきた数多くのご先祖様のいのちがあります。お盆には、仏壇や墓前に手を合わせ、先立たれた方々のご恩を偲び、改めて今あるこの身の幸せに感謝を申させていただくものではないでしょうか。
大切な方、身近な方を亡くされたことを思うとき、生前の様々な思い出の中、言いようのない寂しさがこみあげてくることもあるでしょう。
親鸞聖人は、晩年お弟子へ宛てられた手紙の中で「この身は今は年を重ねました。きっとあなたより先に往生するでしょうから、お浄土で必ず必ずあなたをお待ち申し上げます。また会いましょうね。」と言われ、再び会うことに間違いのない世界を慶ばれたのです。
大切な方を亡くされた大きな悲しみは、阿弥陀如来の本願力によって同じ信心をいただき、その救いの手の中にある。だからこそ、先立たれた大切な方も、迷いの人生を送っている私たちも、必ず浄土で再び会える確かなことを、今ここで慶ぶことができるのです。悲しみ苦しみは無くならないけれど、その事実を受け入れ乗り越えていく力となるのではないでしょうか。
8月はお盆の季節、9月1日、2日には、年中行事の中で最も大切な、親鸞聖人の遺徳をしのぶ報恩講が勤まります。
先立たれた数多くのいのちが、今あるこの私に伝えて下さった本願力の教えを大切に、感謝の日暮らしをさせていただきましょう。
たった一言が
2012年7月
たった一言が ひとつの心を傷つける
たった一言が ひとつの心を温める
私たちは何気なく人と話をしたり、人の話を聞いたりしていますが、私の口から出る一言一言が、時には相手を知らぬ間に傷つけ、いつまでも心の中に不愉快な気持ちを残すこともあります。それはただ単に、口から出る言葉だけではありません。私達の行い、身の振るまいにおいても同様です。では、人の心を傷つける言葉と温める言葉とは、どこからその違いが出るのでしょうか。
お釈迦様は「言葉や行いを清らかにしようとするならば、先ず心を浄めよ」と教えられています。私達の言葉や行いも結局は私の心のあらわれなのです。お釈迦様が説かれた心の持ちかたは、「我執を捨てよ」ということでした。私達は長い人生の中で、しかも生存競争の激しい世の中で自分だけが生きる、自分だけがより幸せな生き方ができればよいと、他人を無視して思い上がった気持ちになりがちです。そこでお釈迦様はその思い上がった気持ちに気付き、自己中心的な執着から離れなさいと教えられたのです。
何事も相手の身になって考え、おかげさま、おたがいさまと感謝の気持ちを持って接することができたなら、心豊かな人生をすごせるのではないでしょうか。
《真宗法要法話大辞典より》
実りある人生へ 〜人生に代理人はいない〜
2012年6月
「人生は道なり、道とは自らの責任において歩むものなり、独り生き、独り死ぬものなり」と、日々、仏さまのお心をいただく人生の中で、あらためて気づかせて頂く毎日でございます。
この一回限りの人生を、時代が悪いから、世間が悪いから、家の建ち方が悪いからといって通り過ぎるには、あまりにも勿体ないことではないでしょうか。自らのいのちと人生を、掛け値なく正しく見つめて、代理人のきかないこの人生を、自ら背負って、責任を果たして生きることこそ、実りある人生ではないでしょうか。
《真宗法要法話大辞典/中西智海 師より抜粋》
二河百道の譬え
2012年5月
ひとりじゃない ほら 仏様と一緒だよ
浄土真宗を開かれた親鸞聖人がお敬いされた中国の高僧、善導大師様が「二河白道の譬え」によって、次のように教えてくださいます。
人生は旅だと言われますが、旅人が西へ向かって行こうとした時に、目の前に行く先をふさぐ河が現れました。南側には荒れ狂う火の河が、北側には同じように水の河があり、その河は無限に続いています。
その火の河と水の河の中間には、幅わずか四、五寸、人が一人やっと通れるような細くて白い道が、東から向こう側の西へとつながっています。それは長さ百歩くらいの道で、絶えず炎と水が襲いかかり、とても渡れそうにありません。しかも、振り向いてみると猛獣が追いかけてきて、すぐそこまで迫ってきているのです。
西へ進めば火の河か水の河に飲み込まれ落ちてしまいそうですし、立ち止まっていても猛獣に命を取られることになってしまいます。
そんな時、東の岸から「行きなさい」という、お釈迦様の励ましが聞こえ、西の岸からは「私を信じて来なさい」という呼び招く阿弥陀様の声が聞こえてきました。
そして、旅人は、ためらうことなく一筋の南無阿弥陀仏のお念仏の道を歩んで往くものでした。このたとえは、東の岸を、悩み、苦しみ、欲望のままに生き、いつかは空しく終えてしまう私達の迷いの世界としてあらわされています。
このような世界から荒れ狂う煩悩を越えて到達するのが、阿弥陀様の世界、お浄土という西の岸です。欲望にまみれ悩み苦しむ迷いの人生を送る私達に「二河白道の譬え」は歩むべき道を教えて下さいます。
ひとりじゃない、仏様に護られ、支えられ、安心した人生を歩みますか?それとも、空しく寂しい人生でいのち終わっていきますか?
大きな違いがあるのではないでしょうか。
今日もまた、まっさらな一日がはじまります
2012年4月
私たちはしばしば、時間に対し不満をもらすことがあります。「一日の経つのが早い」と。
さらに一週間、一か月、一年などに対しても同じことを感じたり、言ったりしています。
しかし、それは逆で正確に刻まれている時間を、自分の思いや感じで「速い」、「遅い」とか言っているに過ぎないのです。特に「速い」「遅い」と言っている人にとっては、『一生』も「ああ速かった」で終わってしまうのではないでしょうか。
「人間一生、酒一升、あるかと思えば、もう空か」というのを思い出しました。
あたかも、湯水のように時を浪費して来た私は、今日一日を、宝もののように出会い、尊み、歩んで参りたいと思うこの頃です。
《真宗法要法話大辞典より》
彼岸の由来
2012年3月
お彼岸の中日は、ちょうど昼間の長さと夜の長さが同じで、太陽が真東から昇って真西に沈む特別な日です。古来、太陽信仰の篤かった私たちの祖先は「どうか今年もたくさん作物がとれますように」と太陽に拝み、神仏をお祀りしておりました。真西へ沈む夕日に極楽浄土を重ねて思いを馳せ、祖先をうやまい亡き人をしのぶ日となったともいわれています。彼岸とは文字どおり彼の岸のことで、一般に冥土は暗闇で、死者が赴く世界と考えられていたようです。庶民の信仰では、太陽が沈む西の方は死後の世界を意味していましたが、仏教が輸入されるようになると、迷いの娑婆世界である此岸(しがん)に対して、彼岸は悟りの浄土として説かれるようになりました。彼岸に至ることを古いインドの言葉で「パーラミター」と言い、中国人はこれを波羅蜜多(はらみた)と音写しました。これから悟りを求める人が実践すべき行いを波羅蜜(はらみつ)と言うようになり、施すこと(布施)、慎むこと(持戒(じかい))、耐えること(忍辱(にんにく))、励むこと(精進)、心を鎮めること(禅定(ぜんじょう))、ちえをみがくこと(智慧)、この六種の行法を六波羅蜜(ろくはらみつ)と呼び、お彼岸の中日と前後三日間を合わせて七日間の修行を行ったそうです。インドには仏教以前から、善いことをしたものは善い世界に生まれかわり、悪いことをしたものは悪い世界に生まれかわるという輪廻転生(りんねてんしょう)の考えがありました。しかしお釈迦さまは、すべてのものは関わりあって存在しているという「縁起の法」を説かれ、輪廻転生を超えることを目指されたのです。輪廻転生から解き放たれ、脱することを解脱(げだつ)と言い、六波羅蜜のような仏道修行は、死者の国に行くためのものでなく、ブッダ(目覚めた人)になるために彼岸を目指すことなのです。ところが私たちは、地獄、餓鬼、畜生の悪道(三悪道(さんまくどう))へ落ちるタネ作りの道を走り続けています。阿弥陀さまは、箸にも棒にもかからない私たちを「救いの目当て」であるとされて、「私を力にしなさい、頼りにしなさい」と呼びかけて下さっているのです。お彼岸のお参りを、阿弥陀さまに感謝をささげ今日の自分をお育て下さったご先祖の方々に思いをはせる機会としたいものです。
(真宗法要法話大辞典抜粋)
門徒もの忌み知らず
2012年2月
日日是好日 ふっても てっても
日日是好日 泣いても 笑っても
きょうが一番いい日
私の人生の中の
大事な一日だから (相田みつを)
「門徒もの知らず」という言葉は「門徒もの忌み知らず」が語源といわれています。「門徒」とは「一門(いちもん)の徒輩(とはい)」とか「同門(どうもん)の徒弟(とてい)」を省略した言葉といわれ、僧俗ともに同じお念仏の教えをいただいている仲間という意味で使われております。
「もの忌み」とは、日の良し悪し・方位・墓相・家相・姓名判断などの迷信や俗信をいいます。
代表的なものには、暦の六曜(ろくよう)「友引」があります。日頃あまり気にしない方でも、突然の葬儀などにあうと「友引に葬儀はさける」と考えられます。これは「死者が友人を引っ張って、さらに死人が出る」という考え方のようですが、何の因果関係もない文字の連想であり、気にする必要はありません。しかし、現在、札幌市の火葬場 では「友引」を休日としていますので、おのずと葬儀のできない日となっております。
さらに葬儀に関する「もの忌み」には「一膳飯」「守り刀」「左前の死装束」「六文銭の頭陀(ずだ)袋(ぶくろ)」「棺の釘打ち」「お清めの塩」など、死を忌み遠ざけるものとしてありますが、死をご縁に仏縁を深めることが大切な門徒には必要ありません。
「日日是好日」とは、いつでもどんな時でも好い日であるということです。もし病気になったとして「病気をしたおかげで健康のありがたさがわかる」というように、自分にとって都合の悪いことが起きたとしても、比較の物差しを離れ、受けとめ、我が身を振り返る機会をいただいたと味わえたなら、悪い日だと思っていたものが、好い日へと転じられていくのでしょう。
何の根拠もないことに身を煩わし心を振り回されるのではなく、しっかりとした精神的基盤をいただいて、その日その時の人生を大切に歩ませていただくのが「門徒もの忌み知らず」の念仏生活といえるのではないでしょうか。
私の煩悩に正月休みなし
2012年1月
皆様にお念仏相続にてお正月をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
昨年は、親鸞聖人750回大遠忌、また福住寺開教120年と節目の年を迎え、皆様のご尽力、ご協力のもと九月には大法要を厳修させていただき、盛会裡のうちに本年を迎えることができました。門信徒の皆様にはあらためて感謝とお礼を申し上げます。
浄土真宗におきましては、「一年の計は元旦にあり」と言い習わすことから、「念仏を正しく身に修める法会」として元旦会をつとめます。
「私の煩悩に正月休みなし」
私たちは毎日毎日煩悩いっぱいで生きています。これをなくすことはできません。
煩悩は、なくすことはできないが、気づくことが大切なのです。煩悩いっぱいで生きていながら、煩悩に気づいていないからどうしようもない不安や苦しみを抱え込んでしまうのです。
深い思考を通して煩悩からの解放を完成された阿弥陀仏は、南無阿弥陀仏となってこの私に届き、わが心の在り様が知らされたとき、自然に頭が下がり、すがすがしい心の夜明けが訪れるのでしょう。
蓮如上人は、「あらたまの年のはじめは祝うとも 南無阿弥陀仏のこころわするな」と詠まれ、念仏あってこそ新年が本当の新年になるのだ、と教えられます。
福住寺も一日に午前十時から元旦会のおつとめをします。
本年も共々にお念仏の歩みをしましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|