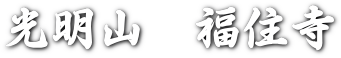月報「なむ」
2011年
行く年 来る年 除夜会・元旦会のご案内
2011年12月
除夜の鐘に心のすすを払い新年を迎える人は幸せである
除夜の鐘に心のすすを払いきれぬ重さに気づく人はさらに幸せである
お念仏の光りに照らされているからこそ払いきれない心のすすにまみれた私に
気づかせていただける
■除夜会 /12月31日(土) 午後11時30分より除夜の鐘(梵鐘)を撞いていただきます
■真夜中の成人式 /1月1日(日) 除夜の鐘に引き続き午前零時よりご家族に成人式を迎えられ る方がおられましたら記念品を差し上げますのでお寺までご連絡ください!
■元旦会 /1月1日(日) 午前10時より
元旦会は新年を祝うと同時に今年もお念仏と共に日々を送らせていただく誓いを新たにするお正月のすがすがしい行事です。「一年の計は元旦にあり」といいますが、浄土真宗の門徒にとって元旦は、真実に生かされる身の幸せを喜び、この一年をお念仏のみ教えをよりどころに送る決意を新たにする日です。元旦の朝には家族揃って家の仏壇に灯りを 点じ、仏さまに年頭のお参りをして新年を迎えたいものです。
※除夜会、元旦会ともに景品を用意し楽しい抽選会を催します。ご家族揃ってお参りください。
お見舞いの心構え
2011年11月
あなた往く人 私少し遅れて往く人 共に浄土に歩む人
本年7月17日、鹿児島から長倉伯博師を迎えての仏教講演会が開催されました。先生は病院内で活躍されている僧侶で、大変重い病気を抱えられた方や、そのご家族の苦しみ悩みに寄り添われた20年の経験を通しての講演をいただきました。
思い通りにならない人生、時には重い病気を抱えていかねばならないことがあります。「あなたは重い病気ですよ」と言われた時から、本人もその周りにいる家族も苦悩の多い人生を送ることとなるのです。お見舞いに伺う時に「大丈夫?頑張って」などという言葉をよく使いますが、それは本当に患者さんを励ますことができているのでしょうか。
命に関わる重い病気を抱えられ、闘病生活を送り、頑張っている方に対して「大丈夫?」と言われた患者さんの返事は「はい大丈夫、頑張ります」に決まっているのではないでしょうか。励ましたつもりが相手には辛い言葉となるのかもしれません。
お見舞いで一番良くないのは、「お医者さんは、何て言っているの?いつからだったの?そして今どうなの?」などと、詮索するお見舞いだそうです。
見舞う側から相手を問い尋ねることはせず、腹を据えて相手の心を、どんなことでも受け入れて聴き、話をしやすいよう促してあげることが大切です。
患者さんに寄り添い「傾聴、受容、促進」することによって「この人は私の心と一緒にいてくれた」と感じさせ、その人の孤独感が和らぐのです。人は話を聞いてもらうだけで、心が癒されるものではないでしょうか。
「あなた往く人、私少し遅れて往く人、共に浄土に歩む人」という心構え、また、逆の立場で言えば「私先に往く人、あなた少し遅れて来る人、共に浄土に歩む人」と心得たならば、わずかでも心にゆとりと安心をいただくことができるのではないでしょうか。
先生の医療チームは、死という事実から逃げずに「辛いけれど事実を支え合う」ことを大切に活動されているそうです。命に関わる心構えを考えさせていただくご縁となりました。
幸せとは、比較の物差しを捨てること
2011年10月
案外、人は「幸せになりたい」というよりも、「幸せだと思われたい」と願っているのではないでしょうか?
いつの日からか、私達は「幸せとは何か」ですとか「幸福論」というような話題で、幸せについて考えるようになりました。一昔前、某お笑いタレントが「幸せってなんだっけ、なんだっけ」と商品を手に取って歌っていたのを何故か鮮明に覚えています。世の中には金銭的な充足が幸せだと考える人がいたり、立身出世こそが幸せだという人もいれば、最低限の衣食住が整っていれば幸せだと感じる人もいて、それぞれです。それで満たされていればいいのですが、満たされているのに幸福を味わえない人もいると思われます。
その原因として考えられるのは、常に自分を他人と比較するからではないでしょうか。
幸せを感じるのはあくまで自分自身です。マイペースでゆったりと生きること、そして「足を知って、分に安んじる」という心得こそが、幸せな人生だと思います。
(真宗法要法話365日大辞典より)
福住寺開教120年記念慶讃法要
2011年9月
開教120年記念慶讃法要を厳修いたします。明治26年に福住寺が建立されて以来、み教えを心の支えとして、お寺のために尽力された多くの皆様によって護持され120年の年月が流れました。平成19年から始まりました開教120年記念事業により、会堂と庫裡の改築、永代廟の建設、境内地の総合整備が行われ、慶讃法要にて円成となります。
お寺とは、様々な人々の願いの上に建立されております。一人ひとりの願いを大切にするとき、間違いなく届いているお念仏の光に照らされて、お寺の本当の役割が見えてまいります。お寺そのものが、「世のなか安穏なれ 仏法ひろまれ」と伝えていく拠点となり、実践していく場にならなければなりません。
お念仏が伝わるという阿弥陀様のお働きは、大悲心が根本にあります。それは、大いなる共感・共苦の心です。お念仏を伝えていく実践の場としてのお寺の役割とは、お念仏申す生活の中で、共感・共苦の心を育てていくことではないでしょうか。それは、様々な人々とのふれあいの中で関わる事と真向かいになるということであり、人間は一人で生きているのではなく、怒っても、愚痴を言っても、悲しくても、それは人の間にあることの証拠なのです。阿弥陀様は私達から逃げずに、いつでもどこでも真向かいになってくださいます。決して見捨てないぞという願いがあるからこそ、私達の悲しみや苦しみを我が苦しみとして受け止めてくださるのです。
私達一人ひとりが阿弥陀様の一子であると想わせていただき、安心感のある共感・共苦の空間としてのお寺の役割の大切さを皆様と共々に感謝させていただきましょう。
(真宗法要法話大辞典一部抜粋)
福住寺開教120年記念慶讃法要
2011年8月
数百年に一度と言われる大地震によって、大きな津波が東北地方を広範囲で襲い、数多くの方々が犠牲になり甚大な被害となりました。さらには福島原子力発電所の放射性物質による事故、それに伴う風評被害など、現在でも数知れない大勢の方々が避難所生活や、不便な生活をし、大変なご苦労をされております。
この大震災は、物の豊かな時代を送らせていただいている私達に、自分の人生を見つめ直す機会を与えて下さっているのではないでしょうか。
7月18日、サッカー女子ワールドカップドイツ大会決勝で、「なでしこJAPAN」が米国をPKの末、破り優勝、史上初の快挙を成し遂げました。体の小さな選手達は、見事なチームプレーで、信頼し支え合う姿を見せ、世界一となったことは、大変な災害を抱える日本人にとって、励みになる結果となったことでしょう。
また、4月より本山では、50年に一度の尊い御勝縁であります親鸞聖人750回大遠忌法要が勤まっております。そして、9月には当寺で開教120年記念慶讃法要が厳修されます。
今、私達は、後世に残る歴史の只中におります。たまたま人間として、この時代に生まれてきた私。生まれることの難しい人間に生まれ、大変な大震災に遭い、さらに遇うことの難しい仏法に今、出遇っている不思議さと、歴史の重さを感じます。
明治26年に福住寺が建立されて以来、み教えを心の支えとして、お寺のために尽力された多くの皆様によって護持され120年の年月が流れました。平成19年から始まりました開教120年記念事業により、会堂と庫裡の改築、永代廟の建設、境内地の総合整備をさせていただきました。そしていよいよ来る9月1日から3日まで行われる慶讃法要によって円成となります。
これまで福住寺を支えて下さいました先人達のご苦労を偲び、また、この法要を迎えさせていただく喜びを味わいつつ、是非、皆様お揃いで参詣いたしましょう。
子から親へ
2011年7月
先日、初参式(赤ちゃんの初参り)が本堂にて執り行われました。毎年、ご門徒さん等の赤ちゃんに参加して頂いていますが、今年は私の友人の赤ちゃんにも一緒に参加してもらい、皆様でお参りをさせていただきました。
数日前にその友人のお宅に行った時のことでした。ふと、棚の上に目を向けると「無量寿」と書かれた赤ちゃんの手形が押してある色紙。その横には「おしゃかさま」の絵本が飾られてありました。これは、初参式の記念品としてお寺より、参加していただいた赤ちゃんにお渡ししたものです。眺めているうちに、友人の奥さんより、「ありがとうございました。むすめから、お寺にお参りする機会をもらいました。」続いて友人からは、「自分もお参りに参加してみたかったです…。」との事、友人は仕事のため参加できず。奥さんからお参りの様子を聞いたのでしょう。それからの会話はお寺や、お経の質問など…。いつもの会話とは全く違う内容に私は少々調子がくるってしまう反面、何か少し嬉しい気持ちにもなりました。
色紙に書いてあった「無量寿」とは、量ることのできない限りない命を持つ仏さまのことです。「生きとし生くるものを救う」と誓われた阿弥陀様の願いの中に生かされ、仏さまに抱かれているのです。尊い命の誕生とともにいただいた仏さまとのご縁、阿弥陀様のお慈悲の中で育っていく事を共々に喜び、感謝させていただきましょう。私自身も、この世に生を受け、仏法に出遇わさせていただける喜びを友人との会話の中で今一度、気付かせていただきました。
思いを分かち合う
2011年6月
平成17年1月9日に、ご門主様より『親鸞聖人750回大遠忌法要についての御消息』をいただき、平成23年4月から、平成24年1月まで「親鸞聖人750回大遠忌法要」が修行され、いよいよ宗門至重のご法要に遇わせていただくこととなりました。しかしながら、この度の大遠忌法要は、東日本大震災を受けての法要であり、宗門では地震発生後、先行きの見えない不安を抱えながら生活されている被災者の方々に対し、「緊急災害対策本部」を設置するとともに、本願寺仙台別院内と、本願寺築地別院内に「現地緊急災害対策本部」を設置し、一日も早い復興を願い支援活動を行っております。ご門主様からは、「宗門では、すべての被災された方々の悲しみに寄り添い思いを分かち合いたいとの願いを持って、4月9日より親鸞聖人750回大遠忌法要をお勤めいたします。阿弥陀如来のお慈悲のなかに、ともに支え合う宗門であることを心にとめていただき、心身ともにお大切にお過ごしになられますよう念じます。」との、お言葉が届けられました。「世の中 安穏なれ」という、親鸞聖人のお心を受けた750回大遠忌法要のスローガンのもと、我々一人一人が共に生かされているという事に気づき、心の有様を見つめ直す機縁とさせていただく事が大切なのではないでしょうか。今日まで受け継がれてきたお念仏に遇い得た喜びを、この度の大遠忌法要を通して、皆様と共々に味わわせていただきましょう。
失ってみて気付く大切なこと
2011年5月
死者行方不明者2万7千人以上という災害に見舞われた東日本太平洋沖地震から1カ月以上が過ぎました。現在も被災された多くの皆様の厳しい避難生活が続いております。
私達は物の豊かな時代を送らせていただいておりますが、失ってみて気付くことが多くあります。家が無くなり家の大切さがわかる。電気が無くなり電気の大切さを思う。水が無くなり水の大切さに気づく。ある被災者の方は「家を流され、車を流され、すべて失いましたけれど、この命が助かっただけでもありがたいです」と言われました。私達は今、この大災害を目の当たりにし、便利な世の中にあって自分の生活はこのままでいいのだろうか、自分に今、何ができるのだろうかなどと、失われた多くの命が、自分自身をかえりみる機会を与えてくださっているのではないでしょうか。
当寺では、震災の翌日から義援金箱を設置し、4月15日現在で累計100,742円が寄せられました。心温まる義援金は、西本願寺の「たすけあい募金」を通じ、東北の皆様へお届けさせていただきます。尚、義援金箱は引き続き設置しておりますので、ご支援ご協力下さいますようお願い申し上げます。
本年9月には開教120年記念事業の「慶讃法要」、「帰敬式」「お稚児さん」などの関連行事、そして11月には「団体参拝旅行」を計画しております。大震災にて行事を自粛する考え方もあろうかと思いますが、今、私達ができることを精一杯させていただく日頃の活動そのものが、被災された方々への支援につながっていくものであるのではないでしょうか。皆様には何卒、ご理解ご協力を賜り、各行事への積極的な参加申込をよろしくお願いいたします。
亡き人をご縁として
2011年4月
明治時代に活躍し、浄土真宗のみ教えをいただいた伊藤左千夫は、娘の七枝ちゃんを1歳10ヵ月で亡くした時のことを、『奈々子』という小説に書いています。
左千夫は、娘の七枝ちゃんが池に落ちたという知らせを聞き、驚いて飛んで帰りましたが、すでに手遅れでした。左千夫は常々、子どもが池に落ちたら危ないと思っていたので「どうして早く池を埋めてしまわなかったのか」と自分を責め「もう泣くより外はない。自分の不注意を悔いて、自分の力なきを嘆いて泣くより外はない。我が子を見守って泣くより外に術はない」と書いています。その時に詠んだ歌が
「み仏に救われありとおもひ得ば、嘆きは消えむ消えずともよし」
という歌です。「七枝ちゃんはお浄土へ帰って往ったとわかっていても本当に大丈夫だろうか。仏様に救われたとわかっていても、嘆きは消えるだろうか。消えなくてもいい。私は生涯かけて七枝ちゃんのことを、しっかりと思い続けていくのだ。」という内容です。「月日がたてば悲しみや嘆きは消える」というような話ではありません。
お念仏のみ教えは、心の取り繕いではなく、思い通りにならないこの身の現実を受け止めるということです。その現実を気付かせて下さるのがお念仏のみ教えなのではないでしょうか。もし、左千夫がお念仏のみ教えに出遇えていなかったなら、現実逃避するか、慰めを求めて彷徨っていたかもしれません。
亡き人が、自らの死をもってお示し下さった、思い通りにならないこの身の現実を「ご縁」としていただき、「いのちを生きる」ということの意味をあらためて見つめ直し、しっかりと人生を生き抜くことが大切なのではないでしょうか。
また会いたいね
2011年3月
『人は死んだらゴミになる』そんなタイトルの本がありました。内容は知らないがなんとも悲しいタイトルです。
ある大学の教授の書かれた本にこんな事が書かれてありました。「私は無信論者で、人は死んだら灰になるだけと、誰彼無く、そう話していました。そんな折、孫娘が白血病に成り、苦しい息の中、私を呼んで病室でこう聞きました。
「おじいちゃん… 死んだらどうなるの?」と。私は「死んだら灰になるだけ」そうは言えませんでした。
子供の頃、祖父母が話していたことを思い出し、亡くなった者は皆、阿弥陀様のお力でお浄土へ生まれ、同じところでまた会う事が出来る(倶会一処)と話し終えたら、「おじいちゃん、まってる」と言って息を引き取ったのです。
私の考えはそれから変わりました。お浄土は必ずあります。いや、なければならない。」と書いてありました。
浄土は願いの世界。また再び会いましょうの世界。死んだらおしまいと言う人には浄土はありません。しかし、死んでからの話ではなく、二度と会いたくないと思いながらの生活はそのまま地獄であり、願い合える生活をしている人はすでに浄土にいる人だと私は思います。
『真宗法要法話365日大辞典』より
世の中安穏なれ
2011年2月
昨年末、群馬にある中央児童相談所の玄関に10個の箱入りランドセルが届けられていたのをはじめとして、全国の児童相談所や児童養護施設などへ、様々なものが寄贈されタイガーマスク現象ともいうべき運動が各地でおきております。
多くの送り主は、40年程前、プロレス漫画「タイガーマスク」の主人公「伊達直人」を名乗る人がほとんどです。孤児であった伊達直人は、施設で育ちましたが、レスラーとして活躍し、自分を育てて下さった感謝の心から、様々なものを施設の子供たちへ届けました。
素晴らしい運動だと思いますが、送り主自身の名前を公表しない方が多いのです。もしかすると、その行為をねたまれ、批判される恐れがある、人間社会が原因なのかもしれません。
人とのつながりが希薄であると言われる現代に、自分の幸せをわずかでも分け合い、皆が幸せに、心温まる人間社会になってほしいという願いが広がりを見せているのでしょう。
「世の中安穏なれ」という親鸞聖人の言葉は、多くの人が「自分のため」だけではなく「人のため」に行動するということで実現されるよう願っているのです。
仏様に願われ生かされている私達。人は誰かに必要とされたり、願われたりすることで、自分の居場所が確保され、生きる希望や勇気、元気を与えてもらえるのではないでしょうか。
謹んで新春のお慶びを申し上げます
2011年1月
新しい年を迎えました。「正月」という言葉は、政治に専念した秦(しん)の始皇帝(しこうてい)の生まれ月である1月を政治の月、政月(せいがつ)と称していたのが、いつのころか正に変わって「正月」となり、読み方も「しょうがつ」になったと言われています。もともと「正」という字には年の初めという意味があり、「正月」とは年の初め月という意味になります。また、「正しい」には「まっすぐ」という意味もあり、元旦を機に「物事を真っ直ぐな心でみているか」を問い正し、自分自身を振り返り反省し、本当に正しい生き方とは何なのかを確認していく節目ではないでしょうか。大掃除をして新年を迎えるように、この一年をどのように生きるのか、新年にあたり己のいのちを見つめ直し、襟を正していく時なのです。
阿弥陀様はお念仏となって、「我が名を人生の依りどころとして生きぬいてくれよ」と、よび続けてくださっています。仏様の呼び声に素直に耳を傾け、己を見る眼を育んでいきましょう。
本年は親鸞聖人750回大遠忌(だいおんき)ならびに、福住寺開教120年の年に当たり、福住寺にて記念法要が執り行われ、数々の行事が予定されております。このたびのご勝(しょう)縁(えん)を有り難くお迎えし、皆様と共々にご参拝させていただきましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|