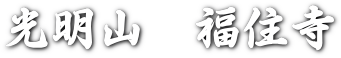月報「なむ」
2010年
行く年 来る年 除夜会・元旦会のご案内
2010年12月
■除夜会 12月31日 (金) 午後11時30分より
除夜の鐘 (梵鐘)撞いていただきます。
■真夜中の成人式 1月1日(土)
除夜の鐘に引き続き午前零時よりご家族に成人式を迎えられる方がおられましたら記念品を差し上げますのでお寺までご連絡ください!
■元旦会 1月1日(土) 午前10時より
元旦会は新年を祝うと同時に今年もお念仏と共に日々を送らせていただく誓いを新たにするお正月のすがすがしい行事です。「一年の計は元旦にあり」といいますが、浄土真宗の門徒にとって元旦は、真実に生かされる身の幸せを喜び、この一年をお念仏のみ教えをよりどころに送る決意を新たにする日です。元旦の朝には家族揃って家の仏壇に灯りを点じ、仏さまに年頭のお参りをして新年を迎えたいものです。
※除夜会、元旦会ともに景品を用意し楽しい抽選会を催します。ご家族揃ってお参りください。
「救われる」とはどういうこと?
2010年11月
チリの鉱山落盤事故にて、地下約700メートルの地点で2カ月余りの間、閉じ込められていた33名の方々が救出されました。よろこびの報道が多くされていますが、救出され病院へ搬送されたある人は「今こうして生きていることが本当にうれしい」と言っておりました。
普段、私達は今あるこのいのちを素直に喜ぶことは難しいのかもしれません。欲望の多い人生、自分の思い通りになることは少なく、我慢しなくてはならないことが多いものです。それがストレスの多い社会と言われる原因なのでしょうか。
人間の社会は法律や規則によって行動が制限されており、私達のいのちは4つの限定の中に生きていると言われています。1つには「誰にも代わってもらうことができない」ということです。自分が日本人として生まれたこと、男や女として生まれたこと、体が丈夫だったり弱かったりすることなど、自分の人生は自分が生涯背負っていかねばなりません。2つには「やり直しがきかない」ということです。振り返り反省することはできますが、やり直すことはできないのです。3つには「必ず終わりが来る」そして4つには「その終わりはいつ来るかわからない」ということです。だれもが必ず「死」を迎えます。人間の死亡率は100パーセント、逃れることも、代わってもらうこともできないのです。しかも、人生において努力し積み上げてきたものは何の役にも立たないのです。
落盤事故で閉じ込められ、絶望や不安の中「何のために生きているのか」「死んだらどうなるのか」という人生そのものの問いが生まれ、いのちを見つめる機会になったことでしょう。
「救われる」とは、人として生まれ生きていることを慶び、今現在、生きている素晴らしさに気づくことであると言えるのではないでしょうか。まさに今、ここに至り届いている大いなる救いのはたらきに気づき、感謝する日暮らしをさせていただきましょう。いつ終えても後悔しない人生を送りたいものです。
絶対的よろこび
2010年10月
アメリカ大リーグ、マリナーズのイチロー選手が、 10年連続200安打達成まで秒読み段階となっています。そんな偉業を成し遂げようとしているイチロー選手が「誰かと競争し、比較して一位になったということよりも、自分で立てた目標に向かって、自分なりに手ごたえが得られることこそが、うれしい」と発言されました。
しかしながら私達は、自分自身の中に満足感や喜び、生きていて良かったと思えるものがないと、自分より劣って見えるものをついつい探してしまいがちです。探しても見つからない場合は、作ってでも見つけようとすることもあります。自分よりも劣っていると思われるものを見つけ、それと比べて「自分はあの人から比べたらましな方だから喜ばなければ」「あの人は気の毒で、それに比べたら私はまだ幸せな方だと思わなければ」などと、このようにしてしか満足を得られなくなってしまいます。そういう私たちの考え方が錯覚であり、比較をつくりだしてしまうのではないでしょうか。人間には長所や短所、特徴や癖など色々ありますが、人生においても自分に都合の良いこと悪いことなど色々起こります。そのような予想のできない人生ですが、お念仏のはたらきにふれたなら、不都合なことも含めて身の上に起こる全てのことに意味や価値があるということに気付かせていただくことができるのです。
阿弥陀様の無量の光明に照らされることで、人生における真実のよろこびとは相対的な喜びではなく、絶対的なよろこびであったと気づかせていただくことが出来たなら、自分自身の人生や生活の中からよろこびや安心というものを見出すことができ、比較することは全く必要なくなり、意味のないこととなります。
日々、大切でかけがえのない人生が、私自身の「今」と「ここ」にあるのだと開かれていくよろこびの道を、お念仏と共に歩ませていただきましょう。
お寺で聴こう 南无阿弥陀仏
2010年9月
浄土真宗の教えは、お聴聞に始まり、お聴聞に尽きると言われています。
南无阿弥陀仏を称え、聞くと、どうして救われるのか。また救われるということはどういうことか、そうしたことを聞くことを聴聞と言います。これは、日ごろの講演会や、テレビ等では聞くことのできない話です。世間の常識では、よい学校よい就職、高収入こそが、幸せの基本であり、人生はすべてそれで決まるように思い込んでいます。経済的に豊かであり、しかも健康で、それさえあれば人間は幸せであると考えています。ですが健康で経済的に豊かであればすべてが幸せとは決して言いきれません。どんなに努力し苦労しても、自分の期待どおりには行かないことが現実です。人は誰でも老いて病気になり死んでいくという、根本的な問題を抱えています。
南无阿弥陀仏を聞くということは、大変な病気にかかっていても、経済的に豊かでなく、地位や名誉がなくても、人間は豊かな生活ができるということを教えていただくことです。幸せとは何か、何が喜びか、救われるとはどういうことか、仏様の働きとは何か、そうしたことが味わえると、特別なことが手に入らなくても、いまここで、このままでもっともっと喜べることがいかに多いのか、自分ほど幸せな人間はいないと気づかせていただき、積極的に喜びを持って生きて行く力を与えられるのです。お念仏の中で生きるとは、ありのままを受け止め生きる力を与えられ智慧をいただく事です。南无阿弥陀仏で、この私ほど幸せな人間はいないと味わうことが出来る生活をいただけるのです。
当寺では1日〜3日報恩講、23日、24日とお彼岸の法要が勤まります。仏さまのお話を聴聞しにお寺に来てみてはいかがでしょうか。
お浄土の教えを聞いて、よろこび一杯の人生を送りましょう
2010年8月
お参りをして、仏さまの教えを聞くということは、この世に生まれて本当に良かったと慶び、たとえ短くても悔いのない人生を生き抜いていく、お浄土への道を歩ませていただくものです。
人は年をとると、いろいろなものを失っていきます。視力や体力を奪われ、重い病気になったり、身近で大切な人を失うなど、深い悲しみの中から、大きな命のはたらきに出遇うことがあります。自分の心臓や肺の活動を私自身がコントロールしているわけではありません。大きな命のはたらきが、私を生かしているのです。その仏さまのはたらきを聞くことで、生きていると思っていたことが、生かされているということに気づく、あたりまえと思っていたことが、おかげさまであったと慶ばせていただけるようになるのです。年老いて失っていくことは、さみしいことですが、年を重ねたからこそ得させていただくことは大きな慶びとなります。
お盆には、亡き人をご縁に、今あるこの命に感謝し、仏さまの命のはたらきを聞かせていただく。疑い深い私たちではありますが、聞き続けることで、いつか仏さまのはたらきが自分に届いていることに気づくときがやってまいります。聞き続けることをやめてしまっては、もったいないのではないでしょうか。
そして、いつでも仏さまの命のはたらきの中に抱かれているのだと受け入れることができたときには、人生の目的と意味が与えられ、「生まれてきてよかった、死んでも悔いはない」という、のびのびとした余裕ある、迷いのない、よろこび一杯の人生を恵まれるのです。手を合わせるご縁を大切にいたしましょう。
頭が下がる
2010年7月
今日ほど、誰しも自分の生き方考え方こそが正しいと思い込み、人生において大切なものが見失われてきている事は、なかったのではないでしょうか。人は誰しも自分が一番可愛いものです。いざとなったら、何をしでかすのかわからない、自己中心的な生物です。日常生活では下げたくない頭を下げながら、毎日を送っています。しかし、自分の得にならないと思うと頭を下げることをやめてしまい、自分の欲深さは無いものとして、他人の欲深さを責めてしまいがちです。
私たちには思い通りにしたいという気持ちが必ずあり、そうであるから意見があわず口論になったりもします。しかし、おのずと自己中心的な考えを認めた所に頭がさがり、そこから新たな会話が生まれたりもするのです。自分の不完全さを自覚することはとても大切です。
親鸞聖人は「もともと私たちは、仏さまの教えを聞いたり、仏さまやお浄土を思い、両手を合わせ、頭(こうべ)を垂(た)れて、お念仏申そうとする心さえなく、そんなご縁さえなかったのだ」とおっしゃいました。完全なる阿弥陀様の慈悲のお心にふれ、今まで頭が下がることのなかった自己中心的な私が、自分の不完全さを自覚させていただき、その御恩に、自然と合わすはずのなかった両手を合わせ、下げるはずのなかった頭が下がり、お念仏申すはずのなかった私の口にお念仏が出て下さるのです。今、私の口にお念仏が出て下さっている。それはまさに私自身が仏さまのはたらきの、まっただ中にいることなのです。
お頭が下がり、感謝のお念仏を申させて頂く中に、人生を精一杯、強く明るく生き抜くことができるのではないでしょうか。
恵信尼さま
2010年6月
今在る仏教教団の中で浄土真宗は、特に女性の存在を重視してきた教団といえます。
僧侶の妻帯を認め、お寺の奥さんは『坊守さん』と呼ばれ、お檀家さんに親しまれ、住職と共にお寺の顔となり伝道活動に励まれています。最近では坊守さんが中心となって各寺婦人会活動や様々な行事を行うお寺が増えてきました。
京都女子大の籠谷(かごたに)真智子教授はある新聞に「坊守さん。なんと優しい響きだろう。坊守さんとつぶやくとき、私は穏やかな母の手のぬくもりを感ずる」と、子供の頃の思い出と重ねて述べておられますその坊守となられた最初の方が親鸞聖人と結婚された恵信尼さまだったと言ってもいいでしょう。親鸞聖人と出遇われた恵信尼さまの実家は越後にあったとされ、親鸞聖人と共に関東、京都に四十年余り念仏者の妻として、さらには単身で越後の地に帰り田畑の耕作の指図をしたり、孫達の世話に明け暮れその優しさとたくましい姿を世に残し一生を終えたとされています。
その恵信尼さまのお姿は、福住寺の本堂に絵像が掛けられていて見ることができます。
六月には当寺で営まれる婦人会報恩講、親鸞聖人降誕会(聖人の誕生をお祝いする法要)が勤まります。どうぞ皆様も恵信尼さまのお姿を見て、なつかしいぬくもりを感じながら、仏さまに手を合わせてみてはいかがでしょうか。
ナムアミダブツ ナムアミダブツ
2010年5月
すべてのものの いのちをいただき 皆様にお世話になって
ここまで いかされてまいりました 有り難う御座居ます(長尾タツ子)
平成22年4月1日、福住寺第5世坊守、長尾タツ子様が行年95才で往生の素懐を遂げられました。葬儀には、たくさんのご参詣、ご焼香をいただき、加えて、過分なるご香料、ご供花、ご供物までもいただき、厚くお礼申し上げます。
振り返りますと、お寺に嫁いで70年余り、門信徒の皆様と共にお念仏の繁盛に尽力され、法務に励み、心なごます花を愛した坊守でありましたが、平成20年の元旦に突然倒れ、救急車で病院へ運ばれました。そして、お医者さんから「余命10ヶ月」を宣告され、以来、病院にお世話になる回数が増えていきました。
同じ頃、開教120年記念事業の庫裡改築や永代納骨廟の建築を喜び、余命の期間を過ぎて、これらの完成をはっきり見届けることができて、安堵したことでしょう。
体が痛く辛そうにしている時でも、愚痴も言わず、我慢強く耐え、大変な病気を抱えているにも関わらず、人にはやさしい言葉をかけて下さり、生きるよろこびを感じさせる坊守でありました。たくさんの方に囲まれ支えられ、お念仏と共に生き抜かれた坊守は、本当に幸な人生を、よろこびの多い人生をおくることができたのではないでしょうか。
今後とも、福住寺の法灯を受け継いでいき、お念仏の相続に皆様方のお力添えをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
お誕生日
2010年4月
4月1日は宗祖親鸞聖人のお誕生日です(本願寺派では新暦の5月21日にお祝いいたします)。7日は宗祖の師、法然上人のお誕生日で、8日はお釈迦さまのお誕生日、花祭りです。ですから4月は私たち浄土真宗をよりどころとするものにとって、たいへん意味のある月とも言えます。
誕生日といえば、人は三度誕生してはじめて一人前になると言った方がいます。まず最初に、赤ん坊としてこの世に生まれ、二度目は思春期中に自己認識が生まれ、第二の誕生をむかえます。これで終わりではなく、最後によりどころとなる宗教と出遇うことができて初めて一人前になると言われるのです。しかし、多くの人は二度目の誕生までは迎えるのですが、よりどころとなる宗教と出遇うことが出来ずに、迷いの人生を不安のなかで過ごしている人々が現代に溢れているのではないでしょうか。では、宗教に出遇うということは、どういうことでしょう。宗教に出遇うことで、今まで気付けなかったことに気付き、当たり前だと思っていたことがそうではなくなってくる。真実の光に照らされることで、自分自身をあらためて見つめ直すことができ、新たな人生を歩むことができるのです。日々の生活の中で、苦悩や絶望のふちにたたされたとしても、たしかなよろこびと希望を感じさせてもらえるものが宗教であり、私達にとってそれは、お念仏の教えです。お念仏の教えに出遇えたお蔭で、いつ、どこで、どんなことがあったとしても、生きがいあるよろこび多い人生を歩ませていただくことができ、間違いなくお浄土へ往生させていただくのです。
往生とは、私たち浄土真宗をよりどころとするものにとって往死(死に往く)ではありません。お念仏と出遇い、人として一人前とならせていただき、今、この現世で、必ずお浄土へ生まれ往くというよろこびをいただくことなのです。
お念仏に出遇うことができ、「お蔭さまでよろこび多い日暮を過ごさせていただいています」と自分の誕生日を心からよろこべる人生でありたいものです。
一期一会
2010年3月
先日、学生時代の友人と久しぶりに会い一緒に食事をした時のことです。
懐かしくていろいろな話をしながら食事を楽しんでいたのですが、ふと、楽しいのだけれど、学生時代にその友人と遊んでいた時の楽しさとは少し違うなと思いました。同じ人と同じことをしているのになぜと思いましたが、考えてみれば当然のことで、お互いに昔とは違っていたのです。これは悪い意味で言っているのではありません。人に限らずこの世の中のものは、常に変化し続けていると言うことです。
たとえば桜の花、毎年同じようにきれいな花を見せてくれますが、これも同じではありません。年々木は成長し大きくなる、その年の気侯によって花の多い年少ない年があり、長持ちする年とすぐに散ってしまう年がある。花の色も微妙に違っている。つまりその年の桜はその年にしか見ることのできない一度きりの桜だということです。だから私たちは一度きりの桜を見ることができることを、毎年もっと喜ぶべきではないでしょうか。
人との出会いも同じように、また来年会える、また来月会える、また明日会えると同じ出会いがあるように思っていますが、同じ出会いは二度とありません。たとえ同じ人と会ったとしても前あったときと比べてお互いどこか少しは変わっているはずです。それにこの世は無常です、また会えると思っていても、また会える保証はないのです。
『一期一会 今この時 めぐり遇いの大切さ』
小さな縁が、やがて大きな縁を呼ぶかもしれません。今いただいているこの尊いご縁を大切にいたしましょう。
死んだらどこへ
2010年2月
この世の縁の尽きるとき 如来の浄土に生まれては
さとりの智慧をいただいて あらゆるいのちを救います
「拝読 浄土真宗のみ教え」より転載
6千人以上の人が犠牲になった阪神淡路大震災から15年がたちました。毎年各地で犠牲者を追悼する式典が開かれ、その日を迎えるたびに、悲しみを新たにされている様子が映し出されます。
人生の中で、苦しみ悩みの深い状況にあうと、「何のために生きているのか。死んだらどうなってしまうのか」などという、大きな問いが生まれます。重い病気や交通事故、地震や火災などの災害、または心の病などによって自らのいのちを絶つなど、生きていること自体が死へ向かって歩んでいるということでもあります。人間の死亡率は100%です。決して逃れることはできません。
身近で大切な方が亡くなると、手を合わせるご縁や死後の世界を考える機会を与えて下さいます。亡き人の人生を無駄にすることなく仏道を歩み、お念仏申させていただくことが、ご恩報謝となるのではないでしょうか。
浄土真宗は、この世の縁の尽き、いのち終えたならば、阿弥陀如来の本願のはたらきによって、お浄土へ往生させていただき仏さまに成らせていただく。そしてこの世に還って迷える私たちを導き、あらゆるいのちを救う教えです。
親鸞聖人は晩年、門弟に書かれたお手紙の中に「私は年をとりすぎてしまいました。あなたより先に死んでしまうでありましょうから、お浄土でかならずかならずお待ちしておりますよ。」と述べられております。このお言葉によって、人としてのやさしさや思いやりを感じさせ、お浄土を人生の目的とされ、力強く生き抜かれたお姿が偲ばれます。
愛する人を亡くし深い悲しみの中にいる人にとりまして、「再び会える世界がある」ということは、本当に有難いことでございます。
死んだら終わり、おしまいだという考え方は、孤独で寂しい暗い人生で終わってしまいます。仏さまのお心をお聞かせいただき、「いつでも一緒の仏さま」に抱かれていることを素直に慶べたならば、お浄土という往く先の定まる安心した人生、悔いのない明るい人生に恵まれるのです。
めでたい
2010年1月
「一年の計は元旦にあり」 といいますが、浄土真宗の門徒にとって元旦は、真実に生かされる身の幸せを喜び、この一年をお念仏のみ教えをよりどころに送る決意を新たにする日です。
私達は、新年になるとお互いに「おめでとう」ということばを交わします。 「めでたい」 という文字は一般的に「芽出たい」と書くことが多いようですが、お互いに今年こそ芽の出る人生を持ちたいという願望が、この文字の上からも感じとることができます。草木は、春になって土から芽が吹き出るまでに冷たく厳しい冬を経験します。やがて芽が出て花を開くに至るまでには、風雨にたたかれ灼熱の太陽にさらされるなど、その成長過程は大変なものです。このように私達も、苦悩や悲しみをいかに受けようとも、確かな芽の出る人生を持ちたいという思いが「おめでとう」という新年の挨拶になったのではないでしょうか。
仏教で人生は「一切皆苦」と示され、生きるということ自体が苦であると説かれています。私達の存在そのものが苦から逃れることができません。苦が越えられる道が得られたとき、人は確かに生き得たということになるのではないでしょうか。
良寛さんの詩の一節に「蝶来るとき花開き、花開くとき蝶来る」 とありますが、素直な思いで向き合う時、阿弥陀様と私は、常に一緒であります。阿弥陀様は、苦悩する私がいるからこそ必ず救うと願いを起されたのです。私自身は阿弥陀様と共にいるからこそ強く生きる事が出来、その人生がめでたいのではないでしょうか。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|