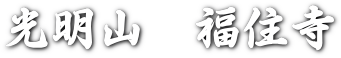月報「なむ」
2009年
〜あらゆるいのちをもらさず救いたい〜それが如来の願い
2009年12月
先日、久しぶりに実家に帰省し隣町から友人夫婦が子供を連れて私に会いに来てくれました。友人の息子はもう小学二年になっていて、子供の成長に驚かせられながらもついつい昔話に花がさき、当然のように友人の子供は退屈そうにしていました。すると子供は退屈しのぎに「お菓子を買いに行ってくる」と親に言い出しました。私の実家からは、わずか30メートルほど行ったところに商店があるのですが親子供に慣れてはいない町なので心配そうに「大丈夫?一人でいけるの?」と声をかけたところ子供は聞く耳ももたず小走りに出て行ってしまいました。お母さんはやはり心配になり子供の後を追って行きました。親としては当然の行動にみえますが、子供の方は『ついてこなくても大丈夫だよ!』というような顔をしながら、退屈な時間から逃れるように出て行きましたが、親の方はやはり子供のことが心配だったのです。阿弥陀様もこの私という子が、心配でならないのです。親鸞聖人は、ご和讃の中でこのようにうたわれています。
十方微塵世界の
念仏の衆生をみそなはし
摂取してすてざれば
阿弥陀となづけたてまつる
と讃嘆されておられます。「摂取してすてざれば」とは、「一度とらえたものを永遠に捨てない、逃げるものを追いかけてつかまえる」ということであります。阿弥陀さまは、念仏の衆生を決して捨てない、逃さない如来さまであるのです。
念仏のみ教えに遇いながらも身勝手なことばかりしているこの私は、阿弥陀さまという親さまから逃れようとしている子なのでありましょう。このような者を、逃がすものかと、とらえてみなもらさずにお捨てになられないのが、阿弥陀さまの御慈悲であり願いでもあるのです。
他をさす指はいくつもあるのに 私をさし見つめ問う指はない
2009年11月
私たちは、他人に親切なことをして、思い通りに物事が進むと自分の手柄として喜びます。それに対して、相手が礼を言わず、思い通りにならなければ「あの人が悪い、この人が悪い」と言って、他人を指差し、批判し、腹を立てるのです。他人のことはよく見えるのに、自分自身に指をさし、我が身を見つめ、私自身を問う指は、持ち合わせていないのでしょうか。
人生には、愛する人との突然の死別、老いや病気、あるいは信頼していた人との関係崩壊など、様々なことが起こります。私たちは幸せな人生を望みますが、思い通りにはいかない無常の風は常に吹き荒れ、時には、絶望と深い悲しみの中に放り出されることがあります。大切なものを失って初めて自分の力の無さに気づいていくのです。
真実の教えに出遇うと、真実ではない自分自身の本当の姿を知らされます。本当の姿とは、煩悩にまみれた私であるということです。欲望と怒りと愚痴で毎日を過ごし、善いことをすればいつまでもそれを手柄として持ち続け、恨みやねたむ心を、自分は正しいと主張しながら生きている。そうした自己の姿に気づかせていただくならば、善人などとは言えないのではないでしょうか。
親鸞聖人は、歎異抄第2条に『いづれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし』(注釈版聖典833頁)と示され、「どのような行も満足に修めることができない。悟りへ近づくどころか、迷いが深まるばかり。煩悩まみれの私は、地獄行きがちょうどいい」と、自らの姿を徹底的に見つめられ、権力や財産などを求めず、ひたすら、人びとが南無阿弥陀仏のお念仏に生かされてゆく道を切り開かれ慶ばれました。
あてにしていた自分自身があてにならない、愚かで恥ずかしい私であったと気づかせて下さる、お念仏のはたらきに、導かれる人生を歩んでほしいと、おすすめ下さるのです。
明日こそ明日こそ 弁解しながら過ぎていく日々
2009年10月
薄着の夏にメタボ気味の身体が気になり、ダイエットを試みようと思いながら「明日こそ、明日こそ」と夏が過ぎ、食欲の秋を迎えてしまいました。私たちは過去を悔やみ、明日を夢見て、肝心の「今」を見失いがちです。以前、ある人が春の高校野球大会の開会式を見て面白い事を言ったそうです。歌手ウルフルズが唄う入場行進曲「明日があるさ」が流れたとき「高校野球に明日は無いんだよ!」と叫んだそうです。確かにプロ野球なら明日というのも考えられますが、高校野球は負ければそれでおしまいです。私たちの人生も「明日があるさ」と唄いがちですが、明日に保証などありません。本願寺第八世の蓮如上人は「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」とお示しくださり「仏法には明日と申すことあるまじく候ふ」と諭されました。私たちは常に「今」を生きています。昨日は過ぎ行き明日は来るのかもわかりません。確かなのは、「今」この一瞬だけなのです。その一番大切な「今」をどう生きればよいのかを教えて下さるのが仏法です。「明日があるさ」と生きるより、二度と戻らない「今」を大切に生きることが必要なのではないでしょうか。お通夜やお葬式で「昨日会ったときはあんなに元気だったのに」という声を耳にするたびに、あらためて世の無常ということを感じさせられます。この無常という言葉に、多くの人はもの悲しく寂しいイメージを持っているのではないでしょうか。
無常とは生死だけを指すものではありません。この世に存在する物、出来事すべて、形や本質は常に変化するものであり一瞬たりとも同じ状態を保つことはできないというのが無常です。人の生死はもちろん、私たちの日常生活そのものが無常であり「今」というときが永遠に続くことはありません。「みなさんに明日が来ることは奇跡です、それを知ってるだけで日常は幸せなことだらけで溢れています」この言葉は『余命1ヶ月の花嫁』という映画のモデルとなり、乳ガンで24歳にして亡くなられた長島千恵さんの言葉です。彼女は「生きていることの幸せを知ってほしい」という願いを込めてこのメッセージを残されました。私たちは、毎日を何気なく過ごしていると、今ある現状がついついあたりまえだと捉えがちです。食事をし、話し、泣き笑い、喧嘩のできる家族がいて、夜になると眠り、朝が来たら目ざめること。そしていま生きているということ。
有難い「いのち」をいただいた私たちですが、欲深く自己中心的で、そんな自分自身の姿にも気付くことができず"当たり前"を"有難い"といただけない私たちの姿は、無明の闇の彷徨い人になってはいないでしょうか。阿弥陀様の智慧の光は彷徨う私たちを照らしだし、お念仏となって至りとどいてくださっています。皆様と共々にお念仏申させていただき、"当たり前"ではなく"有難い"と感謝させていただく人生を歩みたいものです。
あらゆるいのちの 犠牲によって 私は生かされている
2009年9月
だんだんと夏の日差しも薄れ、これから実りの秋をむかえようとしています。私たちの住む北海道は全国的にみても、食料自給率が約200%と自然の恩恵を大いにうけて生活をしています。生産者の意識が高いなか、一方で消費する(食べる)私たちの考えはどうでしょう。近年の相次ぐ天候の変化によって作物の不作であったり、家畜などの伝染病によって食物の供給が低下したとしても、今の時代は技術の発達、諸外国からの輸入などで対応することができ、食べ物が全く手に入らないということは無くなったのではないでしょうか。
私たちは、『生きる』という為に毎日食事をしなければなりません。米、肉、野菜、果物など色々なものを食べますが、それは、それらの『いのち』をいただいて、自分のいのちを養っているのです。
私たちは当たり前のように食事ができる環境に生きて、大切なことを忘れてしまいがちです。
私たちは生き物たちの『いのちの布施』を頂いて生かさせていただいています。「いただきます」、「ごちそうさま」はその感謝の表れです。感謝の心を養う大切な役割を果たしています。生産者の方、それを調理してくれた方はもちろんのこと、なによりも料理の材料となってくれたものへの「ありがとう」の感謝の気持ちから合掌し「いただきます」、「ごちそうさま」と言うのです。
いつのまにか食べることも、生きることさえも当たり前になってしまった私たちです。ですが、私たちは日々『いのちのお布施』を頂きながら生かさせていただいているのです。
お盆のご縁
2009年8月
[いのちの根]
なみだをこらえて 悲しみにたえるとき
ぐちをいわずに 苦しみにたえるとき
いいわけをしないでだまって 批判にたえるとき
怒りをおさえて 屈辱にたえるとき
あなたの眼のいろがふかくなり
いのちの根がふかくなる (相田みつを)
お盆には、あわただしい毎日を送る中で、多くの方が実家に帰省し、両親や兄弟親族などと顔を合わせます。しかし、一緒に育った兄弟も今では離れて暮らし、会うこともままならない。体が不自由になって、会いたい人に会えないもどかしさもあるのではないでしょうか。また、無常の風は、ある日突然やってきます。身近で大切な方を亡くされると、涙をこらえて愚痴を言わずに、悲しみ苦しみを抱えながら、苦悩の多い人生を歩んでいかねばなりません。
久しぶりの再会にはうれしいこともありますが、時には、年老いた両親からの愚痴や批判も聞かねばなりません。言い訳をしないで、怒りを抑えて屈辱に耐えることもあるでしょう。「この世であと何回会えるだろうか」そう考えると、今、会える時間を大切にするのではないでしょうか。
お盆には、両親はじめ多くのご先祖様のご恩を思い、今ある身の幸せに感謝し、お念仏を申させていただくものです。大切な方を亡くされ、目からあふれ出る涙のように、私の口からあふれ出るお念仏を通して、そっと寄り添う亡き人のお心が私の耳に聞こえてまいります。いつでもどこでも、あなたと一緒だよ、絶対に見捨てないよと、苦悩の深い私の心に大きな慶びを与えて下さるのです。
阿弥陀様のはたらきが、私の心に届いて、住み着いたならば、眼の色や、いのちの根が深くなり、大きな花を咲かせることができるのではないでしょうか。今を生きる私自身が、明るく心豊かな生活を送るために、お盆のご縁を大切にしたいものです。
入院生活から学ぶ
2009年7月
元気なときには 健康の有難さを忘れ ちょっと具合が悪いと 死の幻影におびえ
思い通りにならないと 世界一の不幸せものだと思い込み
思いがかなうと 有頂天になる私 でも心静かな時
ふと こんな私が いつでも み仏の掌の上にいるんだなあと思ったりもしています
人生の中には様々な出来事が起こり、自分の思い通りにはいかないことが多いものです。突然の病気や事故などが原因で体の調子が悪くなって病院にお世話になる方もいるでしょう。また、年を重ねるごとに体の具合が悪くなり、薬を欠かすことのできない生活を送っている人もいます。
皆様は病院へ入院した経験はあるでしょうか。入院生活は、あくせくした世の中にあって、ゆったりとした時間の流れるものです。頼りになるお医者さんや、看護師さんに囲まれ、療養しながら、自分を見つめ、いのちを見つめ、病状によっては「死」という恐怖におびえたりするものなのしょう。
大きな病院であれば、たくさんの患者さんがおられます。そんな時、自分と他人を比較して、自分の病状よりも、重病を抱える方を見ると、大変だと思う半面、自分では気づかない心の奥底には「自分の事でなくてよかった」という感情が存在するのではないでしょうか。たとえば、自分でご飯を食べることも、歩いてトイレにいくこともできない、そのような人を見て、できる自分に、幸せを感じたりすることはないでしょうか。病院内で生活し、いのち終えていく子供たちもいるのです。かわいそうなことだと思いつつ、自分のことでなくてよかったと、他人の苦しみ痛みを自分のこととして受け取ることのできない、そんな自己中心的な心から逃れられない私。そういう愚かな私を見抜いて、阿弥陀様は心配して下さるのです。
どんなに立派なお医者さんが私の面倒をみてくれたとしても、治療には限界があります。お医者さんに見離された、いのちはどうなってしまうのでしょうか。いつでもどこまででもあなたと一緒だよと、人生ギリギリのところでは阿弥陀様のはたらきによって、愚かな心を抱えたままの私を、他人の苦しみ痛みを我がこととして受け取ることのできる仏さまとならせていただくのです。
入院生活の中では、つらく苦しい時があるのはお互い様で、お互いが自分のしんどい気持ちを安心してゆだねることができる、相手のつらさをそっと気づかい合える、そんな人間関係を育て、普通に生きることが当たり前になっている私たちに、普通に生活することが、どれほど有難いことであるのか気づかせてくださるものではないでしょうか。毎日が うれしい日、素晴らしい日、有難い日なのです。
降誕会
2009年6月
今から836年前、承安3年(1173)旧暦の4月1日、新暦の5月21日に、浄土真宗の宗祖、親鸞聖人がご誕生になりました。このご誕生をお祝いする行事が降誕会であります。親鸞聖人は、九歳で出家得度をされ、比叡山での二十年間の堂僧としての修行の時代をへて、法然上人との出遇い、越後への流罪、関東でのご教化そして京都へ帰り数多くの著述を残され人々にお念仏のみ教えを伝えていかれました。今日、私達は、その親鸞聖人の九十年のご生涯と数多くの著述のおかげで親鸞聖人の生き方、浄土真宗のみ教えをいただくことができるのです。
それは親鸞聖人がこの世にご誕生になったからのご縁であります。このご縁がなかったなら、お念仏をいただき、阿弥陀様に手を合わすこともなかったかもしれません。親鸞聖人ご自信も、吉水の草庵で、師である法然上人と出遇われたご縁を「本師源空いまさずは、このたびむなしくすぎなまし」(本当の師である源空(法然)聖人がこの世においでにならなかったなら、私の人生は空しく過ぎてしまったことでしょう)と『高僧和讃』に著され喜ばれました。そして、同じく『高僧和讃』のなかで「本願力にあひぬれば、むなしくすぐるひとぞなき」(阿弥陀様のお念仏のはたらきに出遇へたなら、むなしく迷いの人生をおくることはありません)という人生を恵まれた喜びでもありました。親鸞聖人から長い長い年月をへて、多くの人々の命のつながりの中、お念仏の声は間違いなく私へと伝えられ、そして次の世代へも伝えられていく喜びに出会えたなら、人生においてどんな困難や試練に遭遇したとしても、生きがいある、喜び多い人生を歩まさせていただき、やがてはお浄土に往生させていただくのです。「お蔭さまで喜び多い毎日をおくらせていただいています」と降誕会とともに、自分の誕生日も心から喜べる人生でありたいものです。
美しい花
2009年5月
北海道にもようやく遅い春を迎えました。長い冬を経て草花もまた私達に美しい姿を披露してくれようとしています。私たちの目には美しく咲いている花の姿しか見えていません。しかし、よく考えてみるとその美しい花を咲かせるためには地中に伸びた多くの根が水分や栄養分を吸収し、そのお蔭で茎も葉も成長しやがて花を咲かすことが出来るのです。それに気づいていない、なかなか気づけないのが私たちなのではないでしょうか。
そのように考えてみますとこの私も、今ここにこうしていることは当たり前であると思っていますが、よくよく考えるとそうではないと気づかされます。
親をはじめ、家族や友人の存在、動物や植物、水や空気などありとあらゆるものの力によってここに生きているのです。それは、決して自分一人の力で生きてはいないという自覚ではないでしょうか。お念仏を味わえば、このような普段の生活ではなかなか気づくことのできないことに少しずつ気づかせていただき、感じられるかもしれません。
南无阿弥陀仏は、私が気づかずにいる大きな力を知らせていただき、気づかせていただき、喜びと生きがいと豊かさを与えてくださるものです。
南无阿弥陀仏の働きの一つでも、二つでも味わうことの出来る生活は、何にも増して幸せな人生だと思います。気づいてみれば私ほど幸せなものはないのだと喜べるのです。気づくか気づかないかで、その一生は大きく違うのだと思います。
見えない根たちの
ねがいがこもって
あのような
美しい花となるのだ(坂村真民)
誰のため 何のための お参りですか
2009年4月
昨年よりアメリカで経済不況がおこり、その影響は日本の大手企業にも波及しております。賃金カットや大幅な雇用の削減など、私達の生活全体に不安が増大しております。また、現代では、他人とあまり関わりたくないと思う人が多く、近所に住んでいながら、どのような人が住んでいるのか知らないという方もいて、人間関係の難しい、ストレスの多い社会と言われております。さらに、核家族化や少子化が進み、家族大勢で暮らす家庭が少なくなってきました。祖父母と一緒に暮らす家庭が少なくなった今日では、年老いていく苦しみ、悩み、寂しさ、そして誰にでもやってくる死という現実に触れることもないまま育つ子供達が増えています。そうした中いのちに対する優しさや思いやりというものが少なくなり、生活環境など様々な要因があると思いますが、いのちを簡単に奪ってしまう事件など自分中心の考えで引き起こされる犯罪などが多発しております。
私達は、なかなか自分では、自分の姿に気がつきません。他の人から指摘されるまで、自分の姿を知ることができないことが多いものです。そして他人の欠点ばかりが目につき、人の悪口など言って、お互いに傷つけあっているのです。そうした自分のみにくい姿はとても見えるものではありません。それどころか迷っていることにさえ気付かないのです。欠点だらけの自分を見るということは不愉快なことですし、たとえ親しい人から指摘されたとしても受け入れにくいものです。このような心が争いや犯罪をおこす原因になっているのです。誰もが争いや犯罪を起こしかねない心を抱えているのです。
誰のため何のためのお参りでしょうか。亡くなった人の為に、死んだ人があの世で迷わず、安らかに眠らせる為にするものであり、迷う亡き人に向けられたお参り、と思われている方が多いのではないでしょうか。
阿弥陀様のはたらきが誰の為に向けられているのか、それは苦しみ悩みの多い迷いの人生を送り、いつ争いや犯罪を起こしかねない心を抱えた「私」の為であるということを聞かせていただくものであります。私達は限りあるいのちを抱えている、だからこそ死の苦しみが越えられる道を聞くことなくして私が本当に生きられる道はないのです。求める前に与えられている阿弥陀様の願いと、はたらきに支えられていることに気付かせていただき、安心して死ぬことのできる道を教えてくれるものであり、つらく悲しい、苦しいことがあっても、その事実、現実をしっかりと見つめ、明るく正しく力強く生き抜いていく力をいただく為のお参りといえるのではないでしょうか。
実るほど、頭(こうべ)を垂るる稲穂かな
2009年3月
今日、人間中心の考えがいよいよ強まり、利益の追求が拡大され世界的な格差を生み、様々な生き物の存続の危機が危ぶまれています。そして急激な社会の変化に伴い、いのちに対する考え方の根本が揺らいでいるように思われます。私たちは世の中の流に惑わされ自ら迷いの人生を歩んでいるのではないでしょうか。私たち人間の人生とはあらゆるものの価値を追求し続けることであると言っても過言ではありません。金銭に価値を見出す人、地位や名誉に価値を見出す人、あるいは精神的肉体的な充実に価値を見出す人など様々です。私たちは各々の価値を追求するために毎日働き、一つ一つ手に入れていくのです。しかし、その価値を見出した存在自体に価値があるわけではないのです。金銭や地位や名誉、様々な物事の価値を判断するのは人間の「知恵」です。「知恵」とは、人間自身が未知なるものを学び、覚え、理解することです。しかし世の中には 「知恵」で価値を判断できるものばかりが存在しているわけではありません。例えば、一輪の活けた枯花があるとします。それを「知恵」で判断すると価値を見出すことは難しいかもしれませんが、その一輪の花が咲くためには、種がなくては咲きません。そしてその前の種、光や水、様々なご縁が重なりあわなければ咲くことはできないのです。永い永い、いのちの関わり遇いがなければ、その花の存在そのものが無かったことを知らされた時、そこにはいのちの根本的な深い意味があることに気付かされるのです。そんな人間の「知恵」で価値を見出すことのできないものに、深い意味を感じさせるはたらきを「智慧」といいます。「智慧」とは人間の「知恵」では価値を見出すことのできないものを、尊い慈悲の光で私たちのこころの闇を照らし出し、目覚めさせるはたらきをいいます。そして「智慧」に出遇へば出遇うほど自分の愚かさに気付かされ実るほど、頭(こうべ)を垂るる稲穂かな」ということわざのように、有り難さで頭が下がるばかりです。しかし、人間の「知恵」はつけばつくほど賢くなり、偉くなるので頭が上がるばかりです。そして、素直に聞く耳をなくし謙虚さがなくなり、自分一人の力で生きているのだと思い上がり自分を見失いがちです。鏡を見なければ自分の顔を見ることができないように、人間は阿弥陀様の教えという鏡に「智慧」の光で照らし出されることなくして、自分というものの現実に目覚めようのない存在なのです。「知恵」のはたらきはどんなに優れてい、自分自身の間違いや欠点に気付く作用はありません。そのことをおしえてくださるのが「智慧」のはたらきなのです。現代社会で人間は、知識や常識的に賢くなることに積極的で 、「知恵」をつけた人が増えてきましたが、そのお陰で忙しい毎日に追われ、目先のことにとらわれて人生において大切なことを見失い、かえって人間の心が荒廃してきたように感じられます。親鸞聖人によって開かれた浄土真宗は、あらゆる生きとし生けるものが南無阿弥陀仏のお念仏のはたらきによって仏となり、この世の迷えるものを救うためにはたらくという教えです。お念仏の道は、お陰様と生かされる道であり、有り難うと生き抜く道であります。お念仏に聞きましょう、お念仏を申しましょう、そして阿弥陀様の尊い「智慧」の光に照らされながら、いのちあるものが敬い支えあうこころゆたかな人生を、強く明るく生き抜いてまいりましょう。
私達の合い言葉は南無阿弥陀仏
2009年2月
もうすっかりと口々に交わす言葉も「今朝も冷えますねぇ」などとお馴染みの挨拶を交わす季節になりました。私達は知り合いでも他人でもまず一言目には挨拶を交わし距離を縮め、親交を深めていきます。挨拶や会話も様々で、出会いの挨拶、別れの言葉など、場面、状況に用いるときや、朝、夕など時間や季節によっても言葉が異なります。そう考えると実に数え切れない程の言葉や身振りでお互いにコミュニケーションをとって日々生活していかなければなりません。
しかしながら仏様の前に居るときはどうでしょう?お仏壇を自宅に迎えたとき、お仏飯をお供えするとき、またお寺や自宅でのお参りのときに、時間、季節に関わりなく口から 発してくるのは南無阿弥陀仏というお念仏ではなかったでしょうか。この六文字は私達、浄土真宗のみ教えをいただく者同士の仏様へのご挨拶のお言葉でもあり、有り難いお言葉なのです。南無阿弥陀仏とお念仏を喜び称えれば阿弥陀様の働きによって私達を疑いなく救ってくださるのです。
仕方のない事ですが普段の生活や会話の中で誤解を招くことがあります。お念仏を称え喜ぶことは何の誤解も生じません。皆様も仏様とお話をして心を通わせる時間を増やしてみてはどうでしょう。思い起こせば仏様に出遇うご縁をいただいた時も、大切な人が亡くなってしまった時も南無阿弥陀仏と称え、大切なことに気付かせていただいたのではないでしょうか。
気づかせていただく人生
2009年1月
昔は、人生50年といい、今日では80年とも90年とも言われるような時代になりました。平均寿命の延びた現在では「死んだらおしまい、終わりだ」という考え方や「私はまだ生きられる、まだまだ大丈夫だ」という油断が人生をむなしくさせ、どうでもいいことに、あくせくしている人が多いようです。これらの人生は、孤独でむなしく寂しい人生と言えるのではないでしょうか。
世界的な経済不況が起こり、その影響は日本の大手企業にも波及しております。賃金カットやリストラなど大規模な雇用の削減は、日々の生活に大きな影響を与えております。
今、私達は心静かに自分を見つめ、充実した豊かな人生をおくるために、何をどうすれば良いのか考てみる必要があるのではないでしょうか。
今まで積み重ねてきた人生の苦労が、自分自身をどう育てたのか考え振り返った時、むなしさを感じたならば、それをどのように解決すれば良いのでしょうか。
親鸞聖人は高僧和讃に『本願力にあひぬれば、むなしくすぐる人ぞなき』とうたわれ、阿弥陀様の本願力に出遇ってこそ、むなしくない充実した人生が送れると示されました。
私達の都合によって作られた願いや思いはあてにならないことが多く、その通りになることは難しいですが、阿弥陀様の根本の願いは、願いだけにとどまらず、はたらきとなってその通りになるというものです。私達を必ずお導き下さり、往生させて下さるはたらきに生かされた日々の生活を送ることで、心豊かに生き抜くことのできる充実した人生、むなしくない人生に気付いていくことができるのではないでしょうか。
浄土真宗は死んでからの教えではありません。今を生きる私達に今、必要なお浄土であり、今をどう生きるかが問われているのです。
本年も、阿弥陀様の願いの中に包まれ、生かされ、支えられ、気付かせていただきながら、慶びの日々をお念仏と共に歩ませていただきましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|