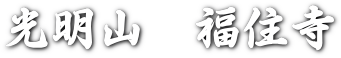月報「なむ」
2008年
ご恩、ご恩と除夜の鐘
2008年12月
「もう師走ですね」「ついこの間お正月を祝ったと思ったらもう年の瀬ですね」こんな声が聞こえてくる時期になり今年も残すところあと少しとなりました。大晦日には全国のお寺で除夜の鐘の音が聞かれます。一年の締めくくりは除夜の鐘を、ご恩(ゴーン)ご恩(ゴーン)と撞いて新しい気持ちで新年を迎えたいものです。除夜の鐘の由来は様々ですが、百八の煩悩(苦しみの元)が鐘を撞くことで一夜にして除かれると言われています。一年の罪や災いが除かれ、新年を清らかで真っ白な心で臨みたいという人々の気持ちの現れでしょうか。この一年を振り返ってみますと本当に残念な事件や事故がが多かったことに気付かされます。「こんな事も、除夜の鐘を撞いて無くなるのかな?無くなってくれればいいな」と考えたくなります。でもそう都合よくはいきません。親鸞聖人のお伝えいただいたお念仏の教えは私達の都合で仏様にお願いする教えではありません。また、災難を起こらなくしたり避ける教えでもありません。もし災難が起こったとしてもそれらに真向きとなることをお示し下さる教えです。そして、仏様の物差しをいただいて一つ一つをご縁といただきながら生き抜かせて頂く教えなのです。今年の除夜の鐘を撞くことがきっと皆様のご法縁となることでしょう。
おかげさまで、庫裡が完成いたしました!
〜12月より会堂のご利用を再開いたします〜
開教百二十年記念事業の一環であります庫裡の改築工事が皆様のご協力のもと無事完成をむかえることとなり誠に有り難うございました。尚、長期にわたり会堂のご利用を中断しご迷惑をおかけいたしましたが十二月より葬儀や法事等の会場として従来通りご利用いただけます。また、来年度には六角堂工事に着工する予定でございますので御門徒の皆様には引き続き御尽力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
浄土真宗辞典 作法編
2008年11月
【お仏壇】
「ひとつのお内仏(仏壇)に、他家の先祖を祀ってもいいのでしょうか?」という質問をうけました。皆さんはどう思われますか。
近年少子化が進み、結婚されたご両人が、それぞれの先祖をみなければならない事が多くなってきました。そのような中で、でてくるのがこのような質問のようです。私達のお内仏(仏壇)は、仏様のおられるお浄土をあらわしたものであり、日常生活の中で私達の心の依り所となる場所であります。また、お浄土とは、私の先祖はもちろんのこと、お念仏をいただかれた多くの方々が往生されたところでもあります。
この事を基本に据えて考えますと、何々家のお仏壇という考え方は、浄土真宗にはありませんし、ご両家の過去帳をひとつのお内仏に安置し両家の御先祖を偲ぶ事に何の問題もありません。むしろご縁のある形でできるだけお参りすることが望ましいことではないでしょうか?
お内仏は死者を祀る所と考え、我が家と他家と縄張りがあるように区別してご先祖を偲ぶ事の方が問題ではないでしょうか。
私達、浄土真宗のお仏壇の意味は、死者を祀る所ではなく、亡き人を偲び、私が仏様のみ教えを聞かせていただくところなのです。
【お仏飯】
「お仏飯はいつお仏壇からおろしたらよいのでしょうか?」
お仏飯とは、ご存じのように仏様にお供えするご飯の事ですが、皆さんはどの様にしてお供え、お下げになっているでしょうか。
お仏飯は、朝炊いたご飯を一番始めに仏様にお供えします。供え方は仏飯器という専用の器に蓮のつぼみの様に盛り仏様に供えます。お供えしたお仏飯は、あまり長くお供えしていると硬くなってしまいますので、家族の皆さんで朝のお参りのあと、お下げになられても良いかもしれません。最近は、パン食なども増え朝にご飯を炊かないという方もいるかもしれませんが朝に限らずご飯を炊いた時には、一番に仏様にお供えする様に心がけて頂きたいと思います 又、ご法事の時は必ずご飯を炊いてお仏飯をお供えしましょう。
お仏飯をお供えする意味は仏様に、食事の中で大切な主食となるご飯を、感謝の気持ちを込めてお供えします。そして、このお仏飯を今度は、仏様からのお恵み「お下がり」として頂きます。お供えを粗末にしてしまう事のないよう心がけたいものです。
仏さまのお育てに遇うと明るく正しく充実した人生に変わる
2008年10月
九月に入っても気温の高い日が続き、局地的な大雨、それに伴う洪水、また、地震などの自然災害、まるで地球が悲鳴をあげているように思えます。人類が長い年月、自己の権力や財産などの利益を追求してきた結果が表れてきているのでしょうか。さらに現在でも地球上のあちこちで戦争や紛争が起こっています。最近では、大相撲の力士が大麻所持で解雇され、日本相撲協会と裁判で争う事件など、人間の争い事は、とどまることを知りません。生きているだけで地球温暖化に協力し、自然を破壊し続けています。また、自己の欲望から、あらゆるいのちを犠牲にし、そのいのちを食べなければ生きていけない、自己中心の心に振り回されて生きていてはダメだと言われても、それをやめることが出来ないのが私達の本当の姿なのです。しかし、そのことに気がついた時、そこには、ちがった世界が開けてくるのです。単に自己中心の心に振り回される生き方ではなく、そういうあり方を恥ずかしいことだと受け止めて生きる中で、少しずつ仏さまのお育てにあうのです。
仏さまはすべての人間を、罪悪深重、煩悩具足の凡夫と見られ、そんな私達を憐れに思い、お浄土という人生の行く先を用意してくださいました。浄土に生まれるということは単に物質的な移動ではありません。浄土の存在は、苦しみ悩みの多い泥沼のような現実から、救い出すのではなく、もがきながら生きていく力や勇気を与えるもの。お念仏を称えることは、大いなる如来のはたらきを感じ、自分のいのちが大いなるいのちに包まれていることを感じる、それに気付くことで人生の考え方の転換を促してくれるものです。
病気になり余命を宣告され「あと何ヶ月のいのちです」とお医者さんに言われた人の残された人生、その後の人生は悔いが残らないようにと、とても充実しているように思えます。それと同じように、私達も限りあるいのちを見つめ、その問題を解決するお浄土のはたらきを聞かせていただいたならば心豊かに生き抜くことのできる充実した人生に変わっていくのではないでしょうか。浄土真宗は死んでからの教えではありません。今を生きる私達に今、必要な教えなのです。
私のいのちがあるのも、先立たれた人たちを含めた仏さまのお陰です。「お参りをする」ということは、亡き人を偲び、浄土に生まれさせる仏さまのお徳を讃えて、そのご恩に感謝することです。それと同時に、他ならぬ私たち自身がお念仏の教えを聞き慶ぶ事でもあります。ですから「亡き人のためのお参り」ではなく「私自身のためのお参り」と言えるでしょう。極端な言い方をしますと、仏さまを疑いなくいただき「生まれてきてよかった」「生きていることは素晴らしい」「死んでも悔いはない」と慶べたなら、生きても良し、死んでも良しという、生死を越えていく道、すなわち仏さまに成る道を恵まれるのです。
お彼岸をご縁に
2008年9月
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、北海道の短い夏が過ぎ去り、秋の訪れを感じさせる季節の到来です。秋分の日を中日とし、それぞれ前後三日計七日間をお彼岸としています。「彼岸」とは、迷いの世界であるこの世「此岸」から、悟りの世界である「彼岸」(お浄土)へと到るということです。彼岸のお中日には太陽が真東から昇り、真西に沈みます。西方十万億土の阿弥陀様の極楽浄土を偲び、すでに往生された故人やご先祖を憶うことで、他を顧みない自己中心的なあさましい私達を、西方のお浄土へと生まれさせ必ず仏にするぞとはたらいてくださるみ教えを味わう大切な仏教行事なのです。
よく人生は旅にたとえられます。どこからどこへ何のためにが明かでないと、その旅はあてのないものになってしまいます。どこへ行ってもそこには道があります。では一体どの道を歩んでいけばいいのでしょう。前御門主は、この不安と混迷の現代社会を乗り越えることができるのは、親鸞聖人のお勧め下さった念仏の道によってはじめて救われると信ずるといわれました。念仏の道は『おかげさま』と生かされる道であり『ありがとう』と生き抜く道であるとお示し下さったのです。私達が歩むべき道は「お念仏の道」なのではないでしょうか。その道はお浄土(彼岸)に向かう道です。お浄土(彼岸)に生まれさせていただき、阿弥陀様の国で仏とならせていただくこと(成仏)が人間に生まれてきた大いなる旅の目的なのではないでしょうか。多くの道の中から、私達に最もふさわしい「お念仏の道」をお示し下さり、その道を私達のご先祖の方々も歩んでこられたのです。「お念仏の道」は『おかげさま』と生かされる道であり、『ありがとう』と生き抜く道であります。『おかげさま』『ありがとう』を合い言葉に、お念仏に聞きましょう、お念仏申しましょう、そして親鸞聖人がお示しくださったお浄土(彼岸)への道を、南無阿弥陀仏のお念仏の光に照らされながら、共に強く明るく生き抜いてまいりましょう。
浄土真宗の教章(私の歩む道)
2008年7月
■宗名 浄土真宗
■宗祖(ご開山) 親鸞聖人(しんらんしょうにん)
・ご誕生 1173年5月21日(承安3年4月1日)
・ご往生 1163年1月16日(弘長2年11月28日)
■宗派 浄土真宗本願寺派
■本山 龍谷山 本願寺(西本願寺)
■本尊 阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)
■聖典
・釈迦如来が説かれた「浄土三部経」『仏説無量寿経』『仏説観無量寿経』『仏説阿弥陀経』
・宗祖 親鸞聖人が著述された主な聖教『正信念仏偈(『教行信証』の行巻末の偈文)』『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』
・中興の祖 蓮如上人のお手紙 『御文章』
■教義 阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏申す人生を歩み、この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に還って人々を教化する。
■生活 親鸞聖人の教えにみちびかれて、阿弥陀如来のみ心を聞き、念仏を称えつつ、つねにわが身をふりかえり、慚愧(ざんぎ)と歓喜(かんぎ)のうちに、現世祈祷(げんぜきとう)などにたよることなく、御恩報謝の生活を送る。
■宗門 この宗門は、親鸞聖人の教えを仰ぎ、念仏申す人々の集う同朋集団であり、人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝える教団である。それによって、自他ともに心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献する。
【教章が新しくなりました】
四月十五日より「浄土真宗の教章」が新しくなりました。教章は私達の信仰生活の規範となり、教えの要点と教団の基礎知識が示されているものです。
浄土真宗は、お釈迦さまの説かれた『浄土三部経』をよりどころとして、親鸞聖人が明らかにして下さった教えです。「仏説無量寿経」には、礼拝の対象である阿弥陀如来様(お念仏)のご本願が説かれています。それは「すべての人を必ず救う」という願いがはたらきとなって私がお浄土に生まれ、仏に成らせていただき、この世に還って迷える人々を導くはたらきをする教えであります。仏さまのみ心を聞きひらき、お念仏を称えたならば、自分自身の愚かさやこの教えに出遇えた慶びに気付いていくことでしょう。お浄土という確かないのちの行く先が定まる人生は、むなしく過ぎて行く人生ではありません。その日その時を大切に充実した日々を心豊かに生き抜いていくことができるのではないでしょうか。
「教章」を規範として親鸞聖人が生涯をかけて私達に示された教えを受けとめ、迷いの人生を送る私達に今、何が大切なのか、私達の歩むべき道を見定め、すべての人が心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献していきましょう。
ひとり
2008年6月
間もなく北京オリンピックが開催されますが、最近スポーツの応援風景が変わってきたように思えます。現地のスタジアムでの応援ではなく、スポーツ居酒屋など人の集まる所に大きなオーロラビジョンが設置され、その前での応援風景など、以前にはなかったのではないでしょうか。その上、多くの観客が集まると言うのには驚かされます。多くの人々と共有する応援の楽しさがそこにはあるのでしょうが、何かこのような応援風景ばかりでなく、世の中全般が、「みんなと一緒」の意識が強すぎるように思えます。昔「赤信号、みんなで渡ればこわくない」という流行りの言葉がありましたが、この傾向はだんだん強くなっているような気がします。しかし所詮人間は存在自体は孤独なのです。
浄土真宗が最も拠り所としている 『無量寿経』に「人、世間の愛欲の中にありて、ひとり生まれ、ひとり死し、ひとり去り、ひとり来る。身みずからこれを受け、代わる者あることなし」という一節がありますが、まさにわたし達はそれぞれがこの世にたった一人で生まれ、たった一人で去っていかなければならない存在です。携帯電話をいつも手放せない依存、アルコール依存、パチンコ依存。これらは孤独が辛いからなのではないでしょうか。「あの人が言ったから」とか「みんながしていることだから」とか、責任を「みんな」にかぶせてしまいがちです。誠実で根本的な責任の取り方ができなくなってきているようです。
人間は孤独な存在というのが、仏教の見方であります。 先人の逞しさは誰もが孤独に耐える強さをもっていたことです。お釈迦様も、松尾芭蕉も、種田山頭火も親鸞聖人も誰もが孤独との背中合わせに生き抜かれました。逆に孤独を耐えるというよりその孤独こそが自らを磨き上げる場として考えられている事だと思います。
孤独は辛いことでしょう。悲しいことでしょう。 「孤独死」などといいますと、やりきれない思いにおそわれます。「ひとり」という恐怖は、誰しも容易に想像できるでしょう。しかし、先哲はよく敢えて「世捨て人」として、自らを鍛え上げていきました。それは自己を観じる最も尊い時間で遇ったのでしょう。人は集団的な生き方をすれば「孤独」の苦しさからは逃れられるかもしれません。しかし、その中に埋没すればするほど「孤独」は恐ろしくなります。そして「みんなと合わせる」生き方が楽に見えてきます。しかしそのような生き方は何ら「孤独」の解決にはなりません。それどころか、本当にひとりとなった時には、さらに孤独感が増します。「ひとり」を友として生きていく覚悟がもとめられています。
阿弥陀様が「どんなに世間が冷たかろうが、どんなに他人から相手にされまいが私だけは決して見捨てず離すことはしない」と呼びかけられる大きな慈悲のこころに気付かされるのが「南無阿弥陀仏」のお念仏であります。お念仏に聞きましょう。お念仏申しましょう。そして、お浄土という確かないのちのよりどころに包まれながら、孤独であって孤独でない世界を強く逞しく生き抜いてまいりましょう。
『仏説阿弥陀経』「今、何が大切か・・・。」
2008年5月
長い冬も終わり最近ようやく春の日差しに恵まれ草木やお花も新しい芽をふくらませ綺麗な姿や可愛らしい姿を私達に楽しましてくれる時期になりました。また、入学の春でもあり真新しい鞄や靴を履いて学校へ通う新入生の子ども達もピカピカと輝いて見えます。
普段私達がご法事や祥月命日にお勤めさせて頂いてます『仏説阿弥陀経』と言うお経の中には、私達が往生させていただく、「お浄土」のお姿を、花で表現して下さった一節があります。
「・・青の花は青い光を、黄色い花は黄色い光を赤い花は赤い光を、白い花は白い光を放ち、いずれも美しくその香りは気高く清らかである・・」と。
お浄土に咲く花々。それは、お互いがお互いの光を汚すことなく、その一つ一つのいずれもが、精一杯に輝き、そして、光っていると表現されているのです。
学校へ通う子ども達一人一人にもきっと素晴らしい個性、光があるのでしょう。
走るのが速い子。絵がとっても上手な子勉強がよくできる子。思いやりや、やさしさのある子。我慢強い子。笑顔のかわいい子。花にたとえるなら、元気なひまわりのような子、静かで清らかな香りのする水仙のような子、と様々でしょう。しかし、その子一人一人の個性を、親の思う通り、先生の思う通りにしようとすると、子ども達の光を汚してしまうのかもしれません。
先生も親も子ども達も、お互いに輝く個性、光を持った中で、同じ一つの命として接することが、とても大切なようです。どの色の花が優れていて、どの色の花が劣っているというのではありません。それぞれが、それぞれの個性や持ち味を生かして、精一杯輝かせているのです。
仏様の願いは、「一人、一人の姿や性格はみんな違っていても、それぞれの『いのち』を精一杯輝かせて、人と違っていることで悲しんだり、淋しがったりくじけたりしてはいけないよ。たとえくじけそうになっても、私がちゃんとついているから、安心して精一杯、元気を出して生きて下さいよ。」という願いなのです。
「青色青光、黄色黄光・・」と示されこの経文の一節は、単にお浄土の姿を表現して下さっただけではなく、この混迷の現代社会にも通用する大切なことを私達に教えて下さったのです。
「そんなの関係ない」という私を支える尊いご縁
2008年4月
私達は様々な人間関係の中を生きています。自分に合う人、苦手な人など、自分の気付かないうちに、都合の良い人と悪い人を区別しています。「あれは隣の人のこと、私には関係ない」、「あれは外国のこと、私達の国には関係ない」というように、私に関係のないことだからと、考えることが多いと思います。どのようなつながりがあるのか解らないことは沢山ありますが、本当にこの世の中で私に関係のないものがあるのでしょうか。
親鸞聖人は歎異抄に「一切の有情はみなもつて世々生々の父母・兄弟なり」と、全てのいのちあるものは皆、遠い昔から、生まれ変わり、死に変わりしてきた中で、あらゆるものが父母、兄弟姉妹であると示されました。それはどのようないのちであろうと単独では存在せず、全てのいのちは深く尊いご縁によって一つにつながっているということです。
少子高齢化により、老人のひとり暮らしが多くなっています。年老いている私の介護を「子供にさせて迷惑をかけたくない」という人や、「他人に迷惑をかけたくない」と言う思いからか、葬儀を家族、親族だけで済ませることなど、普段の生活の中にも「他人とはあまり関わりたくない」と思うことが誰にでもあると思います。極端な言い方をしますと「自分には関係ないから」という無関心は、人の喜びや悲しみ、辛さを思いやることもなくしてしまい、自分ひとりの小さな殻の中に閉じこもり、孤独で寂しい人生、むなしい人生になってはいないでしょうか。
私達が人間としていのちを受けたご縁を考えてみますと、父母をはじめ、多くのご先祖様の存在がなければ今の私はありません。また日々、無数のいのちを奪い食べ、そのいのちに支えられて存在している。あらゆるものとのつながりの中にあり、多くのもののおかげによって、生かされている事実に気付くことでしょう。他人に迷惑をかけずには生きられないのです。この世は「もちつもたれつ」です。それを教えて下さったのが仏教であり、お念仏です。
介護に疲れ果てた娘が、老母を殺し自殺するなど、胸の痛む、いたましい事件が続いております。他人事ではありません。いつ私達も同じ立場になるかもしれません。そう考えると今、私達は積極的に身近な人から関わりをもち、心を開いて、敬い合い、支え合って生きていく必要があるのではないでしょうか。
願われ生かされている私
2008年3月
いま生きていることを、当たり前と思いますか?それとも、不思議と思いますか?「頼みもしないのに勝手に産んで、ああしろ、こうしろと親は好きな事を言う」大抵のひとは、似たような事を言いながら親に反抗しています。 「私のいのちは私のもの。どうしようが私の勝手だ。余計なお節介はしないでくれ」と思わず口をついて出たことはないでしょうか。あるいは、誰かに似たようなことを言われたことはないでしょうか。これはある意味捨て台詞かも知れません。「私のいのちだ。勝手にさせろ」と言われたとき、人はそれに怒りを覚えたり、無力感に襲われ黙り込んだりします。それでも尚相手と向き合おうとする人は、本当に相手のことを思っているのかもしれません。
ところで本当に「私のいのちは、私のもの」なのでしょうか。「私のいのち」を自らの思いで作ったと言う記憶はありません。気がついたら生まれていて、生きていたのです。たくさんの「いのち」の関わりの中で、自らの意思とは関係なく、お陰様の中で生かされていたのです。そんな生かされた「いのち」が昨今、粗末に扱われ過ぎているような気がします。毎日のように、この日本で殺人事件がおきています。自ら生命を絶つ人も年々増加し、年間三万人を大きく超えています。なぜこうなってしまったのでしょう?その背景を私たちは真剣に考えていかなければならない状況にあります。現代人の生命観の特色に「いのち」の所有意識があります。 かつて「いのち」は授かりものでした。しかし、現代の人々は授かりものという意識を、「いのち」に対してほとんど持っていないといっても過言ではありません。
「子供は何人欲しいですか?」 「二、三人は作る予定です」 こんな会話が結婚式等のときに交わされています。我が子の「いのち」さえ作り物と考える時代を私たちは暮らしています。「私が作ったんだから、私の勝手」と、 子供の「いのち」への所有意識さえ見られる風潮があります。しかし私たちは、そういった所有意識を持つことに 疑問を抱かずにいることに、なかなか気付けません。私たちの眼(まなこ)には、最も近くて大切なものが、最も見えにくいのかもしれません。このような心の闇を闇とも気付けない救われがたい私たちがいるからこそ「何としても救うぞ」という阿弥陀様の願いが生まれたのです。無数の「いのち」の支えで生かされている私。また、巡り合わせによって、どんな恐ろしいこともおこしかねない私。このような私の姿に気付かせ、同時にそのまま救いとってくださるのが南無阿弥陀仏のはたらきであります。お念仏に聞きましょう。お念仏を申しましょう。そして、お浄土という確かな「いのち」のよりどころに包まれながら、今を生き抜いてまいりましょう。
今日一日 わかっちゃいるけどやめられない
2008年2月
「仏法に明日ということは あるまじくそうろう」とは本願寺第八代門主蓮如上人がお述べになられたお言葉です。それは今日一日の大切さを、私達にお示し下さいました。
私達は日々の生活の中で、多くの人の死に出遇いみずからのいのちもまた、限りあるものであることを重々承知しています。いつおわるやも知れない自らのいのち。このいのちを精一杯生きずにはおられないと誰もが願っています。しかし、なかなか思うようにならない。今日やるべき事を明日に延ばし、明後日にのばしているのが真実の姿のようです。
「わかっちゃいるけどやめられない」という歌を唄った植木等さんは日本の高度成長期に「日本一の無責任男」として一世を風靡。「お呼びでない?こりゃまた失礼しました」のギャグで列島中を爆笑の渦に巻き込んだ人物です。
その素顔は実直な責任男。長年の知人たちによれば「普段は酒を飲まない」「まじめで勉強家」という素顔がうかんできます。その植木等さんが「スーダラ節」の楽譜を渡された時に「こんなくだらない歌は嫌だ。これを歌うと人生が変わってしまう」と悩んだほど。父親に相談すると「わかっちゃいるけどやめられない」の歌詞は親鸞聖人の精神に通ずると諭され歌う決意をしたといわれています。
この父こそが「人間植木等」の原点。故郷の三重県で浄土真宗の寺の住職だった父親は軍靴の音が響く時代に、差別、労働問題に身を投じて「人間平等」を説き続けた。そのために投獄され、小学生だった植木少年は父の代わりに僧依で檀家を回ったといいます。
まさにこの歌のように、わかってはいるのだけど「つい」というのが、私たち人間の本質なのではないでしょうか。
その様な人間の本質を自覚された上で、常に私たちを導いて下さる仏法に早く出遇う事が寛容かと思います。
「年を取ってからお寺に行けばよい」ということではなく、老若男女、全ての人が自ら時間を作り、今仏法に出遇って、自分の身をそして、こころを仏法の中に浸けていただきそのことによって、いのちの尊さに気づかされ、また常に忘れがちで、なまけがちな私たちに、大切な事を思い起こさせていただくもの、それが仏法であるのではないでしょうか?
老いても日々輝いていたい
2008年1月
新春のお慶びを申し上げます。日頃、皆様には当寺の護持発展にご尽力いただき厚くお礼申し上げます。本年は、開教120年記念事業である庫裏の工事が開始されます。当寺で行う葬儀や法要など、皆様にはご不便をお掛けすると思いますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
御文章に「一生過ぎやすし」という言葉があります。平成も今年で20年目、月日がたつのは本当に早く感じます。「年を重ねるごとに、時間の経過が早くなる」という方がおりますが、はたしてそうなのでしょうか。「若いときには考えもしなかったのに、年老いた今は1日が早く、1ヶ月が早く、1年が早い」と言う方や、「何もしないのに年ばかりとって困ってしまいます」などと嘆いている方が多くおられます。
そしていつの間にか高齢者の多い社会になってしまいました。「豊かな老後」という言葉がありますが、本当に満たされた老人の生活が実現しているのでしょうか。最近では年金の問題や生活費の上昇など、高齢者のみならず、私達の生活にも不安が増大しています。
お釈迦様は「人生は苦なり」と示されました。私達はこの世に生を受けた時から「老い」の苦しみが始まっております。それを止めることは出来ません。避けることも出来ません。当たり前の事実として受け入れて行かねばなりません。いつまでも元気でいたいと思って、高価な健康飲料などを飲み続けても年老いていく苦しみから逃れられません。
年を取ると目も耳も不自由になるし、体の機能は徐々に衰えていきます。人はそこで自らの「老い」を知り、孤独と寂しさを感じるのでしょう。
「あなたを絶対に見捨てない」という仏様のお心にふれ、人として生まれた苦しみを、人として生まれた有り難さに転じさせていただくのです。苦しみ悩みは尽きないけれども、それをそのまま受け止めて、いつも私に寄り添い、必ずお浄土まで導いてくださる働きとなって、すでに私達に届けられております。私がどんなに背を向け、拒否しても、いつでもどこでも必ず私を案じて付き合って下さいます。ですから、ただそれを素直に受け止めて、孤独や寂しさを和らげて下さる仏様と一緒に、苦悩の多い人生を歩ませていただきましょう。
仏法に出遇えた慶びを感じた時、年老いた事は決して無駄な事ではありません。顔にしわが寄っても心にしわが寄らないように。足腰が弱っても、心は強く。体が衰えても、心は明るく若くありたいものです。本年もお念仏と共に心豊かな、いのちの輝きに気付かせていただきましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|