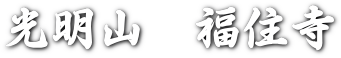月報「なむ」
2007年
流した涙の数だけ いのちが何かをおしえてくれた
2007年12月
ある方が癌で亡くなりました。そして病中、妻宛に手記を遺されました。その書き出しは「癌告知を受けて」から始まります。そこには、病院の検査結果がわかるまでの不安と、告知を受けた後の動揺と平静さを保とうとする葛藤までが素直に書かれてありました。「”まさか!”私は心の中で何度も叫んだ。”俺がそんな病気になるはずがない”と心の中でつぶやいた。いや、そう思いたかった。目の前が真っ白になりながらも、頭の中を駆けめぐっていたのは妻のことであった。妻も癌を患っている。しかも、余命六ヶ月と宣告されている。私はそんな妻に何をどう伝えればいいのだ。私の思いは千々に乱れた。」夫は半月近く悩んだ末に、ご自身の病気のことを妻に伝えました。その夜のことが手記にこう書かれてあります。「今日妻に病気の事を伝えた。私が入院している間自宅療養している妻を一人っきりにはできない。一緒に入院しようと私は言った。妻は静かに聞いていた。妻は私のそばに来て座り、私の背中を幾度もさすった。そして一言、”大丈夫よ”と言ってくれた。妻のその言葉で、私は涙があふれ止まらなくなった。”余命半年と言われてるのに、何が大丈夫なんだ?!”そう言いかけて、私はことばを呑み込んだ。これまでの妻の、悶々とした苦悩の日々を思った。内心の真実はわからないが、底知れぬ苦悩をあじわってきたからこそ、今日の穏やかさがあるに違いない。癌を告知された男が、余命半年の妻の膝に顔を埋めて哀れにも泣きじゃくった。」夫が遺した手記を大事そうに胸に抱いて妻は言いました。「不思議ですね。すでに余命を宣告されていた私が残り、看病していた夫が先に逝ってしまうんですから。 ”あなた。さっさと逝ってしまってずるいわよ”って、お仏壇の前で時々恨み事を言ってます。でも、夫が私にいのち本当のいみを教えてくれたのかも知れませんね。」ノートに書き遺した夫の言葉、そして妻のいう言葉を通して、絶望の底をくぐり抜けてきた人の優しさを感じずにはいられません。「絶望を体験したことのない者の言葉を私は信じない」親鸞聖人に深く傾倒していった北海道出身の昭和の文学家、亀井勝一郎氏の言葉です。亀井氏は親鸞聖人の絶望の深さを、同時にいのちの深さとあじわった人でもありました。 人生に無駄はひとつもありません。悲しみも苦しみも悩みも、いのちを深める貴重な糧です。そんな豊かな世界を開いてくださるのがお念仏です。仏様の大悲のおこころを聞かせていただいたならば、死は虚しい滅びではなくお浄土にうまれ仏さまにならせていただくご縁であります。悲しみは尽きないけれど、それをそのまま受けとめてお浄土まで導いてくださる大いなる呼び声が「南無阿弥陀仏」のみ名となってすでに私達に届けられているのです。お念仏に聞きましょう。お念仏申しましょう。そして、お浄土という確かないのちのよりどころに包まれながら今を生き抜いてまいりましょう。
ありがとうと いえる よろこび
2007年11月
「ありがとう」という挨拶の言葉は「有り難し」から転用されたものです。仏教では「難し」を単にむずかしいという意味ではなく、不可能という意味で使ってきました。ですから、有り難しとは「有ることが不可能」ということになります。そこから考えると「ありがとう」とは感謝の表現であると同時に、あり得ないことがあったという驚きの意味も含んでいるといえます。
今ここに生きていることを、当たり前と思いますか?それとも不思議と思いますか?「そんなことは考えたこともない」そうおっしゃる方がいるかもしれませんが、よくよく考えてみたら、今ここに「わたし」が生きて存在しているというのは不思議に思えてなりません。それは、二十一世紀のこの日本に家族と共にあることや、まわりで「わたし」を支えてくれる人びと、立っている大地、どれひとつとして自分が選択したものではありませんでした。
我が親や我が子でさえ「わたし」が選び取ったものではありません。選択の余地なく、気がついたら親や子としてあったのです。しかも自分の認識を越えてある、それらの人びとやものごとに支えられて今日が成り立っています。又それは、自分の身体と思いこんでいるこの身体も「わたし」の認識を越えて存在しています。無意識のうちに呼吸し、意志を越えて心臓は動き、体内を血液がかけめぐっています。三千大世界といわれる大宇宙に比べて、一メートル数十センチのこの身体は決して引けを取らない不思議さを湛えています。
私たちが生きるということは、出会いと別れの織りなす道を歩んでいくということでもあります。その出会いと別れを、当たり前とみすごしていくか、不思議と受けとめていくか、それは私たちの人生を深くし、今あることの不思議さに響く心を持てるかどうかの別れ道なのではないでしょうか。
医師からガンで余命半年と宣告され、三十四才で亡くなられた青年僧侶の手記に「間に合った」と書かれてあります。「私の聞いてきた教えは浄土真宗だ。とっくに間にあっていたのだ。もうすでに摂め取られていたのだ」「この教えに出会えたことが、私の最大の幸せ、喜びと初めて気づかされた。南無阿弥陀仏」と記されています。さまざまな葛藤があったでしょうが、幾度も「よかった」と書く最期のその人のなかに、ありがとうと生き抜いていかれた尊いいのちを拝まずにはおられません。
嬉しい事も 楽しい事も 苦しい事も 悲しい事も 全部私の宝物
2007年10月
これまで歩んできた人生を振り返って、すべてが楽しいことばかりであったと思えるひとはまれなのではないでしょうか。順風満帆な人生を歩んでいるように見えるひとでも、心の内を聞かせていただいたら、ビュービューと冷たい風が吹き荒れているということもよくあることです。できることであれば、嬉しいこと楽しいことだけの人生であってほしいと願うのが人情というものかも知れません。けれども、仮に何の問題も起こらず、楽しいこと、嬉しいはずのことばかりに囲まれて生きていたとして、その人が幸福に思っているかというと、不思議にそうでもありません。
「尊となく卑となく、貧となく富となく、少長男女ともに銭財を憂ふ。有無同然にして、憂思まさに等し。屏営として愁苦し、念を累ね、慮を積みて、(欲)心のために走り使はれて、安き時あることなし。田あれば田に憂へ、宅あれば宅に憂ふ」 (『仏説無量寿経』巻下)
問題があって苦しむのではなく、みずからが問題を作って苦悩していくのだと釈尊は示されたのでした。けれども、「問題」の中で苦悩している真っ只中で、その問題をみずからが作っているとは思えないのが私たちでもあります。
鳥取県に足利源左さんという方がおられました。幕末から昭和のはじめまで生きられ、妙好人と慕われた方でした。お寺参りの帰りに、草のはえた田圃を見て源左さんは田圃の中に入って草むしりを始めました。通りがかったひとが源左さんに声をかけます。「源左さん。そこはあんたの田圃じゃなかろう」源左さんは答えました。「おらの田圃、他人の田圃と小さなこと言うなや。如来さんの目から見たら、みんなかわいい田圃じゃろう」
「ようこそ ようこそ」が口癖であったと伝えられていますが、源左さんは生涯に二度も火災で家を失っています。火事見舞にかけつけた手次寺のご住職に源左さんは言われました。「如来さんがお浄土を用意しているのは、わしのためであったとようようわからせてもらいました。ナンマンダブ ナンマンダブ」
「目が変わる。心が変わる。世界が変わる」といわれたひとがおりますが、お念仏の教えによって見事に視点がかえられたのでありましょう。逆境や苦悩さえもが私を育ててくださる宝ものであったと知らされる世界、それがお念仏の世界であります。
報恩講
2007年9月
浄土真宗では、初秋より一般寺院で「報恩講」の法要が営まれます。「報恩講」とは、浄土真宗を開かれた親鸞聖人の三十三回忌を、曾孫にあたる本願寺第三世、覚如上人が勤めた時よりはじまりました。覚如上人は親鸞聖人のお徳を讃え深い感謝を表し、「報恩講」の法要儀式・作法に関する『報恩講式』と言う書物を著述されました。以来、連綿と受け継がれている法要が「報恩講」なのです。また覚如上人は、その三十三回忌報恩講を勤めた翌年には『本願寺聖人親鸞伝絵を著されました。それは、親鸞聖人の御一代記を絵図と詞書きによって綴られた物です。現在は絵と文章に分けられ、絵の部分は「御絵伝」と言う掛け軸として「報恩講」の時にはお寺本堂内陣の左余間に掛けられます。文章の部分は『御伝抄』と言う書物となり、 福住寺では「報恩講」二日目の午後六時より拝読されます。その『御伝抄』の中に思いもよらない論争があったことが著されています。それは、親鸞聖人がまだ法然上人の門下生の時、「自分の信心と、師である法然上人の信心とは全く同じである」と言われたのでした。それが弟子達の間で大変な問題となり、智慧第一と言われる師の法然上人の信心と、弟子の親鸞聖人の信心が同じはずがないと反論されたのでした。そこへ法然上人が現れその論議をお聞きになり「信心に違いがあるというのは自分で作る信心だからであります。信心とは阿弥陀様からの頂き物であり、私達人間が計らい知る事の出来ないものでありますから、私の知識や経験が加味されるようなものではありません。したがって、私と親鸞の信心は少しも異なる所はなく、ただ一つ同じであります。」と答えられたのでした。浄土真宗の信心とは当てにならない自らの計らいを捨て全てを阿弥陀様におまかせすると言うことであります。阿弥陀様はこの世で迷いもがき苦しんでいる、いきとし生けるもの全てのもの残らず救うと言う願いをたてられ、もしその願いが成就しなければ私は決して仏に成らないと誓われました。そして、大変な苦労をしてその願いを成就し、私達一人一人残らず救うため、我を呼べ、我に頼めと「南無阿弥陀仏」のお念仏と言う呼び声となって私達の口から出て、至り届いてくださっているのです。闇夜では自らを照らすことは出来ません。明るい光が闇を照らすことによって自らがうつしだされるのです。太陽が無くては月も輝くことができないのです。私達人間は自己中心的に物事を考えがちであり、また現代社会においては忙しい日暮の中自分と言う物を見失いがちです。そういった私達であるからこそ阿弥陀様と言う真実の光に照らされることによって自分の進むべき道を見いだされ強く明るい日暮らしを過ごせるのではないでしょうか。親鸞聖人は、闇より自らの心を阿弥陀様の光明に照らしだされ、晴らされた事を喜ばれ、強く明るく生き抜かれたかたでした。そして、私達もまた親鸞聖人を手本として 「南無阿弥陀仏」とお念仏の人生を生かさせていただきましょう。
お浄土から願われている私
2007年8月
先立たれた大切な人は、阿弥陀如来の働きによって、お浄土に往生して、阿弥陀様と同じ仏様になられました。眠っている暇なくこの世に還り、迷いの世界を右往左往しているとも気づかない私を、お浄土へ導びこうと働いてくださいます。その働きがお念仏です。私が亡き人のために「成仏しておくれ」または「おたすけ下さい」と、お願いする必要はありません。お願いする前から私の方が願われているのです。「与えられた命を精一杯生き抜いておくれ」と亡き人の願いがお念仏となって私の口から出てきます。
お念仏はこの世に残された私にいつも寄り添い「大丈夫、心配いらないよ」と働きかけて下さっております。その呼び声を聞く私はお浄土への道のりをすでに歩んでいるのです
そんな尊い働きに気づいたならば、亡き人と別れた悲しみも乗り越えられていくでしょう。そして生きてよし、死んでもよしの人生を力強く心豊かに生き抜く事が出来るのではないでしょうか。
赤ちゃんがこの世に生まれる時には様々な準備を整え、願いをかけます。しかし人間の準備にはあてにならない事が多く、願いがそのまま働くことは難しいようです。それに対して、私が浄土に生まれていく為の準備は、仏様が全て間違いなく完全に仕上げられております。「必ず救う」という願いがそのまま働いて、その働きを、ただ念仏していただくばかりになっています。
人間としてこの世に生まれた大きな目的は、この仏様の教えに遇うためであり、お浄土に生まれていく事にあるのではないでしょうか。そんな尊い仏様に願われている私であるからこそ、私達の命は尊いと言えるのではないでしょうか。
親鸞聖人は歎異抄に「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり」と、仏様の深いお心に気づかされ、愚かな私一人を救うために願われていると味わわれました。
御文章について
2007年7月
本願寺が飛躍的に発展したのは八世蓮如上人(1415〜1499)のときであるといわれております。蓮如上人は四十三歳のとき父の存如(1396〜1457)のあとを継いで本願寺第八世となりましたが、その根本は積極的な民衆教化をすすめ、一挙に教線を拡大しました。なかでも御文章または御文といわれる真宗の信仰のありかたを御消息(書簡形式)で平易に説き真宗普及に果した役割は大きいといわれております。
現在も当寺のみならず各寺院の勤行・法話のあとなどでも拝読されていますがその数は真為未決のものを除いて221通が伝えられています。その中でも特に親しまれ広く知られている聖人一流章(五帖第十通)について現代語に訳し触れさせていただきます。
【聖人一流章の意訳】
【親鸞聖人の開かれた浄土真宗のみ教えでは、信心が根本です。そのわけは自力のはからいを捨て、一心に阿弥陀如来に帰命すれば本願のはたらきによって如来が私たちの往生を定めてくださるからです。往生が定まったその位を「一念発起入正定之聚」と示されています。そして信心を得た後に称える念仏は、如来が私の往生を定めてくださったご恩を報じる念仏であると心得るべきです。】
このように現代語訳を見ても、浄土信仰のおける信心はやはり大きな役割を果すことがわかります。また221通の御文章の中には戦国時代の一向一揆など時代背景の様子を知る資料としても重要な役割を果しています。
以上のことをふまえ、あらためてこの御文章を拝読、拝聴しますと今までよりも深く蓮如上人が示された御文章を味わうことができるのではないでしょうか。
生死出づべき道
2007年6月
親鸞聖人は今から834年前、承安3年 (1173年)5月21日京都の南、日野の里に誕生しました。幼くして両親と別れ9歳で出家して、20年間比叡山で仏教を勉強し厳しい仏道修行に励まれました。人一倍感受性が強く、人生を深く見つめる眼を持っていた聖人でしたが、求めていました「生死出づべき道」という問題の解決を得る事が出来ず29歳の時、比叡山を下りました。そして浄土宗の開祖、法然上人にめぐり遇い、弟子としてお念仏の道を学ばれたのです。
「生死出づべき道」とはどのような道でしょうか。私たちは生きている事を当たり前のように考え、その向こうに死があるように思いがちです。しかし、よく考えて見ますと昨日までの命は何処にもなく、明日の命を保証するものは何処にもありません。確実な事はこの命は今ここにしかないという事です。別のいい方をしますと、私が生まれてきたという事は、私たちの背中に死がぴったりとくっついているのです。死と共にある生なのです。ですから聖人の求めた道とは、その生死の苦しみを超えて行く道、すなわち仏のさとりをひらくことに他なりません。
聖人は90歳で往生されるまで、お念仏の道を人々に伝え、人間が本当の仕合せに生きる道は、この教えに導かれること意外にはないということを明らかにされました。自分自身の姿を徹底的に見つめられ、権力や財産などを求めず、ひたすら人々が仏様の働きによって生かされて行く道を切り開いて下さいました。それゆえ、聖人が説いた教えが、長い年月を超えて、今日も多くの人達の心を捉えている、それは私たちもまた聖人が生涯かけて問題とした人生の問題を、同じように背負っているからではないでしょうか。
聖人が力強く歩まれた「生死出づべき道」を私達もお念仏と共に歩ませていただきましょう。
南無阿弥陀仏ということ
2007年5月
普段、私達が口にしている「南無阿弥陀仏」とはどのような事でしょう?
当寺で営む法事、あるいは月参り等々、様々な状況ではありますが、そこに仏様がおられるということは間違いありません。
南無阿弥陀仏とは、阿弥陀仏に帰依するという意味であり、六字の名号、あるいは弥陀の名号ともいいます。この南無阿弥陀仏とは、浄土信仰の根幹であるだけに様々に意味づけられています。
宗祖親鸞聖人は、「教行信証」のなかで詳細な解釈をほどこしています。
この六字の名号(南無阿弥陀仏)とは衆生(私達)が救われるために仏から衆生に与えられた行であるということを明らかにされ、したがって衆生(私達)の側からいえば、ただ仏の本願の力を信じることによって浄土に住生する身と定まるのであるといわれています。
また、本願寺八世蓮如上人は「南無」は「たのむ」という衆生の機(人々の心のありかた)をあらわし、「阿弥陀仏」は「たすける」という仏の法を表すという解釈をしておられます。すなわち「南無阿弥陀仏」とは、仏からいえば「たのむものをたすける」という本願を示し、衆生(私たち)からいえば「たすけたまえ」とたのむ信心を表し、それが口に称えられた時に、信心を喜ぶお念仏となるといわれました。これが私達の住生が定まる他力の信心であると心得て、南無阿弥陀仏と称えれば、今まで以上にお念仏を喜び、深く味わうことが出来るのではないでしょうか。
永代経
2007年4月
祖父母、父母、子、孫、曾孫・・・・。 長い年月を経ても、いのちをつなぐ糸は永代に続いて欲しい。今を生きる私達のいのちは、子孫にまで永代に継がれてほしい。その要であるお念仏のみ教えに感謝し永代に勤まる法要が「永代経法要」です。 浄土真宗で言う「永代経」とは、お念仏の尊いみ教えを私達に伝えて下さった有縁の方々のご遺徳を偲び、私達自身が聞法に励み、その真実のみ教えを今度は子や孫へ伝えていくことこそが「永代経」の意味するところであります。真実のみ教えとは、阿弥陀さまの働きによって煩悩具足の凡夫が煩悩あるがままに、お浄土に生まれさせていただく教えです。煩悩あるが故に、情愛あるが故に、いつも苦しみ悩みながらこの心を焦がし、胸を痛めて生きて行かねばならない。それは、迷いの境涯を巡る種になります。迷いの境涯を断ち切るために、阿弥陀さまはお念仏となって私たちの所にいたり届いて下さるのです。私達にいたり届いて、口から声となって出て下さるのがお念仏です。
私たちには用はなくても阿弥陀さまのほうが用があると、阿弥陀さまの声が私たちの口にかかり、南無阿弥陀の名号となって耳に聞こえて下さいます。
お念仏の道は、お陰様と生かされる道であり、ありがとうと生き抜く道であります。どんな辛い悩み苦しみがあろうとも、阿弥陀さまの呼び声に導かれ、お浄土まで生きる希望、勇気、喜び、安心を与えられていく、それがお念仏もうさせていただく者の喜びでありましょう。
永代経の永代とは、お念仏のみ教えが永代に受け継がれていく意味を持つものであり、お念仏の声を子や孫にという思いを心にとめて「永代経法要」をお勤めさせていただきましょう。
いずれ 生まれさせていただく 彼岸には また会える世界が 広がっている
2007年3月
私がこの世に生まれるのには、両親がいなければ絶対にありえません。もう1代さかのぼりますと、両親の祖父母そこには4人のご先祖様がいます。このように単純に考えていき、10代さかのぼると1024人、20代さかのぼりますと、100万人余りとなります。私一人がこの世に生まれるのに、多くのご先祖様が命を受け継いだことになり、その中の一人が違っていただけで、私は生まれていないのです。なんと不思議な事ではないでしょうか。ご先祖様のおかげで、命を恵まれ今の私が存在するのです。そんな恵まれた命も、最近では、いじめや自殺、幼児虐待など様々な事件が多発しております。
私達は今、忙しい毎日を送る中で、静に自分の生き方を振り返り、何のために生まれ、生きているのか考えてみる必要があるのではないでしょうか。そして私の命の行く先は何処なのでしょう、それが分からない事ほど不安なことはありません。
死んだらおしまいという考え方があるようですが、それは本当にむなしく、寂しい人生だと思います。たとえ、病気になって、お医者さんが私の命を見放したとしても、その命を放っておく事の出来ない阿弥陀様がいます。そんな大きな働きによって、私が死んだら、お浄土に生まれさせていただき仏様と成る。そして、この世に還って残された迷える人を救う働きをする、と気づかせていただく事が出来たならば、心豊かな人生を送る事が出来るのではないでしょうか。
お彼岸には先祖を偲び、今を生きている私が仏法を聴聞する大切な仏教行事です。人として生まれた大きな目的は、仏様の教えに遇い、お浄土(彼岸)に生まれて往くことではないでしょうか。この世は別れて行かねばならず、死んでいかねばならない世界です。それに対して、お浄土は会える世界、生まれて行く世界です。
お念仏を申す私達には先立たれた大切な方と再び、お浄土で会う事が約束されております。生まれ難い人間に生まれ、聞き難い仏法に出遇っている今を大切にし、命を受け継いでいく人へ念仏の相続に勤しんでまいりましょう。
正信偈
2007年2月
印度西天之論家
中夏日域之高僧
顕大聖興世正意
明如来本誓応機
インドに出られた論家(龍樹・天親菩薩)方
中国、日本の高僧(曇鸞・道綽・善導・源信・源空)方は
お釈迦様(大聖)がこの世に出られた本意(正意)をあらわし
阿弥陀如来の本願(本誓)は末世の私のためのものだと明らかにされた
お釈迦様の説かれた、お念仏の教えが私に届くまで無数の高僧、信者達の努力が積み重ねられています。そういう先輩の中から親鸞聖人は特に七人の高僧を教えの師として仰がれました。それは、インドの龍樹菩薩、天親菩薩、中国の曇鸞大師、道綽禅師、善導大師、日本の源信和尚、源空(法然上人)あわせて七人の方で「七高僧」や「七祖」などと呼ばれております。
聖人が、そもそも本願念仏を頂いたのは、法然上人との出遇いによるものでした。比叡山を下り、法然上人の弟子として念仏の道に入られたのは二十九歳の時でした。そして法然上人は源信和尚の『往生要集』を通じて、善導大師の『観経疏』を読まれ、念仏の世界へ入られます。法然上人に多大な影響を与えた善導大師は、道綽禅師のもとで直接、学ばれ、道綽禅師は曇鸞大師の功績を讃えた石碑を読まれ、大きな感動をうけ、浄土往生の道に入られます。曇鸞大師は龍樹菩薩の思想を受けながら天親菩薩の『浄土論』を解釈して『浄土論註』を作られました。しかも龍樹菩薩は『易行品』の中に阿弥陀仏の浄土への願生を述べられております。
阿弥陀仏の本願の教えを受けとめられた七高僧が、それぞれの国で時代や社会に生きる人々に応じた解釈をされました。したがって、それぞれ表現の違いはあるものの「お釈迦さまがこの世に現れた意味とは阿弥陀仏の本願を説くためであり、それは、われら衆生のために建てられた、ふさわしい教えである」と明らかにして下さったのであります。
聖人は七高僧のおかげで、念仏の教えにあうことができたと、深い感謝と尊敬の念をもってお念仏をいただかれました。
当寺本堂の内陣、向かって左側(左余間)には七高僧の姿を現した掛け図が、掛けられております。是非、七高僧の尊いお姿を味わってみてはいかがでしょうか。
初日が光るとき
2007年1月
初日が光るとき 大地がが光る 大空が光る
初日が光るとき 一切が光る われらが光る (中西 智海)
新春のお慶びを申し上げます。お正月を迎えると、思い浮かぶ言葉があります。それは、『蓮如上人御一代記聞書』の「道徳、今年でいくつになったのか。道徳よ、念仏申しなさい。念仏と言っても自力と他力とがある・・・」と言うお言葉です。これは明応二年(1493年)の元旦、本願寺第八代宗主、蓮如上人が門弟の道徳に向かって語られたと伝えられているお言葉です。道徳は、新年のご挨拶に伺ったのに蓮如上人はいきなり、お念仏を申しなさい、しかも、自力のお念仏ではなくて、他力のお念仏を・・・と。お正月早々、なんと、厳しいことを言われるお方であろうとの印象を受けこの言葉が残っています。大切なことであればこそ、お正月早々、引き締まった年頭の挨拶の時におっしゃった上人の厳しくも優しい人柄が偲ばれます。蓮如上人は阿弥陀様の本願のはたらきから申す念仏を「他力の念仏」といわれます。これに対し、「自力の念仏」というのは、お念仏を自分の能力で称えられるものと誤解して、念仏を数多く称え、その功徳によって仏が救ってくださるように思いこんで称える念仏であると誡(いまし)められたのです。すなわち、阿弥陀様の大いなるはたらきが至り届いてお念仏となって下さったにもかかわらず、私の能力、私の先手であるという認識で称えるのが自力の念仏なのです。私達は、さとりを目の前にしても、それがさとりとは気付きません。でも、さとりは、本願のお念仏となり、私の所に至り届いてくださっています。何も加えることなく、何も付け足すことなく邪推は捨てお念仏のままいただいていきなさいという阿弥陀様の声が心に聞こえてきます。
人生には目標や目的がはっきりしていると、それが励みとなる事があります。しかし私の命の目的地はどこにあるのか解らない事ほど、不安な事はありません。本年も「私の生死の目的はどこなのか」ということを聞かせていただき、お念仏申し続ける一年でありたいものです。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|