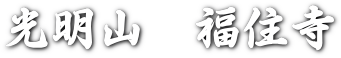月報「なむ」
2006年
正信偈(その9)
2006年12月
弥陀仏本願念仏
邪見僑慢悪衆生
信楽受持甚似難
難中之難無過斯
阿弥陀仏の本願による念仏の法(教え)は
誤ったよこしまな考えをもち、おごりたかぶる人びと(悪衆生)には
信じること(信楽受持)は、はなはだむずかしい
難の中の難で、これ以上に過ぎるむずかしいことはない(無過斯)
「井の中の蛙大海を知らず」という諺がありますが、私達は自ら「私が、私が」という我執の小さな井戸を掘って、その中に閉じこもり、少し物事が順調に進むと「私一人の努力が、苦労が実った」とうぬぼれて自らを見失い、物事が順調に運ばないと「あの人がつまらないから」「この人がつまらないから」「世の中がつまらないから」と、あたりちらして己を見失います。
阿弥陀如来の本願は、「ここに広い広い真実の世界があるよ。一時も早く、そんな狭い暗い井戸の中から出て来なさい。あなたの本当の故郷は、このみ法の光り輝く真実の世界なのですよ。すぐに帰ってきなさい」という南無阿弥陀仏の呼び声となって、井戸の中でウロウロする私を抱きかかえに来て下さっているのです。
私達は、この呼び声に信順するだけで、小さな井戸の中から出られるのです。私を呼んで下さる南無阿弥陀仏の呼び声を喜び、お念仏申しながら歩ましてもらうままが真実の世界、本当の故郷に帰る人生となるのです。何と易しい、何と素晴らしい道でしょうか。ところが、この易しい道を難しいものにしてしまうのが、邪見の人と僑慢の人です。邪見の人とは「自分の考えか一番正しい」と思い込んで、如来のみ教えに耳をふさいでいることです。僑慢の人とは、自分の家柄・財産・地位・健康・知識・美貌・能力等を誇り、他の人の言う事を軽視する人です。さらにいいますと、その気になれば自分の能力で仏に成ることさえ可能だと思い込んでいる人です。これらの人は、他の人の言う事を鼻であしらい、如来のみ教えさえも、まともに聞こうとはしませんから、南無阿弥陀仏の呼び声が耳に届いていましても、受けとめる事もなく、聞き流してしまいます。それで易しい道も結局難しいものになるのです。それは極難といわれ、これ以上の難しい事はないという難しさであるといわれるのです。そして私達は「仏様のお話をしっかり理解しなければ」という思いがありますが、これは阿弥陀様を頼りにしているようで、実は自分自身が納得しなければ、阿弥陀様を信用できないという思い上りの世界です。これらの事は他人事ではありません。私こそが常に邪見と僑慢のとりこになっているのです。
親鸞聖人はここで本願の念仏を頂く心構えについて示されました。それは、親は子供に対して無条件にまごころを注ぎ、子供はそれを分別や計算を抜きにして受け入れます。これは全く理屈抜きの世界です。それと同じように私達も理屈抜きに、尊い親様のみ教えをただ頂きなさいというおさとしではないでしょうか。
【女性のための正信偈 藤田徹文著 参照】
正信偈(その8)
2006年11月
獲信見敬大慶善
即横超截五悪趣
一切善悪凡夫人
聞信如来弘誓願
仏言広大勝解者
是人名分陀利華
信心をいただいて仏さまを敬い、大いに喜ぶ(慶喜)なら
五悪趣といわれる迷いの世界を即座に飛び越え(即横超截)
世間で善人だ、悪人だといわれる一切の人びとは
阿弥陀如来の本願(弘誓願=第十八願)を聞いて信ずれば
お釈迦様は、広大な智慧を得た者(広大勝解者)とほめたたえ
この念仏の信心の人を泥沼に美しく咲く白蓮華だとたたえられる
ここには、迷いの世界として地獄、餓鬼、畜生、人間、天上の五悪趣があげられています。それは実体としてどこかにあるわけではなく、現実の日暮らしの中で、私がつくり、私がおちいっている境涯であり、私たちが自己というものに執着した姿であります。
地獄道とは、傷つけ害し殺し合う世界。餓鬼道とは貪欲、貪りの世界。畜生道とは傍生とも言い、人間を中心として他の動物たちを傍らにするあり方をさし、能力、資質の違いによって相手を傍らにしていく差別の世界です。
こうした 迷いの世界に生きている私ではありますが、阿弥陀如来から賜った信心によって、ながい自力修業のまわり道をしなくても、一拳に迷いのきずなが断ち切られるのであります。それを宗祖親鸞聖人は「他力の教えは信心こそが肝要である」と『唯信鈔文意』に表しています。
この文の最尾の部分に分陀利華というお言葉が出てきますが、インドの言葉の音を漢字にそのまま写したもので、訳しますと白蓮華のことをさします。 白蓮華は、清らかな流れに育つのではありません。よどんだ汚い泥沼から芽を出し、葉をひろげ、しかも、まったく泥には染まらず、美しい白い花を咲かせます私達も同じように、全く汚れのない清らかな世界では生きてゆけません。煩悩をはなれて、いのちを保つことはできません。しかし、泥まみれの私に届けられたお念仏の働きで、お育ていただいたうえからは、泥のなかの身ではあっても、泥におぼれ染まることなく、泥のなかに生きているという深い自覚と反省をもつ白蓮華とならせていただきます。
『観無量寿経』には「念仏者は、人間のなかの分陀利華と讃えられている尊い人である。」と説かれています。
正信偈(その7)
2006年10月
摂取心光常照護
己能雖破無明闇
貪愛瞋憎之雲霧
常覆真実信心天
譬如日光覆雲霧
雲霧之下明無闇
阿弥陀如来の摂取の光明は、常に私を照らし護って下さる
仏さまを疑わなくなり(無明闇を破す)、救われた身になっても
むさぼり(貪愛)や瞋り憎しみの心は、雲や霧のように
常に如来からたまわる真実の信心の上におおいかぶさっている
たとえば、日光は雲や霧に覆われていたとしても
雲や霧の下は明るくて闇がないが如し(救われるということ)
この六句は信心の利益、つまり信心の人は常に如来の光に護られる事がとかれています。
では、お念仏に出遇い、お念仏を称えるようになった私たちの心はいつも、雲ひとつない快晴な心持ちかと言いますとそうではなく、むしろ、絶え間なく襲ってくる貪りやいかりの心でいっぱいです。
いっこうに救われる慶びの心も沸いてきません。
むしろ、あまりの煩悩の激しさに「本当に救われる」だろうかと不安を覚える事さえあります。
こうした懸念に対して親鸞聖人は正信偈のこの六句の巧みな喩えを通して答えられました。
「日光はしばしば雲や霧に覆われるけれども、太陽が輝いているかぎり、どれほど雲霧が光をかくそうとも、その下は明るく闇ではない。同じように信心の智慧が恵まれても、人間であるかぎり煩悩の雲霧は絶え間なく覆う。だが、摂取の心光に護られて信心は壊れることなく、絶えず続いていく」と教えられるのです。
親鸞聖人は「一念多念文意」に
「凡夫というは、無明煩悩われらが身にみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみねたむこころ、おおくひまなくして 臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえず、」と述懐されています。息の引き取るまで、煩悩に明け暮れるわたしであると言い切ります。
そのような私でもお念仏に出遇い救われて行きます。
歎異抄の第九章にはお念仏に出遇いながら常に喜ぶ心がわいてこない弟子唯円に「親鸞も同じこころです」とあたたかく答えられます。
弟子唯円と同じ悩みをうち明け、人間の煩悩の深さに悲しみ嘆きながら、それでこそ如来様の救う目当てはこのような私であったと 確信し喜んでいかれました
慈光に包まれながら、どう処理することもできない煩悩の深さを反省されるとともに それをも障りとされない如来様のお慈悲の広大さを尊く仰がれています。
正信偈(その6)
2006年9月
能発一念喜愛心
不断煩悩得涅槃
凡聖逆謗斉廻入
如衆水入海一味
ふたごころなく(一念)本願を信じよろこぶ(喜愛心)なら
煩悩を断たないままで、涅槃(覚り)を得ることができる
凡夫も聖者も極悪の人も、自力心を捨てて信心の道に入れば
川の水が海に入って一味になるがごとく、平等に救われる
仏教で説かれる最大の利益は「大涅槃」つまり覚りです。この仏様の覚りを、みにくい煩悩をかかえたまま、浄土に往生して得るのです。
煩悩とは簡単に言えば、自分中心の欲望です。「三毒の煩悩」といわれるものには、貪欲(自分だけいいものが欲しい)、瞋恚(自分は正しいのに相手が間違っているという腹立ち)、愚痴(自分としたことがという後悔)があります。この中の貪欲について考えてみますと、貪欲とは人とくらべ合わせて深い浅いを論じるものではなく、世の中に平凡に生きていくうえで必要な欲望を指すのです。たとえば、八百屋さんで店頭のはかり売りで、いつも多目に入れてくれる店に対して、きっちりとはかり売りするところは、ついケチな店だという印象をもってしまいます。しかしそれは決して自分の欲得づくのせいばかりではないのです。仮にその役目がお母さんなら、トクな店を選んで上手に買い物をするのが、家計のためにいいことだからです。お母さんが欲得づくになるのは、お母さん個人のためではなく、家族全員のために、そうならざるを得ない。ですから普通の生活をしている人間にとって、欲望というものから離れられないのです。
親鸞聖人は、師の法然上人によって阿弥陀様の願いを聞かされた結果、阿弥陀如来の完全なる救いの力(他力回向)はこうした日常の欲望の仕組みからのがれられない私達こそ、目当てだったとよろこばれたのです。
海辺を歩いてみると、いろいろな河口があります。きれいな水が流れ込んでいるのもあれば、湾内を黄色く染めるほど濁っているものもあり、それが、広い海のむこうに溶かし込まれていったら、まったくひとつの海水になってしまう。きれいな水も濁った水も「一味」になる。煩悩で心の濁った人は、人生という流れの中でいくらもがいても、自分の力できれいにすることはできません。それが海のように広い仏様の世界に、濁ったまま受けとめていただいてはじめて、きれいな水、濁った水もない、ひとつの海になるのです。
仏様に救われるとは、こういう姿だったのだと、聖人はふかく印象にとどめられて、その海の印象がこのおたとえになったのでしょう。煩悩のまま救われていくのが“真宗”です。
お盆のご縁
2006年8月
お花だったら
もしも私がお花なら
とてもいい子になれるだろ
ものが言えなきゃ、あるけなきゃ
なんでおいたをするものか
だけど、誰かがやって来て
いやな花だといったなら
すぐに怒ってしぼむだろ
もしもお花になったって
やっぱしいい子にゃなれまいな
お花のようにはなれまいな (金子みすず)
他人同士はもちろん、親子のつながりも希薄になってきたと指摘される昨今ですが、実際それが原因とされるような、さまざまな事件が起きています。新聞にはあたかも日本中の人間関係・親子関係が崩れているかのように書かれていることもありますが、まだまだお盆には里帰りをして、家族大勢で過ごされる人達が大半ではないでしょうか。そんなお盆のご縁を大切にし、家族そろってお仏壇に手を合わせ、まず自分がこうしてここにいるという身の幸せを感謝してみてはどうでしょうか。それはきっと、一緒にいる家族にはじまり、様々な人への感謝の気持ちにつながっていくに違いありません。家族の愛情や、人と人とのつながりなどは目に見えず、気付きにくいものです。ましてや私達はあわただしい世の中で生活しています。だからこそ、心静かに自らを省みる時間と場所が必要なのです。
お盆にお仏壇やお墓、納骨堂などにお参りすることは、仏様からそういう機会を与えていただいていることにもなるのです。それを、仏様になられたご先祖からいただいたご縁と喜べたなら、暑い中お参りに行くのも楽しみとなることでしょう。
正信偈(その5)
2006年7月
如来所以興出世
唯説弥陀本願海
五濁悪時郡生海
応信如来如実言
釈迦如来が、この世にお出ましになったのは
ただ阿弥陀如来の本願(第十八願)をお説きになるためで
ご濁悪時の世にある一切の人びとは
釈迦如来の真実のお言葉を信じるがよい
【まことの教えを説くために】
お釈迦さまは人間の「苦」を解決するために修行に入られ、覚をひらいて「覚者」(覚れる者)となられました。覚者を「仏」「仏陀」と呼び「如来」とも呼びます。
お釈迦さまのお説法を、お弟子さん達が文字に書き残したのが「お経」です。
阿弥陀さま(如来)について、お釈迦さまは「人々を救い、まことの利益を恵むためにこの世に現れた」と『無量寿経』の中でおしゃっています。つまり、人として生まれたお釈迦さまは、みずから覚りをひらいて正しい道理「真理」をあきらかにされ「お経」として私達にお説きくださったのです。
親鸞聖人は、お釈迦さまがこの世に現れた意義は、阿弥陀さまの教えを説かれるところにこそあると受けとめておられました。そこでさらに親鸞聖人は、お釈迦さまだけでなく、他の色々な仏さまも阿弥陀さまの教えを説くことにこそ出現される意義があることを示そうとされたと考えられます。つまり、色々な如来(仏)が世に現れるのは、阿弥陀さまの教えを説くためであり、お釈迦さまはその中のお一人であって五濁の世(汚れきった世の中)に阿弥陀さまの教えを説くためにお生まれになったのだから、世の人びとはお釈迦さまのまことの教えである、阿弥陀さまの誓いを信じるがよいと述べられているのです。
人としてこの世に生まれて、阿弥陀さまの誓いを説いて下さった、お釈迦さまに対する親鸞聖人のあつい思いをこの句から味わわせていただきましょう。
正信偈(その4)
2006年6月
本願名号正定業
至心信楽願為因
成等覚証大涅槃
必至滅度願成就
本願の名号は、正しく浄土往生が決定する業因ですから
お名号をいただく信心によって、私は救われるのです
この世で仏になるべき身に定まり、お浄土で覚りをひらくのは
かならず成仏させるという、仏の願いが完成したからです
「本願」とは、ひろく言えば阿弥陀如来の四十八の誓い(願)全体を指しますが、親鸞聖人は、第十八願こそが本願、つまり阿弥陀如来の根本をなす願だと教えて下さっています。第十八願では次のように説かれています。「たとえわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、わが国に生ぜんとおもいて、乃至十念せん。もし生ぜずば、正覚を取らじ、ただ五逆と誹謗正法とをば除く」
あらゆる人びと(十方の衆生)がまごごろから(至心)往生しようとおもって(欲生)信じよろこぶようになり(信楽)お念仏を申し、わが国(お浄土)に生まれることができなかったら、私は正覚をひらかない。ただ、五逆の罪を犯した者と、正しい仏法の教えをそしる(誹謗)者は除くというのです。
つまり第十八願では、すべての人々が阿弥陀如来のおおせをまごころから信順し、お念仏をよろこばねば覚りをひらかないと誓われているのです。ですから、ここでもっとも大切なことは「至心信楽」です。「至心」とは「まごころ」と訳されたり、「信楽」をさらにつよめる言葉とも解釈されます。「信」は「信心」です。名号のいわれを聞き、仏さまの救いを疑うことなく信順し、一切を仏さまの救いにおまかせするということです。「楽」は、この信心による満ちたりたよろこびということです。
この言葉の中に、真宗の教えが凝縮されています。ですから「本願」たる「第十八願」を「至心信楽の願」といわれるのです。
私がはからう、私がこうする、私がこう考える、私が信じるのではなく、仏さまにすべておまかせするのが「信心」です。ですから「南無阿弥陀仏」の名号をおとなえするのは、お救い下さる仏さまへの感謝と、よろこびのお念仏となります。
【「正信偈もの知り帳」 野々村智剣 師 参照】
正信偈(その3)
2006年5月
普放無量無辺光
無碍無対光炎王
清浄歓喜智慧光
不断難思無称光
超日月光照塵刹
一切群生蒙光照
阿弥陀如来のあまねく放たれる「量りない光」「辺なき光」
「何ものにも碍げられない光」「対なき光」「もっとさかんな光」
「清浄な光」「歓喜の光」「智慧の光」
「断えることのない光」「思いはかり難い光」「称えつくせぬ光」
「太陽や月を超えた光」を放ち、数え切れない世界を照らし
すべてのいのちあるものが、この光明に照らされている
阿弥陀様にそなわっている、迷いの闇を破し真理をあらわす智慧『光明』を、親鸞聖人は上記の六句をもって示されました。
ここで親鸞聖人は、阿弥陀様の『光明(働き)』を十二の面からほめたたえられ、それは『十二光』と表現されています。光には様々な働きがあり、それは命を「育てる光」、曇天の空を破って「明るく照らす光」あらゆるものを「温かくつつむ光」などがあります。そうした光の中にたたずんでいると、それは阿弥陀様のさとりの徳や私達を救う働きが「光」で表現されることもうなずけるのではないでしょうか。頑なな私がいつの間にか手を合わす身に「育てられ」煩悩に振り回されて先の見えない暗闇が確かな灯火に破られて「明るく照らされ」くじけて立ち止まっていた背中が「温かくつつまれて」勇気づけられる事などが、光に譬えられる阿弥陀様の働きなのです。
ここで示されている十二の面からの阿弥陀様の働き『十二光』の中で、親鸞聖人は唯信坊という方にあてたお手紙(御消息)の中で、『十二光』を統括するものは『無碍光』であるとおっしゃっております。「無碍」の「碍」とは"さわり、さまたげ、邪魔"という意味ですから、「無碍光」とは、どんなものにもさまたげられることのない光ということです。
親鸞聖人は、私達凡夫を救済する阿弥陀様の働きが「無碍光仏」の名によってもっともよく表現されるのであると述べられています。これは阿弥陀様の働き『光明』があらゆる世界の隅々まで至りとどいて、広くすべての国々を照らし、何ものにもさまたげられることなく、すべての衆生(いきとし生けるもの全て)は、その『光明』に照らされて分け隔てなく救われるという意味が示されているのです。
また、阿弥陀様の木像や絵像の背後から放たれている光の数は、ここでの『十二光』の倍数、四十八でありこの四十八筋の光明は、『十二光』が四方に放たれていることを表しているのです。
日ごろ浄土真宗の方々がなれ親しんでいる正信偈のお勤めは、この『十二光』のお徳をたたえられたものの一部なのです。
正信偈(その2)
2006年4月
法蔵菩薩因位時
在世自在王仏所
覩見諸仏浄土因
国土人天之善悪
建立無上殊勝願
超発希有大弘誓
五劫思惟之摂受
重誓名声聞十方
阿弥陀如来が法蔵菩薩と名のられていたとき
師の世自在王仏のみもと(所)にあられて
諸仏の浄土の建立のいわれや、そこにどうしたら往生できるか
また、その国土のありさまとそこに往生している人びとの善悪を観察され
このうえもないすぐれた願をおたてになり
いまだかつてなかったすぐれて大きい誓いをおこされました
そして五劫という長い時間、思惟をかさねておさめとり
かさねて名号を十方に聞かせて救う、と誓われました
阿弥陀如来は、いわゆる「仏」になる前は、法蔵という名前の菩薩として修行されていました。法蔵菩薩は師仏である世自在王仏のみもとで、善悪を問わず、どのような人々をも救うという、すぐれた大きい誓い(四十八願)を建てられたのです。それは、仏様がつくられた浄土の長所、短所や往生の因をよくよく見られ、そこに往生している人の善悪を見られたうえでのものでした。今日の商業界でいえば、徹底したマーケットリサーチを行って、消費者のニーズをさぐるということになるのでしょうか。いずれにしても、真に人々が救われる道は何かということを究明されたのです。つまり法蔵菩薩は「五劫」という気が遠くなるような、長い時間をかけて考え抜かれ、四十八の誓いを建てられたのです。
「劫」というのは時間の単位で、いろいろな解釈がありますが、私たちがもっとも親しんでいるのは、大きな岩がすりへってしまう時間を単位としてはかることでしょう。四十里四方の大きな岩があり、その上に三年に一度、天女が舞い降りてきます。その時、軽い天女の羽衣と岩がこすれて、確実に岩の表面はすりへります。この四十里四方の岩が三年に一度、天女の羽衣との摩擦で全てなくなってしまうまでの期間、それが一劫なのです。法蔵菩薩が誓いを建てられてから五劫という長い間、考えに考え抜かれた時間は、こういう想像を絶する時間でした。言い換えますと、この時間の長さは、私達凡夫を救う大変さを表し、そのまま私達凡夫の罪の深さであるのではないでしょうか。
「南無阿弥陀仏」は名号ともいい、阿弥陀如来に対する信心も、信心の人を救う法も共にそなわった完成された言葉ですそれは「おまえたちを必ず救いとるぞ」という、たのもしい如来様の言葉、働きであり、私が「南無阿弥陀仏」と称えることは「阿弥陀仏におまかせ(南無)します」との表明なのです。
「南無阿弥陀仏」という名号を、法蔵菩薩が長い修行の末、浄土へ救いとる言葉として与えて下さらなければ、私達は生涯一度も「南無阿弥陀仏」という言葉を称える事はないでしょう。そんな言葉も阿弥陀仏の浄土の存在すら知らずに生涯を閉じ、煩悩にまみれて救われることなく死んで行くのです。
「南無阿弥陀仏」の名号は、私を救いとってくれる言葉だという、いわれを知りながらも「本当だろうか」と疑ってばかりいるような私だからこそ「南無阿弥陀仏」なのだと味わわせていただくばかりです。
【「正信偈もの知り帳」 野々村智剣 師 参照 】
正信偈
2006年3月
お正信偈の最初に親鸞聖人の信心告白・宣言が行われています。
帰命無量寿如来 かぎりなき「いのち」の如来に帰依し
南無不可思議光 かぎりなき「ひかり」の如来に南無したてまつります
「帰命」と「南無」は同じ意味で、心から敬い信じますという意味です。「無量寿如来」とは無限の寿命と無限の智慧を持つ阿弥陀様のことを意味します。そして「不可思議光」とは、思いはかることのできない智慧の光で、ことごとく闇をくだいてあらゆるものを照らしてお救い下さる、これもまた阿弥陀様のことを意味しています。
この親鸞聖人の告白を示すこんなお話があります。
ある満員電車の中で小さな女の子が突然大声で「お母さん」と泣きだしました。すると間髪をいれずに、混雑する車両のなかほどから「お母さんはここよ!」としっかりした声がかえってきました。その声を聞いて、女の子はさきほどの不安も忘れたようにケロッとして、外の景色をながめだしました。遊園地がある路線で、車内はほとんどが親子づれであり「お母さん」と呼ばれる人は多数いたのですが、その子のお母さんひとりが、間違いなく応答してくれたのでした。それはまさしく「私だけのお母さん」だったからです。
お経には数々の仏様について説かれていますが、その数々の仏様の中から親鸞聖人がたった1人の「私のお母さん!」と呼びかけられたのが阿弥陀様でした。「正信偈」はそういう親鸞聖人の呼びかけからはじまっています。「帰命」も「南無」も、ともに『おまかせします』という言葉であり親鸞聖人の阿弥陀様にすべておまかせしますという信心の決意表明に他なりません。満員電車の混雑で、お母さんの姿が見えない子供が発した「お母さん」という叫びに対して「ここだよ」とこたえてくれた母親の声は、煩悩のなかにまどう私に、安心しなさいよという、阿弥陀様の呼びかけと同じものだったのです。それだけではありません。この「お母さん」という呼びかけはお母さん自身から教えていただいたものなのです。
信心正因
2006年2月
《歎異抄第1条》
弥陀の誓願不思議にたすけまゐらせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあづけしめたまふなり。
【意訳】阿弥陀仏の誓願の不可思議なはたらきにお救いいただいて、必ず浄土に往生するのであると信じて、念仏を称えようという思いがおこるとき、ただちに阿弥陀仏はその光明の中に摂め取って決して捨てないという利益をお与えくださるのです。
浄土真宗は阿弥陀如来の本願をよりどころとして、南無阿弥陀仏の本願のはたらきによって、信心をめぐまれ、私が浄土に往生して仏に成る教えであります。
私たちは日頃、多くの「いのち」に生かされて生きているということを忘れ、自分の都合だけで周りの「いのち」を利用したり、また邪魔にして「物」とか「道具」のように扱い、思うようにならないと責め、自分の都合が悪くなると責任のがれをして逃げまわるような生活をしているのが現実ではないでしょうか。
阿弥陀如来はこのような私たちを罪悪深重、煩悩熾盛の衆生と示され、あわれに思い、いつでもどこでも見護ってくださっております。それは、老いも若きも善人も悪人も生きとし生けるもの全てを分けへだてなく必ず救う願いです。
その阿弥陀如来の願いには『わたしの救いを疑いなく信じ、必ず浄土に生まれると思い、念仏しておくれ』と呼びかけられ『それで、もし全ての人が1人でも救われなかったら私は仏となりません』と力強く誓われました。
親鸞聖人は「信心は人間の欲望によって造るのではなく、仏の心(本願)を聞きひらき、本願を信じ念仏することである」と説かれ、この「信心」も「念仏」も「成仏」も、すべて阿弥陀如来のはたらきによることを明らかにしてくださいました。そして阿弥陀如来からいただいた信心こそが、浄土に往生して仏に成ることのできる正因(正しい原因)であると説かれ、これを信心正因といい浄土真宗の教えの要であります。
歎異抄は浄土真宗の教えをわかりやすく書かれたお聖教です。歎異抄を通して親鸞聖人のお心を味わい、混迷する現代社会の問題に立ち向かい、乗り越えていく力を一緒に育んでまいりましょう。
お祈りいらずのお念仏
2006年1月
お正月の三が日が過ぎると、テレビで初詣番付の発表ニュースがよく流れます。そして、その番付の中には浄土真宗の本山である本願寺は見あたりません。では、番付に登場する神社仏閣は、なぜ多くの人が訪れるのでしょうか?
ニュースで放映されている映像を見ていると、大きく「家内安全」「合格祈願」「商売繁盛」などと、赤い太字で書かれた看板が門前を彩っています。多くの人が初詣をして、これらの看板に掲げられていることを祈願しているのでしょう。そこで求められている幸せは、一般的には当たり前のことと思われがちですが、浄土真宗の教えから見てみると、その幸せはあらためて考えねばなりません。
それは、これらの祈願の根本にあるものは自己中心的な欲望にほかならないからなのです。例えば、健康でありたいとの祈りも、つき詰めれば、自分だけ健康でいたいということです。入学試験に合格すれば嬉しいですが、それも不合格の人の悲しみを踏み台にした幸福への祈りと、他人の不幸が前提となってしまいます。これが祈願の裏に隠された真実です。そこまでは言わないにしても自分に都合のいい欲望を満たすための手段として祈願という行為が行われていることはいなめません。でも本当に神仏がこういった個人的な都合のいい欲望を聞き、満たしてくれるものなのでしょうか。
親鸞聖人は現世の祈りを否定されて、次の和讃をお読みになりました。
『仏号むねと修すれども 現世を祈る行者をば これも雑修となづけてぞ 千中無一ときらはるる』
このご和讃を味わいますと「たとえ千人がお念仏していても、神社仏閣などで現世を祈るならば、お念仏を申しても、それは自分自身のためだけの念仏だから、お浄土に生まれることはかなわない」とおっしゃいました。
阿弥陀様の願いには自己中心性はかけらもありません。その願いを疑いなく受け入れた心にはまた、自己中心性はありません。「祈る必要などない、何も加えることなく、何も付け足さず、お念仏のままにいただきなさい。」と親鸞聖人の声が和讃から聞こえてくるようです。
本年も皆様と共々に親鸞聖人のお言葉に耳を傾けてまいりましょう。
年の初めの目出度さは
占いクジではわからない
お念仏は空クジなしで
みんな お浄土があたるよ
| << 次号 | 前号 >> |
|---|