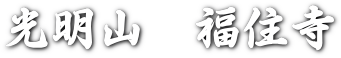月報「なむ」
2005年
報恩感謝の合掌に たたる先祖の霊はない 占いまじない無用なり
2005年12月
【門徒もの知らず】
「門徒もの知らず」という言葉を辞書で調べますと「門徒宗徒が弥陀ばかりを頼んで他を顧みないのをあざけっていう語」とあります。この言葉の語源は「門徒もの忌み知らず」ということです。「もの忌み」とは「迷信」のことですから「もの忌み知らず」というのは「迷信に関心が無い」ということです。しかし今日、門徒のあいだにも「もの忌み」が盛んです。
「もの忌み」とはどのようなものがあるでしょうか。まずは、日の善し悪しである、「大安」とか「仏滅」など、いわゆる「六曜」があります。結婚式や起工式などの日取りには「大安」が喜ばれ「仏滅」は避けられます。葬式には「友引」を避ける風習があり、多くの火葬場では、その日を休日にしております。また、病院の病室番号やホテル、マンションの部屋番号などに「4」や「9」などの数字が無いのをよく見かけます。これは言うまでもなく「4」は「死」に通ずる「9」は「苦」に通ずるという語呂合わせからきたものでしょう。これらの事は、少し考えればすぐに分かる事だと思います。例えば、ほとんどの結婚式が「大安」を選んで行われていますが、必ずしもその全ての夫婦が幸せになっているとは限らないでしょう。また数字の「4」が「死」に通ずるとも思えません。日本には、このような「語呂合わせ」から生まれた迷信がたくさんあり、その他「方角」「墓相」「家相」「姓名判断」など様々な「迷信」や「俗信」があります。
親鸞聖人は悲歎和讃に『かなしきかなや道俗の良時、吉日えらばしめ、天神、地祗をあがめつつ、卜占祭祀つとめとす』と詠まれ、世間の僧侶と俗人が吉凶の占いや世俗の神事に惑わされている事を悲しみ歎いておられます。そして浄土真宗では現世祈祷を行わない特徴があります。現世祈祷とは、人間の祈りの心や信心によって、現世の福利を求めることです。神仏を信心すれば病気が治るとか、商売が繁盛するとか、災難は除かれるなど、福利を求めるところに現世祈祷の誤りがあると言われております。
私達真宗門徒は、聞法を通してこそ、これらの理由のない日の善し悪しや方角の善し悪しを問題にせず、諸神他仏をまつらず、霊や魔がたたるわけもなく、厄払いや祈願祈祷、占い等に頼らず、何ものにも妨げられない念仏者としての道を歩み、現実を見つめ自信をもって明るく日々を大切に生きることができるのではないでしょうか。胸を張って「門徒もの知らず」の生き方に勤しみましょう。
永代経って、どんなお経?
2005年11月
多くの真宗寺院では毎年、春秋2回の永代経法要が勤められます。
「永代経」といえば、みなさんも良く聞かれる言葉だと思います。そういう名前のお経がある訳ではありません。これは永代読経と言うことで「末永く代々に渡ってお勤めする」と言う意味を持っています。別の呼び方をすると「永代祠堂経」とも言われます。祠堂とは何かをご安置するお堂と言う意味で、簡単に言えばお寺の本堂です。浄土真宗のお寺の本堂には阿弥陀様がご安置されているので、祠堂(本堂)は仏法を聞かせ頂く聴聞の場所、すなわち阿弥陀様の願いを聞かせて頂く所ということになります。永代経の「永代」とは「聴聞の場所が永代にわたって維持されるように」という意味で、別の言い方をすれば 今を生きている私達が後に続く子孫に「大切な聴聞の場を守り伝えていく」と言う願いの中から勤められる法要なのです。したがって、永代経法要は福住寺の本堂で勤めるご法事です。私達真宗門徒にとっての永代経とは「念仏道場たるお寺で、故人や代々のご先祖があじわってこられたお念仏を永代にわたって存続し、み教えが伝わっていくように」との願いが込められた大切なものであり、故人を偲び先祖に感謝しそれを機縁として今を生きている私達が、仏法に出遇わせていただく大切な法要、それが「永代経法要」なのです。
先祖のおかげで わたしの「いのち」がある
社会のおかげで わたしの「暮らし」がある
お念仏のおかげで わたしの「喜び」がある
信心
2005年10月
【御文章 聖人一流章】
聖人一流の御勧化のおもむきは・信心をもって本とせられ候、そのゆえは・もろもろの雑行をなげすてて・一心に弥陀に帰命すれば、不可思議の願力として・仏のかたより往生は治定せしめたまう、その位を・一念発起入正定之聚とも釈し、そのうえの称名念仏は・如来わが往生を定めたまいし、御恩報尽の念仏と・こころうべきなり、あなかしこあなかしこ
【聖人一流章の大意】
親鸞聖人のひらかれた浄土真宗のみ教えでは、信心が根本です。そのわけは、自力のはからいを捨て、一心に阿弥陀如来に帰命すれば、思いも及ばないすぐれた本願のはたらきによって、如来が私たちを必ず浄土に往生する身にして下さるのです。
往生が定まったその位を、「一念発起入正定之聚」といい、お念仏一つ、信心一つで救われ、次生必ず悟りを開く身に確定したものの仲間に入ると示されています。そして信心を得た後に称える念仏は、如来が私の往生を定めてくださったご恩を報じる念仏であると心得るべきです。
「私は不信心なもので・・・」とよく耳にします。お寺の法座などへ行く事が出来ない理由にする方がいますけれども、自分が信じる心を持っているか、持っていないかなど、欲望やはからいによって、こしらえた信心を「自力の信心」といいます。人間の迷いの心は変わるものであり、自分の力で信心を継続しようとすると、大変な修行や苦労が必要となり非常に難しい事であります。
それに対して「他力の信心」は、仏様よりいただく信心の事で、変わることのない仏様のお心をそのままいただくのですから、何の問題もなく易しい事ではないでしょうか。親鸞聖人はこれを「真実信心」と言われ、これこそ煩悩具足の凡夫が浄土に往生する因であると示されました。
それではどのように仏様のお心をいただき、誰がそれを証明してくれるのでしょうか。信心をいただく事を「獲信」と言いますが、そのためには聞法よりほかの道はありません。聞法とは仏様の教えを聞信する事によって信心を決定することです。現実に信心決定するには、お寺の法座などで聴聞を重ね、仏様のお心を知り、それに対して信じる心のおこる時、疑いの心のなくなった時となります。そして私の口から自然にお念仏の声となって現れてくださる仏様がそれを証明して下さるのではないでしょうか。
親鸞聖人は、信心を「たのむ」とか「まかせる」という言葉で表現されております。そして「生ける時も、老いゆく時も、病める時も、死にゆく時も、あなたの人生すべてを私にまかせなさい、必ず救ってあげます」この仏様のお心のままにおまかせするならば、即座にお救いにあずかり、必ず浄土に往生する身にして下さることを「信心の定まるとき、往生また定まるなり」と示されました。
報恩講とかぼちゃ様
2005年9月
全国二万ヶ寺をこえる真宗寺院最大の行事が、報恩講です。報恩講は私達にみ教えを伝えて下さった親鸞聖人の御苦労を偲び、その御恩に感謝する大切な法要です。
昔、「報恩講さんは半年がかり」という話があります。そのころほとんどの家が、野菜を自給自足していました。菜っ葉類の他、根菜もつくっており、とりわけゴボウなどは、かなり高く土を盛って周囲を板で囲った畝をこしらえなければなりません。ある家で、それまでよりゴボウの畝が増えました。すると近所の人は「ああ、この家は今年おめでたか」と悟ったといいます。おめでたがあると家族が増え、家族が増えると報恩講に参る人が増え、お斎に欠かせないゴボウをまず多く植えておかなければいけないからです。このように報恩講は土の上に絵を描くような営みであったわけです。半年がかりで報恩講の支度をする人々の姿は、今の私達には残念ながら、なかなか実感がわいてこなくなってきました。大気汚染、森林資源の乱用など、今地球の荒廃が人類的問題となっています。私達の生活の中に、いつの間にか自然との関わりや一体感が失われてしまったからではないでしょうか。私達の「いのち」は一粒のお米、一個のトマト、一本の胡瓜、その他たくさんの「いのち」によって支えられているのだということの有り難さを伴に確かめ合い、伝えていかなければならないのです。
こんな詩があります。
六日夜
かぼちゃの切り目が三片出た
おいしかった
自然の恵みにみちた南瓜
仏さまの願いのあふれた薬であったのだ
光って見えた
「かぼちゃさま」と拝んでいただいた
様々な動物や植物の「いのち」をいただいて、生かせていただいていることへの感謝の心を報恩講を迎えるにあたって、あらためて確かめるための「感謝の日」としてみなさんでお参りいたしましょう。
盂蘭盆会
2005年8月
他人同志はもちろん、親子のつながりも希薄になってきたと指摘される昨今ですが、まだまだお盆には里帰りをして家族大勢で過ごす人たちが大半ではないかと思います。私達はあわただしい世間の中に生きています。今大切な事は、お盆のご縁に皆様そろってお仏壇に手を合わせ、心静かに自らを省みる時間と場所が必要なのではないでしょうか。
「盂蘭盆会」とはサンスクリット語のウラバンナ(逆さ吊り)を漢字で音写したもので「逆さに吊り下げるような苦しみに遭っている人を救う法要」という意味になります。そして「仏説盂蘭盆経」というお経の中に次のようなお話が説かれています。
お釈迦様の弟子である目連尊者はある時、神通力によって亡き母が餓鬼道におち、倒懸(逆さ吊り)の苦しみを受けていることを知りました。そこでどうしたら母を救えるか、お釈迦様に相談しました。するとお釈迦様は「雨期の三ヶ月の修行(安居)の最後の日(7月15日・自恣の日)に仏と僧に多くの供物をささげ供養しなさい。そうすれば七代前までの父母の苦しみを救う事ができます」とお答えになりました。早速、目連尊者は教えを実行し、お母さんはその功徳によって極楽往生が遂げられたとのことです。それ以来(旧暦)7月15日は父母や先祖に報恩感謝をささげる重要な日となりました。これがお盆の始まりであります。
浄土真宗では、お盆に死者の霊を迎える様々な準備は必要ありません。なぜなら「あなたが死んだら必ず浄土へ迎え摂って仏する」と誓われ喚んで下さる南無阿弥陀仏のはたらきによってお浄土へ帰っていく教えです。先立った人は私をお浄土へ導こうと、はたらいて下さっております。仏となられた方への接待は、そのはたらきを褒め讃えることでしかありません。これがお勤めです。お勤めがそのまま私をお浄土へ導こうとする働きそのものです。ですから、迎え火、送り火などの霊が来たり帰ったりということはありません。
お盆には家族皆様でお仏壇に手を合わせ、今の自分があるのも、ご先祖様のお陰であることを味わい、ご恩を偲び、はたらきに感謝するご縁でお念仏を申させて頂きましょう。
お仏壇のお荘厳は法事に準じた形で、前卓には打敷を掛け、お供え物は餅、菓子、果物の順番で派手に飾り立てるのではなく、整然と供えるように心がけましょう。
できることからはじめよう
2005年7月
【ビハーラ】
”老・病・死”それは避けがたい人生の真実であります。万人が体験し、苦悩していかねばならない事ではありますが、その苦悩は「わたくしひとり」のものでもあります。すべてのひとの苦悩でありながら、しかも代ってもらえることのない私ひとりの深い苦悩でもあるのです。
高齢化社会、長寿社会といわれる現代は、これらの苦悩を解決するというよりは、むしろ解決を急ぐ課題として私たちに迫ってきているといえないでしょうか。
効率やスピードが価値のあるものとして尊重される風潮は、それらについていけない「いのち」を無価値なものとして切り捨てていきます。
「私も精いっぱい生きている人間だ」「私は病気を持った臓器ではなく、喜びも悲しみもあるこころを持った人間だ」「私にとって私のいのちは、かけがえのない私一人のいのちなんだ」年老いた人、病を得た人のうめきや悲鳴が、至るところから聞こえてくるようであります。仏教はそれらの人びとの苦悩とともにあります。
”ビハーラ”サンスクリット語で休憩の場所、転じて僧院、寺院という意味があります。現代の寺院が、人びとの身も心も安んじる場所になっているかどうかと思うとき、少なからず懺悔の思いにかられない訳にはいきません。
ビハーラの理念については
1、 限りある生命の、その限りの短さを知らされた人が、静かに自分を見つめ、見守られる場である。
2、 本人の願いを軸に、看取りと医療が行われる場である。そのために充分な医療が可能な医療機関に直結している必要がある。
3、 願われた生命の尊さに気づかされた人が集う、仏教を基盤とした小さな共同体である。
ビハーラ活動は、布教伝道を第一義とする場ではありません。いのちに向き合っている病人や老人とともに、そのかかえている苦悩と不安を見つめながら、苦悩と不安を超えていく、いのち輝く道を、ともに歩もうとする活動であります。
いつでも、どこでも、いのちある全てのものを、必ずお救い下さる方が、「阿弥陀如来」さまです。曇鸞大師は「己を外にする」如来さまであると示されました。私たちは己を先として、他の人を後回しにするために、争いや対立が絶えません。如来さまは「己を後にして衆生を先とする」とご苦労くださり、私のところに「南無阿弥陀仏」となって、いつも喚びつづけてくださっています。
聞法者として「まことのこころ」に遇う私たちは、自他の対立を超えて、社会の人々とともに生き、ともに歩き、ともに共感できる人生でありたいと思います。
家庭の平和は 互いの立場を 尊重するところから生まれる
2005年6月
【仏前結婚式】
人間関係の中で夫婦ほど重要なものはありません。親子も友人も大切でありますが、男と女が出会い結ばれて子供を産む、ということが人類の根源となっていて、もしも男女がいなければ、家庭も親子もなく、人類も社会も存在しないでしょう。形の上では結婚、出産ですが、心の上では男女の恋、夫婦愛、親子愛ということで、人と人とのつながりが基本となっているのであります。
例えば夫が病床に臥し、妻が添い寝で看病して夫の病気を悲しみ、家族の行く末を案じてしみじみと泣く妻を見れば、夫や妻や家族の為に、今しばらく生きてやりたいと願わずにはおれません。病む夫をいたわり泣く妻をなぐさめたいという夫婦愛は、この上もなく美しく尊いと思います。
結婚生活は、いろいろな苦難を避けて過ごすわけにはいきません。どのような事があっても、変わらない愛情を持ちつづけるには、お互いが思いやりをもち尊敬しあう事が何よりも大切な事ではないでしょうか。
親鸞聖人は、越後の国で九歳年下の恵信尼さまと結婚され、その生活を送る中でお念仏を喜ばれながら、力強く生き抜かれました。
聖人御夫婦の愛情は、お互いが尊敬しあい、信じあわれることによってもたらされ、これこそ真の愛情の交流と言えるのではないでしょうか。
今日、仏式で結婚式を行う人は、少数でありますが、最近増えつつあります。結婚式というのは、不思議なご縁があってめぐり会い結ばれた二人が新たな人生を歩む出発点となる大切な儀式です。単なる感覚的な印象や雰囲気ではなく、二人の人生の依り所となるしっかりとした基盤のもとに執り行う必要があるのではないでしょうか。
仏前結婚式ではそうした二人の精神的依り所となって下さる如来さまの尊前で二人が出会った因縁の尊さを味わい、お互いの理解と尊敬と責任のもとに生きることを仏祖にご奉告し、慈悲の光に包まれて、敬愛和合の日暮らしを誓い合うものであります。
仏教では「袖振り合うも他生の縁」といい、夫婦や親子の縁が仮初めのものではなく、深い因縁によって結ばれたことを説き、親鸞さまの教えでは、結婚を人倫の基礎とし、妻子を捨てる出家よりも、在家のままで夫婦家族が共にお念仏を頂くことを奨めております。
親に抱かれた赤ん坊 これ以上の信頼はありません
2005年5月
私達が生まれたとき、両親、祖父母などに名前をつけてもらいます。それには健康であってほしい、幸せであってほしい、賢くなってほしいなど、たくさんの願いがこめられています。親はみな、我が子に大きな願いを持ち、その願いを果たすためにいろいろ考え努力します。しかしその願い通りに育てることは難しく、なかなか思うようには育たないことが多いようです。
一本の花を育てる時も、それを育てる土壌からつくらなければ、自分の思うような花には育ちません。それと同じように子を育てるにも、土壌となる家庭づくりが大切なのではないでしょうか。
一般に教育という言葉には、教と育の二つの意味があります。教は文字通り「教える」ということであり、知識を与えることでもあります。そして育は「育てる」ことです。「育てる」とは、子の中にあるものを引き出し、それをはぐくみ伸ばしていくということであります。知識を与えることはできても、その子の中にある可能性を見抜き、引き出しはぐくむことは大変難しいことです。
子に向かって「勉強しなさい」と口癖のように言うお母さんが多いようですが、自分が全く勉強しようとしないで、いくら子に向かって「勉強しなさい」とくり返しても、勉強好きな子が育つことは難しいようです。
「子は親の後ろ姿を見て育つ」とよく言われます。子は何も見ていないようですが、子の眼は非常に鋭く親のすること、考えていることを見抜いています。子を育てるとはまず、育てる親の成長し育つことによって、子も育つのではないでしょうか。
我が子に大きな願いを持ち、それを果たすために、いろいろ考え努力すると同じように、仏様は私達人間に対して大きな願いがあります。この仏様のお心を聞き続けることで、私に心のゆとり、大きな安らぎ、人生を生きる勇気が与えられます。それは「顔や形、性格はみんな違っていても、ひとりひとりがそれぞれのいのちを精いっぱい輝かしてくれよ。人と違っていることで悲しんだり、淋しがったりくじけてはいけないよ、たとえくじけそうになっても、私がちゃんとついているから安心して精いっぱい元気を出して生きてくださいよ」という願いです。仏様の願いの中に、私が生かされ、必ず救われていくことを味わい、ともにお念仏させていただきましょう。
法名
2005年4月
法名は「死んでからの名前」ではありません。浄土真宗本願寺派では、僧侶なら「得度式」で、また門信徒は「帰敬式」で、ご門主さまのお導きにより、おかみそりをうけ法名をいただきます。帰敬式とは、み仏や宗祖親鸞聖人のみ教えに帰依することを誓う儀式で「おかみそり」とも言います。また通常、法名は親鸞聖人のお名前が二文字であることに準じて二文字の漢字であらわされ、その上には必ず「釈」の字がつきます。これは「お釈迦さまの一族にならせていただいた」という意味になります。
生前「おかみそり」を受ける機会がないままに亡くなったひとには、葬儀に先立って住職が、ご門主に代わって「おかみそり」を行い、法名を授けます。これは「いまから仏弟子の葬儀を行うぞ」という宣言であるといえるでしょう。
仏教諸派の中には、不殺生(生き物を殺さない)・不偸盗(盗みをしない)・不邪淫(淫らなことをしない)・不妄語(うそをつかない)・不飲酒(酒を飲まない)などの仏道修行の基礎である戒律を守ることを条件として戒名を授けます。しかし、浄土真宗では自分の力で励む行や戒律を必要とせず、阿弥陀如来のご本願を信じて仏にならせていただく教えですので、受戒をしません。ですから戒名ではなく法名といいます。
居士・信士・信女などは、在家の生存中の信者を意味する言葉ですので、すでにお浄土に生まれて仏となった人の法名には必要ありません。
なお、院号というのは法名の上に付けられる称号であり、宗門の護持発展につくされた方に対して、本山(本願寺)より与えられるものであります。
法名をいただくということは、これからの人生を仏弟子として、仏法によって生きることをあらわしています。法名は「死んでからの名前」では決してありません。迷信にふりまわされない生き方をこころがけて、まだ法名をいただいていない方は機会があれば、積極的に「おかみそり」を受けるようにいたしましょう。
善人なほもって往生をとぐ、いはんや悪人をや
2005年3月
意: 善人でさえ浄土に往生することができるのです。まして悪人はいうまでもありません。
(歎異抄 第三条)
【悪人主義】
阿弥陀如来の救いの正機(おめあて)は「悪人」であります。私達が普通「悪人」という言葉を耳にしたとき、漠然と世にいう極悪非道の人をイメージとして思い浮かべ、もっと言いますと、自分以外の悪い人を想定して、あのような悪人が救われるのかと、何か不当な事のように思い込みがちです。
ある時には貧欲におぼれ、ある時には憎悪に満ちながらたえずゆれ動き、生きるためにはやむをえないと言って、どれだけ多くの生命を奪っていることでしょう。生きている限り、身を煩わし心を悩ます自己中心的な煩悩の支配から抜け出すことのできないこの私こそが「悪人」なのであります。
わかきとき仏法はたしなめと候ふ
2005年2月
意:仏法は若いうちに心がけて聞きなさい。年を取ると、歩いて法座に行くことも思い通りにならず、法話を聞いていても眠くなってしまうものである。だから若いうちに心がけて聞きなさい。
(蓮如上人一代記聞書)
【年間行事】
2月7・8日及び17・18日 ・・・ 聖典講座(歎異抄)
3月20日 ・・・ 新入学の集い(小学生)
20・21日 ・・・ 春季彼岸会法要
4月 9日〜11日 ・・・ 春季永代経法要
6月 9日 ・・・ 初山式(赤ちゃん初参り)・婦人会報恩講
10日 ・・・ 新門徒の集い・降誕会法要
7月 中旬 ・・・ 特別仏教講演会
8月13日〜16日 ・・・ 盂蘭盆会
16日 ・・・ 初盆会法要
9月 1日〜3日 ・・・ 宗祖聖人報恩講・門信徒展示会・祖師寿
23・24日 ・・・ 秋季彼岸会法要
11月 23日〜25日 ・・・ 秋季永代経法要
12月 31日 ・・・ 真夜中の成人式
念仏者は無碩の一道なり
2005年1月
謹んで新春のお慶び申し上げます。昨年は台風、地震等、自然災害の多い年でありました。被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。新しい年を迎え、皆様と共々にお念仏生活を勤しみましょう。本年も宜しくお願い致します。
【歎異抄】
歎異抄は親鸞聖人の弟子の、唯円が著者であると言われます。唯円は、親鸞聖人より聞かせていただいた言葉をそのまま前半の第一条より第十条までを書き記し、まさに親鸞聖人のお声が今の私達に直接語りかけて下さっている内容となっております。また、後半の第十一条より第十八条までは、お念仏のみ教えを間違ってとらえたさまざまな意見を批判しています。当時、親鸞聖人が往生された後その教えと異なっている教えを説く人達が一層増えたことに対して、唯円は親鸞聖人のみ教えが正しく伝わらないことの異を歎き、お念仏のみ教えに疑いを持たないようにと願われて『歎異抄』と記されました。
表題の言葉より『念仏者は無碍の一道なり。そのいはれいかんとならば、信心の行者には天神、地祗も敬伏し、魔界、外道も障碍することなし。』とあり、意訳は「念仏者は、何ものにもさまたげられないただ一筋の道を歩むものです。それはなぜかというと、阿弥陀仏の本願を信じ念仏する人にはあらゆる天地の神々も尊敬し、悪魔もよこしまな教えを信ずるものも、その歩みをさまたげることはない」となります。本年の当寺カレンダー挿絵にもありますように、私達念仏者を諸天、諸神が敬意を表して守っています。お念仏にいかされている私達は、占い、呪い、日の善し悪しなどの迷信に惑わされることなく、開放的で心豊かなお念仏生活をさせていただけるのです。二月には歎異抄講座もあります。笑顔で新年を迎え本年も皆様と共々に親鸞聖人のお言葉をいただいてまいりましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|