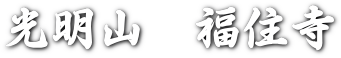月報「なむ」
2004年
門徒の初詣
2004年12月
みほとけの前に 手をあわせた 初めての日に たちかえろう (中西智海)
お正月になると、毎年、おおぜいの方が初詣にでかけます。テレビでは、あちこちの有名な神社の参拝風景を中継し、また、どこそこの神社に何人の参拝者があったかを報道しています。東京では明治神宮、京都では伏見稲荷、大阪では住吉大社といった所が百万人単位の参拝者を集めるようです。これを見ても明らかなように、どうも”初詣”と言えば、神社にお参りする人が圧倒的に多いようですが、当寺では正月一日には元旦会のお勤めをし抽選会などで、新年のお参りをさせていただいております。しかし門徒の方の中には、なぜか神社へお参りされる方がおられるようですが、どういう思いで初詣に出かけるのかと言うと、レジャー気分や雰囲気もあるのでしょうか、その中身は”願い事をする”方も多いのではないかと思われます。「ことし一年健康でありますように」とか「仕事がうまくゆきますように」など、また、若い人の中には「よい結婚相手が見つかりますように」「希望の会社、学校に合格しますように」といった類の願いをかけるのでしょう。
“初詣”という言葉から連想されるのは、以上のように「神社」「願い事」となってきます。しかし、初詣は「新年の初参り」ということですから、やはり、自らの信じるみ教えに則して、その宗教施設にお参りするのが本質であろうと思われます。ご門徒として当然のことながら、所属のお寺にお参りするということです。ともすると、己れの欲望や願いばかりに目がくらみがちな私達です。心改まるお正月なのですから、じっくりと我が身を振り返り、人生にとって何が大切かを見つめ、確かな依りどころとなるお念仏を味わいましょう。それでこそ”門徒の初詣”です。また、元旦の仏壇のお飾りは五具足と打敷、餅を供え家族そろってお参りしましょう。
聞即信
2004年11月
聴聞の心得
この度にこのご縁は初事と思うで聞くべし
我が一人のためと思うて聞くべし
今生最後と思うて聞くべし
浄土真宗は「聞の宗教」であるとよく言われますが、その意味は、浄土真宗は「聞く」に始まり「聞く」に終わるという意味です。
色々疑問もあるでしょうけれども、聞法の場に座わる事から始まるのが浄土真宗なのであります「まず聞く事」をおいて、信心も念仏もあり得ないのですから、浄土真宗は「聞」の宗教であると言われます。
それでは何を聞くのでしょうか。仏説無量寿経に「聞」というのは、『衆生、仏願の生起本末を聞きて疑心あることなし、これを聞といふなり。』(浄土真宗聖典251)とあり、ほとけさまが本願を起こされたわけとその衆生を救う働きを聞き開けば、疑いの心がなくなる。それを「聞」と説かれています。また、一念多念証文には『きくといふは、本願をききて疑う心なきを「聞」といふなり』(浄土真宗聖典678)とあります。私を必ず救うというご本願は決して迷いの世界から解脱できない衆生の為のものであり、その衆生を救う力こそがお念仏であります。また、疑いを抱かないという事は、私達衆生の力は一切役に立たず、阿弥陀仏の救済にまかせきるという事が、ご本願の信心の姿であります。これを聞即信とも言います。
蓮如上人御一代記聞書には「仏法は忙しい世間の仕事を差し置いて聞かねばならぬ。それなのにあなたはひまができたら聞こうと思ってはいないか。それはあさはかな事である。仏法のうえから言えば、老少不定の身であるから明日があると思ってはならない。」とあります。現代は聞く事の非常に難しい時代であります。人間というものは、忙しい時は、文字通り心を失う場合が多く、仏法を聞く心のゆとりさえなく、また、楽しみが多くても仏法を聞くような心のゆとりがなくなるものです。そんなとき、亡き人の法要に出会ってこそ仏法が聞けるのです。亡き人が身を持って示して下さった聞法のご縁を大切にしたいものであります。
読経
2004年10月
「読書百返、意おのずから通ず」
意:いかに難しい書物や文章でも 繰り返し読み続ければ意味は自然にわかってくる
お経は、呪文やまじないではありません。訳の解らない言葉を指して「お経みたい」と言われることがあります。一般に意味不明の難しいこととして受けとめられているようですが、お経はお釈迦様のお説法であり、その数は八万四千もあるといわれています。今から二千数百年前に、この世にお出ましになられたお釈迦様は、出家、修行の末に、永遠の真理に目覚められ、三十五歳の時に仏陀となられました。以来八十歳で入滅されるまで、仏法をお説きになられました。浄土真宗では浄土三部経といわれる「仏説無量寿経」(大経)上下巻、「仏説観無量寿経」(観経)、「仏説阿弥陀経」(小経)を教えの根本をなす教典としていて、いずれも阿弥陀如来のみ教えと、お浄土のすばらしさが説かれ、お念仏をすすめていただいているお経であります。
それではなぜ読経するのでしょうか。「お経は先祖のために称える」と思っている人がいるかもしれませんが、これは間違いであります。浄土真宗で行う読経は故人への追善供養ではありません。阿弥陀如来のお徳を讃え(仏徳讃嘆)、そのご恩に感謝する(報恩感謝)行為なのであります。したがって「読経する」とは、私自身がお念仏のみ教えを聞き慶ぶことであり、如来さまのお徳を讃えて、そのご恩に感謝することであります。誰それのための読経、と言うような「故人のための読経」ではなく、「私自身のための読経」と言えるでしょう。
もうすぐ秋季永代経法要が勤まります。永代経とは「永代読経」の略で「末長く代々にわたってお経が読まれる」という意味です。ですから、「お寺を護持し、いつまでもお念仏の道場としてみ教えが子や孫に受け継がれていくように」という願いがこめられている、大切な法要であります。「み教えを私に伝えて下さったご先祖の遺徳を偲び、私自身が聞法に励んで、その慶びを子や孫に伝えていく」これでこそ永代経といえるのではないでしょうか。
十一月二十三日より二十五日まで秋季永代経法要が厳修されます。お寺の法要へ参拝する折りには経本・念珠を持参するとともに、門徒式章をかけるよう心がけましょう。
ほとけさま
2004年9月
親鸞聖人の開かれた浄土真宗の、み教えでは一口でいうと、すべてを阿弥陀仏にまかせることにあると、いってよいと思います。いったい阿弥陀仏とは、どのような仏なのでしょうか。阿弥陀というのはインドのことばで、限りないとか、量りないという意味です。「仏とは死んだ人のこと」と思っている人がいるかもしれませんが、これは間違いです。仏とは、目覚めたもので自分が目覚めるだけでなく、他のものを目覚めさせることに完全なもの、という意味です。
阿弥陀仏はこの地球上に現れた仏ではありません。この地球上に現れた仏は釈迦牟尼仏だけであり、そのお釈迦様が説かれた沢山の経典の中に出てくるのが阿弥陀仏なのです。その中でも阿弥陀仏について詳しく説かれたのが「仏説無量寿経」(大経)であります。それによると、はてしない昔一人の国王が世自在王仏の説法を聞いて出家を決心し、修行者となって法蔵と名のりました。法蔵は世の苦しみ悩んでいる人々を救いたいという心を興し、立派な浄土を造りたいと思い、誰でもその浄土に生まれることのできる方法について考えました。そして五劫というはてしない長い時間をかけて、それを実現するための四十八の願を建て、「もしこの願いを実現することができなかったならば、自分も仏になるまい」という、誓いを建てました。法蔵は長い長い間修行を積み、ついにその目的を果たして仏となりました。その名を阿弥陀仏といい、それは今から十劫の昔でありましたと、説かれています。阿弥陀仏の本願とは「迷うすべての人々を救わなければ私は仏にならない」と誓われた根本の願いをいいます。これが第十八願です。この完成された救いの働きを「南無阿弥陀仏」という名号として私たちに与えて下さったのです。ですから「南無阿弥陀仏」という名号は、迷いの海に沈んでいる私たちを、お浄土に生まれさせて下さる、阿弥陀仏の救いの働きそのものであります。阿弥陀仏は「われを信じわが名をとなえよかならず浄土往生させるぞ」と働き続けていて下さるほとけさまであります。ほとけさまの本願を信じて念仏する者は、信心をいただいた瞬間に浄土往生が決定するので「後生の一大事」はほとけさまにすべておまかせし、この世のお念仏生活を安心して存分に楽しむ事ができるのです。
九月一日から三日まで宗祖親鸞聖人報恩講、二十三・二十四日秋季彼岸会が修行されます。みなさまご一緒にお参りし、お念仏生活に勤しみましょう。
受け継ぐいのち
2004年8月
人は去っても その人のぬくもりは去らない
人は去っても 拝む掌の中に帰ってくる
人は誰でも生まれ育った、ふるさとを持っています。「三つ子の魂 百まで」というように、私たちは生まれ育ったふるさとの、気候・風土・言語・風俗などを色濃く身につけており、その人の人柄や性格の形成に大きな影響を受けています。それ故、人びとは自分のふるさとに対して独自の思い出や感情を持ち、生涯を通じて、善いにつけ、悪いにつけ、ふるさとを思い出し、なつかしむものではないでしょうか。私が今、人間として生きていることは、何といっても、私の父母なくしては絶対にありえないことであり、もう一代さかのぼりますと、私の父方の祖父母、母方の祖父母があって、そこには四人のご先祖さまが存在するわけであります。このようにして二十代さかのぼりますと、ご先祖さまの数は百万人余りになります。私一人が生まれるのに百万人ものご先祖さまが、いのちを受け継いだということです。
歎異抄の第五章に「一切の有情、みなもって、世々生々の父母兄弟なり」とあり、すべての生あるものの中に、全く他人は一人もいないという、限りなく広い世界が開かれており、ご先祖さまのお蔭で今の私があると味わうことができます。私たちのいのちは、このように恵まれたいのちであります。「人のいのちは地球よりも重い」といわれるのも私たちのいのちには、あらゆるもののいのちがこめられ、それによって支えられているという重みがあるからではないでしょうか。あらゆるいのちなくして、今日の私のいのちはなく、だからこそこの尊いいのちを持って、今を大切に生き、一日一日を悔いのないように生きることが大切なのであります。お盆にはふるさとなどで手を合わせる機会が多くなりますが、先祖の霊に手を合わせることではなく、私自身がお念仏を慶ぶ身となることであり、ご先祖さまの報恩の思いから仏法を聞かせていただき、阿弥陀如来のお力によって救われていく身の幸せを喜ぶことで、ご先祖さまのご恩に報いる道が開けるのではないでしょうか。
初参式
2004年6月
赤ちゃんの誕生は、両親や家族にとって何ものにも代えがたい慶びの一つでしょう。人としてこの世に生を受けることは極めて得難いことであり、不思議としか言いようがありません。このかけがえのない”いのち”がすくすくと育ってくれるように、また人間に生まれた慶びをかみしめつつ人生を力強く歩んでくれるようにと、親なら誰もが願うところです。そうした我が子の人生の出発に当たって、けっして崩れることのない依り所となり、支えとなって下さる如来さまに参拝する式を「初参式」と言います。
初参式は、子にとっての人生の始まりの仏縁ですが、同時に親にとっても、親として生きる出発点であり、子によって与えられた尊い仏縁です。世間では、子が生まれて一ヶ月ほど経つと”お宮参り”といって、神社へお参りする人が多いようですが、残念ながらお寺へお参りする人は限られているのが現状です。日ごろ「私は門徒です」と言っている方でも、なかなかお寺に参ってきて下さいません。これはどうしたことでしょうか。「死に関わる悲しみ事はお寺で、お祝い事はお宮さん」という意識が、人びとの心の奥深くまで浸透している現実に改めて驚かされます。結局ご門徒一人ひとりが聞法に励み、如来さまの深いお慈悲の心に触れることによって自らの人生に目覚めていただく以外にはないのでしょう。ともあれ”死”が大きな仏縁となるのと同様に、”生”もまた尊い大きな仏縁となるのです。どうか初参式を人生にとっての大切な儀式だと心得ていただきますように・・・。
『末本 弘然 著「仏事のイロハ」(本願寺出版社発行)より転載』
無宗教
2004年5月
念佛は「いのちとは何か」という問いであり
「いかに生きるか」という答えであり
「いかに死ぬか」という覚悟である
この頃、「無宗教」を名のる有名人が多く、葬式も音楽葬とか献花葬とか、宗教色をぬきにして行なわれることが増えています。震災後一年の阪神各地で、震災死者の一周忌の行事が行われましたが市や学校などでは、宗教ぬきの慰霊祭が多かったと報じられていました。でも一周忌ということ自体が仏教的ですし、慰霊祭という儀式そのものが神道的な儀礼ですから無宗教とは言えません。要するに神職、僧職ぬきで、祝詞や読経のない儀式ということです。儀式には各宗派の特徴が鮮明ですが宗派(教団)と宗教とは別で、純粋に宗教といえば、いのち・生死をどう理解するかという、生命観・人間観・生死観などの総合的な思想そのものを指すわけですから、いささかでも思想をもつ人びとが、純粋に「無宗教」であることは有り得ない、と思います。むしろ、所属する宗教団体を持たない「無宗派」であるという意味に過ぎないと思います。
さて、お念仏という宗教は、どのような生命観、生死観をもっているか、ということが本章のテーマです。「いのち」とは何かと問いつめれば、いのちが「いかに生きているか」という答えにたどりつき、さらに「いかに死を迎えるか」という覚悟に到達するはずだということです。結論から言いますと、生命は父母を因縁としてこの世に生まれたわたしの「いのち」のことであり、それは久遠(四十億年前)の昔から受けつがれ永遠の未来へと受けつがれてゆく「いのち」の仮の姿であり、自然と仏(真理)によって生かされています。親なしに生れた「いのち」はなく、自然なしで生きることはできませんそれは「生かされて生きている」のです。 個々の生命には寿命(限界)があり、終り(死)がありますが「いのち」そのものは、祖先から子孫に向かって無限の連鎖として受け継がれ個人は死と共に、生命の親里である真理の世界(浄土)へと帰ってゆく、と考えます。その思想の全体が、お念仏であり信心でありますから、無宗派でも念仏者であることに変わりはありません。
杉本顕俊 著 「法語掲示板」(探究社発行)より転載
親友をもっているか
2004年4月
親友は生涯の宝 優しい心でつき合えば
心の親友に会えるかも 念仏者はみな同朋
あなたには誰か「親友」とよべる友だちがいますか。心から信頼して、何でも打ち明けることができる友だち。世界中の人が自分を裏切っても、彼(または彼女)だけは絶対わたしを騙さないと信じられる友だち。もしそんな人がいたら、あなたには最高の宝だと思います 血のつながった親子兄弟姉妹でも、時には信用できないことがあり、長年連れ添った夫婦でも、しばしば嘘をつくことがあります。だからと言って親子や夫婦が互いに疑い合い、いつ裏切られるか知れないと用心しなければならないとしたら、それこそ地獄であり、こんな不幸なことはありません。多少の嘘や誤魔化しはあっても、お互いに寛容の心をもって許し合って生きなければ仕方がないと思います。
近所の人に鬼婆と陰口を言われる怖い姑さんがいました。ある日この姑さんが嫁に向かって大へんな難題をつきつけました。「鬼婆などと人は言うなり」という短歌の下の句を書いて嫁に渡し「これに上の句をつけなさい」というのです。嫁はちょっと考え、さらさらと上の句を書きました「仏にも優る心と知らずして」というのです。二度三度これを読み返していた姑さんが、突然、泣き出し、嫁の手を執って言いました。「かんべんしておくれ。わたしが悪かった。あんたが、こんなにやさしい心を持っているとは知らず、意地悪ばかりしてすまなかった」とさめざめと泣くのでした。その後、人が変わったように優しくなり、近所でも「ほんとうに仲のよい嫁姑だ」と評判になったということです。親友を得るには、まず自分の友を信じ、友に優しい人であること、自分が友を疑う悪友であっては、親友はできません。経にある「善親友」は一般に善知識(よい指導者)のこととされていますが正像末和讃に、「他力の信心うるひとを、うやまひおほきによろこべば、すなわちわが親友ぞと、救主世尊はほめたまふ」と親鸞さまは、他力の信心の人を釈尊が「わが親友」と呼ばれたと示されています。
杉本顕俊師「邦語掲示板」(探究社発行)より転載
彼岸になると
2004年3月
彼岸になると
み仏の私への呼びかけが
寂かに 身に沁みてくる (中西智海)
三月にもなると次第に春めいてきます。冬の厳しい北国はもちろんですが、そうでなくても春は待ちどおしいものです。寒さの実感がないと、春の喜びが少なくなるのは当然でしょう。それと同じように自分の今の心や行いをいいかげんに見ていたのでは、真実のしあわせ、お悟りの彼岸を求め、喜びを迎える気持ちにはなれないでしょう。
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、暑さ寒さという身体の感覚だけで彼岸を考えることはいかがなものでしょうか。人間の肉体的、精神的、対内的、対外的な苦しみやわずらいを超えた彼岸、しかも再びそれらの苦しみや悩みに戻ることのない状態になりきることを願い求めることの大切さを教えるのが彼岸です。
お墓に参るときに、ただ墓石を拝みに行く人はいないでしょうか。お寺やお仏壇に参っても、お仏像の素材である木や紙や布を拝んでいる人はいないでしょうか。それは拝むものではありません。拝むのは仏様です。アミダ様です。アミダ様のご本願力であり、智慧と慈悲のお働きです。南無阿弥陀仏です。私を彼の岸、おさとりに導かずにはおかないという親心です。
浄土真宗の門徒のお墓には多く「南無阿弥陀仏」とか「倶会一處」と記されていますが、これは石を拝んだり、骨を拝んだりするのではないよ。先祖から伝えられた大切な念仏の教えをしっかりと聴聞して、かけがえのない人生を生き抜き、生涯を全うしたときにはまちがいなく、ともに一つアミダ様のお浄土、彼岸でまた会えるよと教えてくださっているのです。
その意味で、お彼岸には何よりも先ずお寺に参って御聴聞をいたしましょう。
鷹谷俊昭「月々の法語(上巻)」(探究社発)より
念仏の鏡
2004年2月
子は親の鏡である
子を見れば親がわかる
念仏はわが心の鏡
念仏いただけば
人間の本心がわかる
鏡が物(光)を映すことによって、物の本質をより鮮明に理解するのに役立つと考えられ特に近代科学では、天体望遠鏡や顕微鏡の果たした役割は極めて大きく、さらに電波望遠鏡や電子顕微鏡にまで拡大されています。経典にも水に映る月光や、手鏡に映る容貌などが随所に記されており、ご本願の中でも第31願と第40願に「猶如明鏡覩其面像」とあります諸仏の世界をみたい人に、「明鏡に自分の顔を映してみるように見せてあげます」という意味です。子を見れば、育てた親がどんな親であるかがわかります。お念仏をいただけば、手鏡に顔を映すように、醜い自分の本心がはっきりとわかります。「心に残るとっておきの話第三集」にこんな話が載っています。元旦の郵便受けに「新聞屋さん、郵便屋さん。明けましておめでとう。旧年中は大変お世話になり、有難うございました。本年もよろしくお願いします」と書いた礼状を吊していたところ、ある年の元日に新聞少年がバイクでやって来て窓越しに、その少年が帽子をとって、その礼状に向かって深々と頭を下げるのが見えたそうです。何という清々しい、何という美しい光景だろう。少年を見ていたこの家の主人は、少年の純真なな心に感動して、涙がこみ上げて来たということです。お念仏の鏡は何処にでもあるということですね。朝日新聞(96.1.12)で、阪神大震災に遭った女性トラック運転手、和歌山の森本佳代子さんの記事を読みました。助手席の二歳の男の子にミルクを飲まそうと、高速を下りたとたんに地震に遭い命拾いをしました。高速を直進した仲間のトラックは落ちた高速道路で即死。死体や怪我人を運び、夕方疲れて工場街に入ったら、おにぎりや水を持った大ぜいの人に会い、生き返ったという。自宅で一休みした森本さんは命拾いした自分に、何かできることはないかと考え、服や下着八百万円分を買ってトラックで被災地に配ったそうです。はいていた靴も小学生の女の子にあげ、帰り道のトイレに裸足で入った、と書かれていました。
『杉本顕俊師「邦語掲示板」(探究社発行)転載』
一つ年を重ねるたびに
2004年1月
一つ年を重ねるたびに 一つわかる
昨年わからなかった事が 今日わかる
年を重ねた 大いなる念仏の日
謹んで新春のお慶び申し上げます。
皆様にはお念仏相続にてお正月をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。本年も又、一緒にお念仏の歩みをしたいと思います。
唐詩選に「一年始有一年春、百歳曽無百歳人」という句があります。一年たてば春は一回やってくる。だが百年待っても百歳まで生きられる人はいないという意味です。
暦の上ではお正月は毎年必ずやって来ますが、人は必ず次の正月が迎えられるとは限りません毎日毎日がかけがいの尊い日々です。そんな日々を私たちは一生懸命、働いて生きていますが私たちどこへ向かっているのでしょうか。鑑みると何一つ確かなものはなっかたのではないでしょうか。
夫婦も子も財も地位も名誉も身につくものではなく、残るのは寄る年波だけです。結局、わたしたちにはお念仏しか残らない、お念仏だけが頼りということでないでしょうか。
親鸞聖人は、ご本願との出遇いについて
「ああ弘誓の強縁、多生にも値ひがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし たまたま行信を獲ば遠く宿縁を慶べ」
「慶ばしかな・・・・・・遇ひがたくひて遇ふことを得たり」と記されました。(教行信証・総序)
「遇う」「めぐりあう」「一期一会」まことに人生は「めぐり遇い」だと思います。人との出合い、本や仕事との出合い、そして先生や仏法との出遇いなど、人生には往々にして不思議な出遇いがあります。
親鸞聖人はお念仏に出遇われ、本当に確かなものに出遇えた慶びに人生の意味をいただきました。
今、私たちは遇いがたくして遇うことを得た阿弥陀如来の大悲の本願を仰ぎながら、お念仏申す身のしあわせを、今年もご一緒によろこばせていただきましょう。
| << 次号 | 前号 >> |
|---|