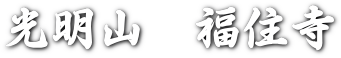| << 次号 | 前号 >> |
|---|
「なむ」は平成2年から毎月発行している福住寺の寺報です。
月報「なむ」
2025年10月
悪いことも「おかげさま」
どのような会合であっても、何かを決めようとすれば必ず反対する者が出てきます。すると反論も生まれ、迷っていたことがかえって明らかになることがあります。反対意見を通して自分の考えが整理され、結論に至るのです。反対する者があるからこそ、一つのことが成就する場合も少なくありません。
徳川家康は「我、天下を治め得たのは、武田信玄と石田治部少輔(三成)のおかげである」と語ったと伝えられます。二人は家康にとって恐るべき大敵でした。しかし家康は、その存在を「おかげ」と受けとめていたのです。
家康は三方ヶ原で信玄に敗れ、命からがら逃げ延びた経験を持ちます。しかし、信玄の死を聞いた時、「これほどの武将が亡くなったのは惜しむべきことであって、決して喜ぶべきではない」と言いました。理由を問われると、「信玄ほどの武将を見たことはない。若い頃から彼のようになりたいと励んできた。隣国に強い武将がいれば、自国でも油断なく武備に心を用いることができる」と答えています。家康にとって信玄は、敵でありながら手本であり、学びの対象であったのです。
一方、石田三成に対しては厳しく、一族を根こそぎ討ち取るように命じました。やがて三成の息子が仏門に入り妙心寺にいると知り、家康が呼び出そうとした時、家臣の本多正信が家康に進言しました。
「三成は徳川家に大きな奉公をいたしました。もし叛乱を企てなければ、殿は大勝利を得られず、天下も徳川のものとはならなかったでしょう」
これを聞いた家康は「なるほど、三成のおかげか。言われてみればその通りじゃ」とうなずいたといいます。
ここに天下人となる家康の度量の大きさが表れているのかもしれません。自らに良いことばかりが「おかげさま」なのではなく、悪いこともまた「おかげさま」と受け取っていかれたのです。
親鸞聖人の語録集といえる『歎異抄』には、「またひとありてそしるにて、仏説まことなりけりとしられそうろう〈仏法に反対する者があるからこそ、仏説が真実であるとさらに証明される〉」とあります。反対する者を拒んでばかりいないで、反対してくれる者の「おかげ」で道が見えた。――そう受けとめる心が大切なのかもしれません。
October 2025 Issue