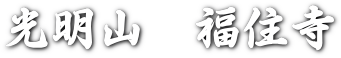月報「なむ」
2002年
薇に当たった
2005年12月
お宮やお寺へ行くと、「おみくじ」というのがあり、大きな筒を振って出た竹の棒の記号により、薮札をもらうと、吉凶・勝負・縁談・失せ者など、運勢や予言が書いてあります。もとは神意を占う方法の一つであったものが、陰陽遣の星占い(九星に五行・方位を組み合わせた八卦を、人の生年に当てて書凶を占う方法)や洋風の占星術(星座や星の運行によって運勢や書凶を占う)など、若い人たちの間にも流行しています。当たるも八卦、当たらぬも八卦といって、占いごとは余り本気で信じていないようですが、中には本気で信じる人もあるようで、旧暦の六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)などは、今も結構本気で使われています。何れにしても科学的ではないし合理的な根拠はなく、デタラメで迷信邪教の類であると断言できると思います。
湯泉津(ゆのつ)の安楽寺で服部範嶺和尚の説教がありました。「往生は千人に一人、まるで富薮に当たるようなものだ。」とお話しになったとき、高座の下で聞いていたオ市さんが、突然立ち上がって叫んだそうです。「その敦、わしに当たった、当ててもろうた。」と。オ市さんはこの時の心境を帝に残しました。「わたしゃしあわせ。官がいらぬに、富があたりて。当ててもろたよ、 六字の官を。日にち毎日、これを楽しむ。」 『正信偽』には「弥陀仏の本願念仏は、邪見騎慢の悪衆生、信楽受持すること甚だもって難し。難中の難これに過ぎたるはなし」とあり、ご和讃の首導讃「仏号むねと修すれども、現世をいのる行者をば、これも雑修となづけてぞ、千中条一ときらはるる。」で、千中条一とは「千人のなかに一人も生まれない」という意味で、「万不一生」つまり、万人に一人も生まれないという泉現もあります。宝くじで特等か一等常が当たるようなものでしょう。 ひとたび信心をいただけば、今度は空鼓なしの総当たり、百人は盲人ながら、千人は千人ながら 全景がお浄土に往生し、さらに必至減反の願により、全員が成仏できるという、「お念仏で浄土が当たるよ」ということです。
『杉本顕俊師著「法藷掲示板」(探究社発行)より転載』
佛と浄土
2003年11月
動物たちは年を数えない
人間のみが年を数え
老いと死に気づき
やがて、佛と浄土に遇う
四季がめぐると、草や木が芽吹き、花咲き、実を結び、やがて凋落します。草木は毎年これを繰り返しますが、歳を数えることはありません。森の動物や小鳥たちも、子を産み卵を温め子育てをして、命をはぐくみ、年々命を受け継いでゆきますが、動物たちも歳を数えることはありません。 ただ人間のみが歳を数え、成長と成熟の中で老いを知り、やがて近づく死に気づくのです。40億年の歳月を親から子へと受け継がれた生命ですが、命をリレーした個体、一人ひとりの命は、せいぜい7・80年ないし100年で終わり、長い長い生命の鎖の輪の一つとしての使命を終えます。
地球上の生命がどうして始ったか、どのようにして生命が承け継がれたか、科学は多くの謎を解いて来ましたが、生命はなおも無限の謎に満ちてます。太陽系や地球が生まれたのも、地上に生命が誕生したのも、全てが偶然のことに過ぎないと言われています。そうかも知れません。それでもまた、多くの人びとは、生命の不思議の中に、個々の生物の中に、この生命を育てはぐくんだ自然の意志のようなものの存在を体感しています。そして人びとは、生命の根元にある自然の意志を、仏と名づけ、神と呼びました。人類文化の多様性の中で、実にさまざまな神仏が生まれ、多種多様な宗教が現れました。
仏教では、自然の意志は、法・真如・涅槃・智慧・悟り等々さまざまな言葉で表現され、さらに人格的な存在として仏・如来・菩薩などの像が語り継がれて参りました。こうしてわたしたちは、仏に出遇い、浄土(仏国)に出遇いました。それらの存在は自然そのものではなく、「自然の中にあって、自然や生命を在らしめている何ものか」ですから、その存在は証明できませんし、証明する必要もありません。ただ、そのような存在を認識するか否か、仏や浄土を信じるか否かなのです全てを否定して無の世界へ死にゆくか、仏を信じ、再会を期して浄土へ生まれてゆくか、それはあなたの自由です。
『杉本顕俊著 「 法語掲示板 」( 探究社発行 )より 』
今日に生きる
2003年10月
わたしたちはいつも「今日」しか生きていない。
昨日は永遠に去り、明日は永遠の未来だ。
「今日」の一日をお念佛と共に生きる。
人は誰でも「現在」しか生きられないのです。昨日や去年は二度と帰らず、過去として永遠に去りました。「十九の春よ、もう一度」と言っても青春は戻って来ません。明日も、明後日も、目前ですが、まだわたしの手は届かず、未来を先取りして生きることは不可能です。もちろん明日のために食事の支度をし、明年の仕事の計画を立て、老後のために貯えるというように、未来のために予定・計画・準備はできますが、その未来まで自分が生きられるかどうか、さらに、その未来まで果たして現実のものとなるかどうかも、全く何の保証もありません。江戸時代の茶人千宗旦(利休の孫)は、新築した茶室の命名を大徳寺の清厳和尚に頼もうと思い、和尚を招待しました。ところが約束した時間に和尚が来ず、宗旦は別の急用のために出かけることになりましたので、弟子に「和尚さまがお見えになったら、事情をお話して、明日もう一度お越しいただくようお願い申し上げておくれ」と言い残して外出いたしました。
程なくやって来た和尚は、弟子から宗旦の伝言を聞き「懈怠比丘不期明日」と書き残して帰ってゆきました。「遅刻するような怠け者の僧であるわたしは、明日のことはお約束しかねます」という意味です。帰宅してこれを見た宗旦は、一寸先はわからぬ人生に、明日の約束を求めた自分を反省し、直ちに大徳寺を訪ね、自作の歌を呈しました。
【今日今日といいてその日を暮しぬる 明日のいのちはとにもかくにも】
明日のいのちもわからないのに、大切な「今日」をおろそかに暮らしているのは愚かなことでしたという反省と、和尚の教訓への感謝をこめた歌です。宗旦は和尚の教えにより、この茶室を「今日庵」と名づけ、今日庵は現在も裏千家の庵号になっています。
九条武子夫人の歌に「見よや君、あすは散りなむ花だにも、命の限り今日を咲きつぐ」とあります今日に命を托して生きる花の健気さに学びたいと思います。
『杉本顕俊著「法語掲示板」(探究社発行)より』
報恩講とは・・・親鸞聖人のおかげ・・とは?
2003年9月
冷夏のままに夏が去りすでに、秋風に揺れてコスモスが咲き乱れています。9月は当寺の報恩講です。今月はその報恩について述べてみます。
報恩講は、親鸞聖人のご命日1月16日(旧暦11月28日)に勤められつ報恩の講(法会)です。親鸞聖人のひ孫にあたる本願寺三代覚如上人が親鸞聖人の三十三回忌に「報恩講式」を著されて、法要の形式でもって親鸞聖人の徳をたたえられたのが始まりです。
親鸞聖人が九十年の生涯をかけて、どんな事があっても必ず救うと常に働いてくださる阿弥陀如来様の働きの真実なることを教えてくださったご恩を喜び、報謝させて頂く集いです。
このように報恩講は親鸞聖人のご恩に報いる心をあらわすつどいですが、私たちはどのようなご恩、おかげをいただいているのでしょうか。覚如上人はその著「報恩講式」に聖人の高いお徳を三つの点から讃歎しておられます。
その第一は、浄土真宗を興してくださったことです。幼少のころより様々な、修業・学問の末に法然上人の門に入り念仏の教えを得られ、教行信証を著して、末世の凡夫にふさわしい、悟りに至る道をお示しくださったことです。
第二は、阿弥陀様のご本願は、私のためにこそおこされ、南無阿弥陀仏の名号として送りとどけられたのですから、そのおいわれを聞かせていただく信心一つで、真実の幸せをちょだいできると示されました。私のつまらぬこだわりやはからいを捨てることが本願にふさわしいと、どんな人でも仏になれる道をはっきりさせてくださったお徳です。
第三は、聖人のご指導、ご教化は、ご浄土に帰られた後も続き、滅後七百年以上隔てた今日の私にも、親しく大きな利益を説いてくださるお徳であります。親鸞聖人が書き残された聖教、書物を通して声を聞くことができます。
この三つの高いお徳に報いるには、この世に生命あるかぎり、自ら進んで仏法を求め、信心をいただいて念仏とともに、生れてきてよかったといえる人生を送りたいものです。
降誕会
2003年6月
五月二十一日は浄土真宗をお開きになった親鸞聖人のお誕生日です。聖人がお生まれになったおかげで、真実の教えによって、真実のしあわせにいたる人生を生き抜くことができるのですから、このおめでたい日をお祝いせずにはいられないのです。
仏教には人間に生まれるということに二つの説明があります。一つは人間に生まれることは、苦であると言い、人間だれでもが受けなければならない四苦八苦の第一にあげてあります。生まれること、がなければ老病死はないのですから、生は死の本であり、生まれ死に、生まれ死にするくりかえしが迷いの姿です。
もう一つは、人間に生まれることは、ありがたいことだと言い、源信和尚は、横川法語というお書物の中に、「人間に生まれることおほきなるよろこびなり」と示されました。私たちが人間に生まれたということは、真実のおみ法を聞いて真実のしあわせになるチャンスを与えられたということですから、この得がたい、ありがたい人生を間違わず生きて行かなくてはならないと説くのです。
この二つの教えは一見すると矛盾しているようにも思えますが、実はそうではなく、人生のありかたをきびしく指摘しているものと言えます。
あなたは苦の連続としての人生を送るのか、それとも真実のしあわせになる人生を送るのか、と問いかけているのです。
仏法を聞き、阿弥陀如来様のお導きをいただくか否かは、人生の分かれ道のどちらに行くかを決定する大切な鍵です。
そして、その鍵は自分が握っているのです。真実のしあわせのために、生まれてきてよかったといえる人生を過ごすために、強く明るく生き抜く力を阿弥陀如来様からいただきましょう。
戦争の愚かさ
2003年4月
戦争を「お国のため」とか「平和のため」といって正当化するが、戦争の本当の原因は
(-)財閥グループのお金儲け
(ニ)職業軍人の外国軍への恐怖
(三)政治家たちの宣伝陰謀
などであり、自国民の愛国心を活性化するための口実として「お国のため」や「平和のため」が用いられます。
「平和のために戦う」、というのは「生かすために殺す」「生きるために死ぬ」というのと同じで、全く意味をなさない。「戦わないこと」が平和の第一条件であり、そのためには「敵をつくらないこと」です。つまり不戦と友好が平和への遣です。
考えてみて下さい。石油も食糧も乏しい日本が、本気で戦争などできるはずがありません。
石油(ガソリン)なしでは、航空機も軍艦も戦車も動くことができないことは、小学生にも解ることです。いかに軍備を増やし、兵器を備えても、ガソリンがなくて動かせなければ「がらくた」と同じです。
全食糧の六割・七割を輸入に頼っている日本が、何を食べて戦うのでしょうか。世界中で今も多くの国や民族が戦争をしています。原因は、権力闘争、民族抗争、領土争奪、宗教紛争などが主です。兵器の大部分は国連常任理事国であるアメリカ・ロシア・中国・フランス・イギリスをはじめ経済先進国が売りつけたものです。
政府と軍需産業とが結託して、戦闘機・爆撃機はじめ軍艦・戦車・ミサイル・機関銃・地雷・弾薬などあらゆる兵器を大量に生産輸出して儲けています。その同じ国が、やれ国連軍だ欧州軍だと言って、和平工作をやっているのですから話になりません。兵器の輸出を禁止するだけで、世界の戦争の大方がなくなると思います。こうした事情が理解できないほど人間は愚かではないと思うのに、結局戦争がなくならないのは、やはり儲けたい企業、恐怖をいだく軍人、権カを求める政治家、そして愛国心・民族心・宗教心を高ぶらせる愚かな国民が多いということでしょうか。
お念仏は不戦・友好の平和な宗教でありたいと思います。
『杉本顕俊 師:著「法詩碑示板」(探究社発行)より転載』
かぎりない智慧と慈悲こそ仏の本質である
2003年3月
浄土真宗の教えは、長年聞いていると次第にこんがらがってややこしくなるという声を聞きます。これはどうしたことでしょうか。教えを伝える人の努力が足りないのか、聞く人の仏縁がととのわないのか、残念に思います。
こんがらがることを防ぐために、ここで私は一つの提案をしたいと思います。何事にも基礎と応用というものがあるように、浮土真宗を一言で表現している言葉を見つけ、いつもそれを土台にしながら法話を聞いたり、法談をすれば、ややこしくなることはないと思うのです。お寺での法座は、それぞれが自分のお味わいを述べるので、いわば応用問題のようなものですから。浄土真宗の教えを易しく説いていただける言葉として、『歎異抄』の「他力真実のむねをあかせるもろもろの正教は、本願を信じ念仏を申さば仏に成る、そのほかなにの学問かは往生の要なるべきや」をあげることができます。
さて、このなかで「仏に成る」ということについて注目してみましょう。私たちはよく「たすけてもらう」、「救っていただく」、「お浄土にまいらせていただく」という言葉を聞きます。しかし「仏に成る」ということを忘れてしまっては仏教ではなくなってしまうのです。
仏教は他の宗教と違って、最後の目的は、私が釈尊と同じようにさとりの智慧をえて仏に成り、苦悩を超えることであります。神や仏の救いでは終わっていないのです。
言いかえれば、どのようなすばらしい教えであっても、この私が仏に成れないようでは、その教えは私にとって仏教とは言えないことになります。
私たちが成らせていただく身の上、仏さまとはどのようなお方でしょうか。
仏さまのお徳を、智慧と慈悲であらわします.慈悲とはすべての者を救おうとする心です。一子地とも言います。相手の悲しみや痛みが、自分の悲しみや痛みとなる心です。智慧とは、その相手を救うために真理を深く洞察することを言います。しかし、この私が仏さまの智慧と慈悲を完成していくのではありません。仏さまの智意と慈悲が私の上に完成されるのであります。私の上にあらわれてくださるのであります。その私が何をするべきであるのか大切に考えたいものです。
(本願寺『心に響くことば』 瓜生津隆真師:著 より引用)
元旦の法要は修正会?元旦会?
2003年2月
人の世は一夜のうちに激変することがないわけではありません。しかし、通常は暦の上で一日違っても、昨日と今日、今日明日の間に格別大きな変化もなく、いつの間にか年月が経ってゆくのですが、季節がめぐるある期間を一年と定めたのは人類の知恵でしょう。そして過ぎ去った一年を一応精算し、来るべき年への決意を新たにすることは、人生の旅路を歩む上で、非常に大切な営みであります。一年の最後の夜(大晦日)を除夜というのは「旧い年を除き払う夜」という意味ですが、私たちはたとえ辛く悲しい一年だったとしても「いま生き、生かされている」ことへの感謝の思いをこめて、一年の終わりの法要(除夜会:じょやえ)をおつとめします。そして、一夜明けると新年で、新春のご挨拶を、まず阿弥陀如来さまに申し上げ、新しい一年を御仏の恵みのもと、お念仏もろとも、こころ豊かに日々を送ることを誓う。これが元旦の法要(元旦会:がんたんえ)であります。当山でも除夜会・元旦会がつとまりました。
先般、お参りに伺った数名のご門徒の方々から「修正会と元旦会はどのように違うのか?」というご質問がありました。同じように疑問に思われていた方もおられることと思い今月号にこの件について掲載いたします。修正会も元旦会も上記のように元旦にお勤めする法要ですが、勅願寺では「修正会」といい、一般寺院では「元旦会」といっています。その法要がつとまるお寺によって言い方が違うわけです。また「会」は「かい」とは読まずに「え」と読み、「法会・法要」という意味です。そして「勅願寺(ちょくがんじ)」というのは、「天皇の願で勅命により建立された寺院や天皇の勅命により寺号を賜った寺院」という意味であります。ご本山の本願寺も亀山天皇より『久遠実成阿弥陀本願寺』という寺号を賜った勅願寺であります。(第四代善如上人のころかといわれています。)それでご本山では、毎年10月12日の亀山天皇の祥月命日に亀山天皇聖忌法要をお勤めしているのです。
二月には、四日間の門信徒研修会を予定しております。
祈らぬ宗教
2003年1月
日本固有の神道は、祭政一致の氏族社会を形成していました。そこへ外来の仏教が伝来し、排仏か崇仏かの争いの後、聖徳太子の努力で日本に受け入れられ、十七条の憲法に盛り込まれました。その後、仏教の神道化、呪術化が進み、神仏習合の異様な仏教へと変身し、奈良・平安時代には、鎮護国家加持祈祷を事とする国営の呪術的密教へと転落してゆきました。
平安末期に流行した浄土信仰・弥陀信仰は引声念仏・、不断念仏を盛んにしましたが、自力行としての聖道的念仏であり、源信和尚の『往生要集』は欣求浄土のムードを盛り上げ、臨終来迎がいっそう貴族たちの間に拡まりました。
鎌倉時代に入り、法然上人が他力念仏(専修念仏)を開拓され、従来、プロの念仏僧によって称えられていた聖道的念仏を排し、個々の信者の念仏集団へと変身しました。専修念仏では呪術性を払拭し、現世祈祷を排除して、本願信順の念仏となったこと、また古代国家権カとの関係を断ち、個人救済の宗教として、新しい念仏信仰が出発しました。
さらに親鸞聖人の浄土真宗では、
①信の一念に往生が決定し、臨終来迎を待たず、救いが成立する。
②往生決定の後の称名念仏は仏恩報謝として十方衆生に廻向され、一念多 念の義を否定する。
③老少善悪の人を選ばず、悪人正機・女人正客の宗風が鮮明された。
④名号一つに一切の神仏の万徳がこもっているため、阿弥陀仏の一仏、念仏 の一行で充分であり他の雑行雑修を排した。
などの特徴が次第に鮮明となりました。
中でも、最も目立った特徴は、加持祈祷の呪術的な念仏を拒否し、他カの信心を中心に据えた「祈らぬ宗教」「称名報恩」の宗義でありました。無我を主張する仏教本来の体質をとりもどし、霊魂不滅を否定して、慰霊や鎮魂を排除し、現世祈祷を徹底的に追放し、近世仏教へ大きく転換しました。
神仏習合によって著しく歪曲されていた日本の呪術的仏教が、仏教本来の英知と信心を中心とする救済の宗教へと進化発展したことは、まことに一念仏者として喜びに耐えません。
『杉本顕俊師著「法語掲示板」(探究社発行)より転載』
| << 次号 |
|---|